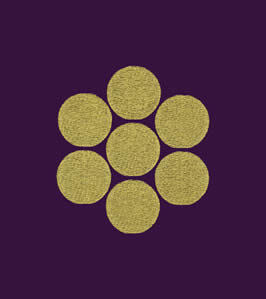△男たちの大和/YAMATO(2005年 日本 143分)
監督・脚本/佐藤純彌 音楽/久石譲
出演/仲代達矢 鈴木京香 反町隆史 中村獅童 松山ケンイチ 渡哲也
△昭和20年4月7日、大和撃沈
学校に通ってた頃、ぼくは戦争というものにまるで興味がなかった。
戦争の話を聞かされるとき、それはたいがい惨めな話で、戦争は悪いことだとずっと聞かされてきたから、そんなものに興味を持つはずがないよね。小学校の時代も、プラモデルで軍艦や戦車を作ってる友達がいたりしたけど、ぼくの作るプラモデルといえばほとんどが怪獣かアニメのキャラクターで、ときどき城とかは作ったりしたけど、兵器や武器にはまるで無関心だった。
信じられないような話ながら、戦艦大和も零戦も、木造だとおもってた。
「くろがねの浮かべる城」という表現が戦艦を指すものだってことも、まるで知らなかった。
ていうより、そもそも、戦艦や戦闘機とかについて考えなかった。でも、人間、年は取るものだよね。今では、大和も零戦も木造じゃないってことくらいは知ってる。で、その『大和』のことだ。戦艦大和というのはなんとも不運な軍艦で、ぼくらが学生の頃には、反戦の象徴として扱われることがままあった。
「世界3大バカは万里の長城、ギザのピラミッド、戦艦大和」
とかいわれ、無用にでかいものを作ったからだと説明された。誰がいった言葉かということはひとまずおいて、でも、そんな世界的なバカのひとつなのに、一方では、世界最大最強の戦艦と讃える。大和にしてみれば、迷惑な話だろう。
この艦は、日本を守るために造られた。たしかにその図体のせいで、パナマ運河こそ通過できないけど、世界のどの軍艦よりも頑丈で、射程距離が長く、そして最強の砲弾をぶちこむ。その方針で造られたはずが、沖縄決戦の応援に充てられ、菊水作戦が発動されるや、制空権を奪われた戦場めがけて出撃した。すでに正規空母もない状況だから、わずかな航空機の護衛すら無く、蜂の巣にされ、沈められた。
戦闘能力を失った時点で、すでにそれは完璧な敗北といえるから、もしも、敵とはいえ日本人の人命もまた尊重するという思想が米軍にあれば、どこかの小島か岩礁に擱座するのを想定して、攻撃をやめるべきだったろう。そうすれば、乗組員の半数以上は生還させられたはずだ。
けれど、戦争はそんな甘っちょろいもんじゃなかったんだろうね。乗組員3016名中、2740名が戦死した。当時、こんなはずじゃなかったと大和を造り上げた人達はおもったろうし、これでいいのだとおもった日本人はたぶん稀れだったろう。
で、現代人の感覚はどうなんだろね。大和が激闘を繰り広げたときの血の量も赤さも匂いも薄まり、冷静な第三者があれこれと分析して、大和の持っていた意義や覚悟や悲劇性よりも、軍国日本の象徴のひとつとして捉えられてるんだろうか?大和は、これまでにもいろんな映画に登場してきた。多くの場合、反戦あるいは悲劇を語る際、引きずり出された。そうでない大和を描く場合、宇宙に飛び出すしかなかった。
この作品はどうかといえば、やっぱり反戦映画だったとぼくは受け止める。
反戦を訴えるのは大切なことだとおもうけど、ひとつひっかかったのは、長嶋一茂演じる臼淵磐少佐だ。文人になれるような素質を持った人だったんだけど、海軍の軍人になりたいという意欲の方が勝って海兵に進んだ。死後進級して少佐になったから大和出撃時は大尉だった。経歴や階級はさておき、この人は、出撃の前夜、海兵出身の若手将校と学徒出身の予備士官との間で論争があり、
「今次作戦につき、国の為に殉じることは意義ありやなしや」
というような論争があり、あわや乱闘になりかけたときに割って入り、
「敗れて目覚める。祖国の新生に先駆けて散ることこそ本望なり」
というような台詞をいったことになってる。ただ、生還者の証言からちょっと信憑性に欠けるともいわれてるらしい。たしかにそうかもしれないね。出撃の前夜、ここまで達観してたら大したものだけど、たとえ、そんな余裕があったにせよ、ちょっといえない。まあ、このあたりの話は長くなるからしないけど、反戦映画としてこの作品が製作されたんなら、大きな意味を持った台詞ってことになるんだろうね。
ただ、こんなことがあった。沖縄へ行ったときのことだ。ひとりの老人と知り合った。その人は「都内でラーメン屋をやってるんだ」といっていたんだけど、話を聞けば、戦争当時は現役兵で、飛行機の操縦士だったらしい。主に一式陸攻っていう陸上攻撃機を操縦してたそうで、あるとき、トラック諸島に派遣された。
すると、
「大和がいたんだ」
やっぱり、どでかい戦艦だったらしい。長門が隣に繋留されてたけど、比べ物にならないバカでかさだったらしい。いや、ただでかいだけじゃなく、たとえようもなく美しい艦影だったらしい。くわえて、
「あいつがもっといろんな戦場に出て、主砲をぶっぱなしてりゃあなぁ」
そのおじさんにとって、大和は当時も今も最強の守り神なんだろう。ラーメン屋さんは、いまにも泣きそうな顔だったけど、胸をはって、なんとも誇らしげに、こういった。
「大和は、ほんとに凄かった。あいつに勝てる戦艦は、世界のどこにもねえんだ」