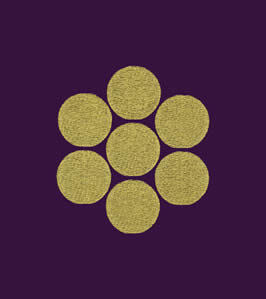◇劇場版タイムスクープハンター 安土城 最後の1日(2013年 日本 102分)
staff 監督・脚本/中尾浩之 撮影/小川ミキ
美術/吉田透 装飾/中山大吉 スタイリスト/Baby Mix
結髪/新宮利彦 特殊効果監修/菅原悦史 音楽/戸田信子
cast 要潤 夏帆 杏 宇津井健 上島竜兵 時任三郎 小島聖 嶋田久作 竹山隆範 吉家章人
◇ただのタイムトラベル物になってしまった
ぼくは実は『タイムスクープハンター』を贔屓にしてる。
毎回楽しみにしてるってほどではないけど、
でも、ときおり、テレビ欄で目に留まると、チャンネルをひねる。
なにがいいかっていえば、結髪と装束と汚しで、
どこまで現実味のあるものなのかはわからないんだけど、
すくなくともほかの時代劇とかよりはリアリティを感じられる。
ノンフィクションを装ったフィクションなんだけど、
このシリーズの場合、世にいうモキュメンタリーとは一線を画している。
なぜって、要潤がいるからさ。
タイムワープをしてしまった瞬間に、それはもう物語であることを語ってる。
でも、こんなことがあったのかもしれないな~とおもうのは、
歴史上の事件や事実とされることを巧みに取り入れ、
製作者側のほんとうはこうだったんじゃないかっていう考えを披露してくれるからだ。
ところが、残念なことに、この劇場版は最初から物語になってる。
要潤とそのまわりの人達の話がなんだか絡んでて、
歴史上の好きなところに飛ぶことのできる技術がちょっと不安定だ。
安土城はなぜ燃えたのかっていうことを知ろうとおもえば、
そのいちばん原因となった場に最初から飛べるはずで、
まあ、そうならないように夏帆の憧れみたいなもので物語を展開させるんだけど、
そもそもテレビシリーズは庶民の暮らしのおもしろさがあるから観ているわけで、
いたずらに物語が込み入ったり、背景が大きくなったりしたところで、
それはこのシリーズが本来追いかけていたものとは異なるものなんじゃないかって、
ちょっとおもったりするんだよね。
本能寺の変から安土城炎上にいたる過程で、
博多の豪商、島井宗叱が所有することになる楢柴の行方をからませて、
話を上手にうねらせてはいるものの、
でもやっぱり安土城の炎上に関しては、
明智方の手が延びてこないのはちょっと腑に落ちない。
途中からリアリズムが要のノンフィクション劇のはずが、
なんだか少年ドラマシリーズのタイムトラベル物になっていっちゃったみたいな感じで、
枠はたしかに東京空襲もあったりして大きくはなってるんだけど、
その分、なんだか別な物語になってしまってるみたいで、
ぼくとしては、ちょっぴり残念かもしれない。