
週に一度ではあるけれど乗馬をしてるんだが、以前の覆馬場で乗ってた環境と違うんで、天気予報が気になる。月曜か火曜で、天気のいいほうに乗馬に行きたい。(別に両方行ってもいいんで、正確にいうと、天気の悪いときには行きたくない、ってことになるか…)
月曜の朝までの天気予報を見てると、火曜日は朝から小雨になる可能性もあったんだが、同じ日の夜の予報では、火曜日の雨は夜からってことなんで、無事いつもどおり、本日火曜日に乗馬に行くことになった。
そしたら、今朝の天気予報では、4月下旬の陽気になるという。シャレで半袖で行こうかと思ったが、さすがにやめといた。
でも、馬装してたら、もうダメ、やっぱ暑いわ

(←たぶん10度超えた程度だろうが) やっぱりシャツの袖をまくって、手袋ナシで乗ることにする。ちなみに、私のふだん使ってる手袋は、軍手みたいなタイプでゴムのポツポツの滑り止めがついてるんだが、ゴム手綱を持つと何だかかえって持ちにくいので、ゴム手綱のときは寒くないかぎり素手で乗ろうとすることが多い。

で、近頃すっかりおなじみになった「ミラノ」に騎乗。
ミラノは、私個人として、いま乗ってて一番おもしろい馬であることはまちがいない。ただし、乗って面白いってぇのが、イコール好きだってことにはならないのが、馬の難しいところだけど(←難しいのは、おまえの考え方だという声もあり)
で、先週にひきつづき、小さいほうの角馬場で練習。
小さいって言っても十分な広さなんだが、この日はなかに障害が4組置いてあるんで、「斜めに手前を替え」ができない。しかたないんで、ときどき半巻きして手前を変える。
どうでもいいけど、練習に来る人が少ないもんだから、先週同様マンツーマン指導になってしまった。それはかまわないというか、ありがたい機会なんだけど、いざ一対一でジッと見られてると、乗ってて緊張する

気ぃ抜いてフラフラする時間がないから。
まあ適当にフラットワーク。速歩では、障害とかあって狭いなかでも、どうにか巻乗りを入れて、あとは長辺で歩度を伸ばしたり短辺で詰めたりする。
駈歩に移行、小さめの輪乗りでクルクルと、まわる。何周かしたあと、最後すこし歩度を伸ばしてみようかって合図すると、あいかわらず反応よくてビュンって伸びる。
ここで先生から「駈歩のとき、ヒザと爪先が外を向いている。進行方向に向けるように」と指摘。爪先は無意識だけど、ヒザはわざと開いてるようなとこあったんで、微妙に直す。
以前から、どうしてもヒザでしがみついちゃうような乗り方になってたんで、ヒザに内側向きの力を入れないように、このごろはヒザ開いて鞍から離して乗ったりするようにしてたんだけど、人体ってヒザの向きに爪先も向くようにできてるから、爪先まで開いちゃった。開くのはヒザぢゃなくて股関節でなくちゃいけないのかな。そう言やぁ、むかし股関節から「脚をローリングさせる」とかって理論を教わったなーとか思い出しつつ、微修正。
駈歩の二度目は、輪乗りを詰めたり開いたりの練習。ミラノの駈歩は、すぐ速くなるんで、グッと抑えながら輪乗り。右手前で内に傾くような感じがする、馬の身体の傾きが左回りに比べてハッキリとする。こういうとき人が左(外)に体重かけると、よけい馬がバランスとろうと右(内)行っちゃったりするんで、鞍の真ん中に、左右均等におしりに体重がかかるように、座るように心掛けて、ゆっくり直すようにする。
さあ、そしたら障害やりますか。微妙な位置取りで障害4組置いてあるんだけど、速歩で数回ウォーミングアップしたら、ぢゃあ今度はまわってみましょうかってことになって、一回一回ちがう経路どりで駈歩で飛んでまわる。
対角線上に二つ置いてあって、その間隔は普通4歩、ギュンギュン行っちゃったら3歩でも行けちゃうところだが、そこは毎回4歩で行くようにがんばる(グッと手綱握ってこらえる)。
「最初飛んだら、右まわって二つ飛んで、左にまわって最後飛ぶ」とか、「最初飛んだら、左まわって飛んで、つぎ右まわって二つ飛ぶ」とか、よく言えば自由自在の設定、実際は単なる猿回しのサル状態になって言われるままに飛ぶ。
何度かやるが、やっぱ右の回転がヘン、内側に入ってしまう。狭いコースどりなので、少し内に入ってしまうとラインにうまく入れず、障害に向けての直線助走部分が短くなって、かなり苦しい。
「そこの回転、難しいですか?」と聞かれるが、「いいえ、大丈夫、できます」と答える。物理的には確かに全然大丈夫なラインなんだけど、馬が内側に入っちゃうんで厳しくなってる。直しながら回るんだけど、例によって、飛んだ後のミラノは勢いがついてるんで、簡単には直せない。「あー、駈歩の輪乗りで、内に入ってきたのが今出てる、もっと入念に練習するんだった」と後悔しながら、走りまわる。
そんなこんなで、まあ何とか最後は90センチくらいの垂直も含めて、どうにか飛んで、練習終了。ミラノは、ちょっとくらい私が誘導ヘタでも、飛んでくれちゃうんで、すごい。もしかしたら、私をもうひとつ上の高みに(←ただ障害の高さだけの意ではない)連れてってくれる馬なんぢゃないかと秘かに期待している。

最後に、「歩度を伸ばした速歩では、脚を使うことを意識しているせいか、下半身の形がよい。ただし、ふつうの速歩では、ヒザに頼ってるような形になっており、そのぶん足の部分が不安定。アブミがぐらぐら前後するのは、そのせいです。」と厳しいご指摘ありました。やっぱ、そんな簡単にうまくなってたりは、しないのね

 名作とかなんとかいうのと、私の好みとは一致しないものなのかもしれない。
名作とかなんとかいうのと、私の好みとは一致しないものなのかもしれない。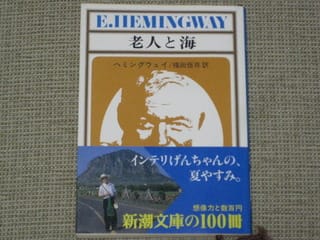
 名作とかなんとかいうのと、私の好みとは一致しないものなのかもしれない。
名作とかなんとかいうのと、私の好みとは一致しないものなのかもしれない。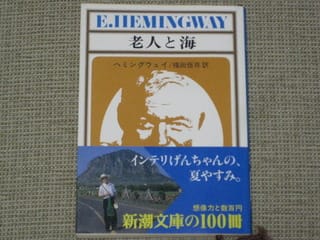












 (←たぶん10度超えた程度だろうが) やっぱりシャツの袖をまくって、手袋ナシで乗ることにする。ちなみに、私のふだん使ってる手袋は、軍手みたいなタイプでゴムのポツポツの滑り止めがついてるんだが、ゴム手綱を持つと何だかかえって持ちにくいので、ゴム手綱のときは寒くないかぎり素手で乗ろうとすることが多い。
(←たぶん10度超えた程度だろうが) やっぱりシャツの袖をまくって、手袋ナシで乗ることにする。ちなみに、私のふだん使ってる手袋は、軍手みたいなタイプでゴムのポツポツの滑り止めがついてるんだが、ゴム手綱を持つと何だかかえって持ちにくいので、ゴム手綱のときは寒くないかぎり素手で乗ろうとすることが多い。


 )
)







