大坂なおみ選手の棄権は、残念だった。
4大大会3連覇を逃しただけではなく、今後どうなるかも不透明。
この件で、思い出したのは二つ。
一つは、平成天皇のご退位。
国に相談していたが、聴く耳を持たなかったため、直訴して、時間はかかったけど、思いはかなった。
ソフトランディングできた。
世論が味方したのも大きかった。
もう一つは、片山晋呉選手。
これは、プロツアーの選手としての行事で、スポンサー向けのサービスとして定着していたイベントで起こった事件。
これは、どんな客だったのかはわからないが、かなり片山選手の責任が重い。
よっぽど練習したかったのだろうが、この1日は、スポンサーのお客様と回ることが決まっておりそれが、前提となって、選手も参加していたはず。
特に、人気低下の男子プロツアーにおいて、スポンサーを無視した責任は、重い。
今回の大阪なおみ選手の場合、事前に誰かに相談したのか。
もししていたのであれば、その相談を受けた人が動なかったのが、悪い。
もししていなかったのであれば、大坂選手のやり方は、やはり乱暴だったということになるか。
しかしそれを受けた、全仏運営サイド、マスコミ側は、一方的に大坂選手を悪者にしてしまった。
大坂選手からの、いきなりの一方的な宣言だった可能性もあるが、運営側の最初の対応は、もっと悪い。
選手と運営側は、お互いにパートナーで、どちらが上とか下とかいう関係ではないはずだ。
お互いに、着地点を見つけて、近い将来、大坂選手のすばらしいプレイが見られることを期待したい。
幸い、グランドスラム側もそのような方向に舵を斬ったように見える。
全仏1回戦は、珍しくLIVEで見ていたが、調子は上々に見えた。
これを、乗り越えて、東京オリンピックで復活した姿を見せて欲しい。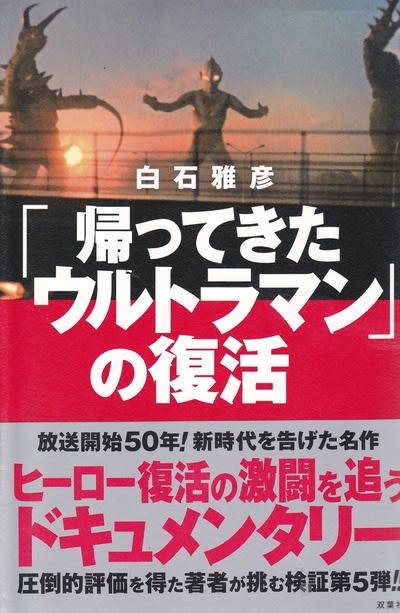
本書は、シリーズ5作目。
見送っていたら、書評で評価されているので、遅ればせながらゲット。
題名は、"後から後悔する"的な題名だが、すばらしい1冊だった。
改めて感じたのは、微妙な世代の違い。
私は、今から思うと、小6~中1。
怪獣から卒業する時期。
著者は、私よりちょっと若く、逆に、この時期がピーク。
だから熱も入るし、リアル感も強い。
私は、塾通いもしていた時期だったろうし、少ししか見なかったと思う。
でも、一部の怪獣の名は覚えている。
ウルトラQ、ウルトラマンは、当然全部覚えている。
私世代にとっては、ウルトラセブン以降、間が空いて、二番煎じ的に復活したイメージだが、本書を読むと、感涙ものの復活だったらしい。
円谷プロ自体ピンチで、東映傘下に入り、円谷プロも第二世代。次の作品も、目途が立たない状況だった。
その原因の一つがスャRンもの。
まさに私の世代ど真ん中。
怪獣物が一服して、巨人の星、サインはⅤ、柔道一直線をみんな見ていて、怪獣物は、過去の物になっていた。
ところが、ウルトラマンの再放送や、ウルトラファイトで、特撮ものの復活の兆しが出て来た。
ウルトラファイトもちょっと見た記憶があるが、本当のウルトラマンを経験した世代からは、ひどい作品だった。
そして、円谷一氏が、英二氏の後任として、円谷プロを率いるようになり、帰ってきたウルトラマンの企画が通る。
その後も、順風満帆ではないのだが(小学生高学年を狙ったところ視聴率が上がらず、ターゲットを低い年齢層にしてから、盛り上がったとのこと)、結果成功をおさめ、その後のウルトラシリーズの発展(ファミリー化?)につながる。
攪乱要因としては、仮面ライターシリーズのヒットと、同じ円谷プロのミラーマンなどの特撮もの。
仮面ライダーがよりヒットしたイメージがあるが、がっぷりよつの視聴率だったそうだ。
ストーリーの背景についても、沖縄人の疎外感、キリスト教徒の純粋信仰感、学生運動等、製作者の生い立ち、世相などを考慮し、推察していて、面白い。
その中で驚くのは、脚本家陣、プロデューサー陣、俳優陣の豪華さだ。
東映傘下となったことと、TBSから円谷に来た一氏の貢献が大きい。
ということで、BDシリーズをゲットしてしまった。
昭和の名脚本家、名俳優達の作品をじっくり楽しみたい。
円谷一氏は、大赤字だった円谷プロを、帰ってきた・・・、ミラーマンで取り返し、急逝された。
典型的な働き過ぎだったという(糖尿、高血圧)。
第二次ウルトラシリーズに取り組みたいということだが、エースの時は、私は、すっかり中学生になっており、付き合いきれないかもしれない。
変身の仕方も、男女の隊員が、腕をクロスするスタイルとなり、これは、アダムとイブ?
ウルトラマンシリーズの変容を象徴する変化だという。
著者の白石さんの、資料発掘力と、構成力に大拍手。















