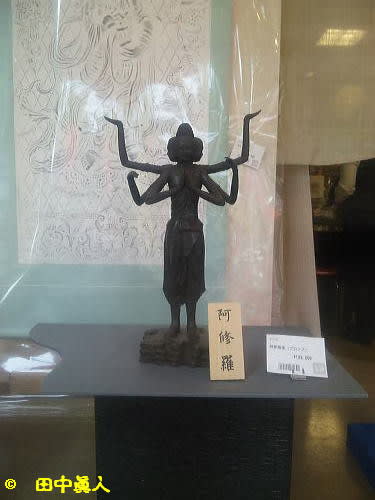一ヵ月半ぶりに入店した「はま寿司」。
今回も新聞チラシに誘惑されて出かけた。
くるくる回転寿司屋が提供するラーメンだ。
前回はエビ味噌ラーメンを食べた。
ラーメン丼ではなく椀に盛ったエビ味噌ラーメン。
とにかく味が濃いかったラーメン。
エビ味噌が濃くすぎるのだ。
麺は細麺の柔らか麺だった。
今回のちらしはエビ味噌ではなくカキである。
どんな味なのか舌で感じてみたかった。
クラブを終えたかーさん迎えついでに寄った時間は丁度昼どき。
入店とともに器械で操作。
人数、席を選んで案内を待つ。
しばらくすればどうぞと席番号を記した札を手渡される。
カウンター、テーブル席はほとんど満席状態。
美味しさの評判が高いのだろう。
子供連れは見られない。
時間に余裕がある家族連れがほとんどだ。
「はま寿司」は平日が一皿90円。税抜き価格である。
この年の3月末までは税込みで94円。
4月ともなればおそらく97円になるであろう。
テレビで盛んにコマーシャルしていたかっぱ寿司は「へい へい へいじつ きゅうじゅうにえん」だった。
が、昨年末の12月からは105円になった。
それから聞こえなくなったコマーシャルソングは耳に焼きついたままだ。
回転寿司チェーン店はどことも競争。
くら寿司はラーメンに加えてイベリコ豚丼まで売るようになった。
過当競争の回転寿司はどこまで行くのか、である。
消費者はお目当てで行くのもあるが、やはり寿司ネタだろう。
かれこれ40年前のことだ。
大阪千日前の水掛不動尊辺りにあったにぎり寿司屋さんに度々出かけていた。
とてつもなく大きなネタだった。
マグロ、ハマチはぶつ切りのネタ。
隣のおじさんが食べたとたんに、ぶっと飛びだした。
ひと口では食べることができないぶつ切りはとんでもない大きさだった。
アナゴなんてものはまるまる一尾だった。
何口で食べたか・・・。
ウナギはさすがに一尾でなく、半分切り。
厚みがあったウナギも一口で食べきらない。
先代を継いだ若い寿司職人が握っていた。
そんなネタを出していた寿司を20皿も食べていた。
若いころのことだ。
今でも寿司店があるのかどうか知らない。
可愛かった嫁さんの顔は覚えているが、店名が思い出せない。
そんなことを思い出しながら回転レーンを流れるにぎり寿司を見ていた「はま寿司」は3月6日から19日までは春の味わいの「春ねた祭」。
漬けほたるいか、特製漬けまだい、あおりいか塩レモン、生しらす、創作かにちらしがお勧めだそうだ。
流れるレーンにそのうちのひとつが登場した。

あおりいか塩レモンだ。
レモンは食べないからそっと横に置く。
もちろん種も要らない。
甘タレ造り醤油でいただく。
まぁまぁ美味いあおりいか。
我が家はイカ派。
好みの寿司ネタであるから、漬けほたるいかも手を伸ばす。

ホタルイカの漬けは美味いのに決まっている。
漁師が船漁している最中に獲ったイカを器にぶっこんで醤油をたらたら。
数時間漬けこんでおけばイカが吐き出す墨と混ざって味が濃くなる。
そういう仕方で造りこんだのかどうか判らないが美味いのだ。
次もまた、イカであるが、レーンに廻ってこない。
メニュー画面を押して頼んだ姿やりいか。
いくら待てどもやってこない注文の品。
メニューを押して頼んだ品は到着間近になれば、チャイム音が鳴りだすのだが・・・。

鳴らないが廻ってきた姿やりいかに思わず手をだした。
食べていたら音が鳴った。
2皿も食べれば飽きてしまう。
そうそう寿司は食べてられない。
今日の目当ては牡蠣ラーメンである。
新聞ちらしに載っていた割引券は牡蠣ラーメンの税込み294円を特別値段に・・・。
ものは試しにと思って注文した。

店員さんが持ってきた牡蠣ラーメンは大きな牡蠣が三つも入っている。
お味はどうか。
牡蠣の味なのか、それとも貝出汁なのか判らないが美味しくいただける。
麺はカニ味噌のときと同じ。
ネギとモヤシが入っていてさっぱり味。
味がさっぱりだが、コクがある。
カニ味噌より断然こちらをお勧めする。
ヒラメかどうか判らないようなえんがわも取った。

サクサクでしっとり感がないえんがわはコリコリ感もない。
一体、何の魚なのだろうか。

あじのにぎりも手にとった。
イカ類はワサビが利いているが、その他はそれほどでも。
廻ってくるワサビをちょびっと盛る。
これで美味さが引き立つ。
「はま寿司」が気にいったのはフライものである。
今回も手にした鶏のからあげ。

大きいからあげがこつんと載っている軍艦巻き。
これが大好きなのだ。
揚げものついでにもう一品はカキフライだ。

ラーメン同様にどちらも大きい牡蠣は一口ではみ出す。
二口でいただく。
満足いっぱいになってもう手が出ない。
支払いは二人で税込1839円。
次回に入店するころは消費税が8%になっているだろう。
(H26. 3. 7 SB932SH撮影)
今回も新聞チラシに誘惑されて出かけた。
くるくる回転寿司屋が提供するラーメンだ。
前回はエビ味噌ラーメンを食べた。
ラーメン丼ではなく椀に盛ったエビ味噌ラーメン。
とにかく味が濃いかったラーメン。
エビ味噌が濃くすぎるのだ。
麺は細麺の柔らか麺だった。
今回のちらしはエビ味噌ではなくカキである。
どんな味なのか舌で感じてみたかった。
クラブを終えたかーさん迎えついでに寄った時間は丁度昼どき。
入店とともに器械で操作。
人数、席を選んで案内を待つ。
しばらくすればどうぞと席番号を記した札を手渡される。
カウンター、テーブル席はほとんど満席状態。
美味しさの評判が高いのだろう。
子供連れは見られない。
時間に余裕がある家族連れがほとんどだ。
「はま寿司」は平日が一皿90円。税抜き価格である。
この年の3月末までは税込みで94円。
4月ともなればおそらく97円になるであろう。
テレビで盛んにコマーシャルしていたかっぱ寿司は「へい へい へいじつ きゅうじゅうにえん」だった。
が、昨年末の12月からは105円になった。
それから聞こえなくなったコマーシャルソングは耳に焼きついたままだ。
回転寿司チェーン店はどことも競争。
くら寿司はラーメンに加えてイベリコ豚丼まで売るようになった。
過当競争の回転寿司はどこまで行くのか、である。
消費者はお目当てで行くのもあるが、やはり寿司ネタだろう。
かれこれ40年前のことだ。
大阪千日前の水掛不動尊辺りにあったにぎり寿司屋さんに度々出かけていた。
とてつもなく大きなネタだった。
マグロ、ハマチはぶつ切りのネタ。
隣のおじさんが食べたとたんに、ぶっと飛びだした。
ひと口では食べることができないぶつ切りはとんでもない大きさだった。
アナゴなんてものはまるまる一尾だった。
何口で食べたか・・・。
ウナギはさすがに一尾でなく、半分切り。
厚みがあったウナギも一口で食べきらない。
先代を継いだ若い寿司職人が握っていた。
そんなネタを出していた寿司を20皿も食べていた。
若いころのことだ。
今でも寿司店があるのかどうか知らない。
可愛かった嫁さんの顔は覚えているが、店名が思い出せない。
そんなことを思い出しながら回転レーンを流れるにぎり寿司を見ていた「はま寿司」は3月6日から19日までは春の味わいの「春ねた祭」。
漬けほたるいか、特製漬けまだい、あおりいか塩レモン、生しらす、創作かにちらしがお勧めだそうだ。
流れるレーンにそのうちのひとつが登場した。

あおりいか塩レモンだ。
レモンは食べないからそっと横に置く。
もちろん種も要らない。
甘タレ造り醤油でいただく。
まぁまぁ美味いあおりいか。
我が家はイカ派。
好みの寿司ネタであるから、漬けほたるいかも手を伸ばす。

ホタルイカの漬けは美味いのに決まっている。
漁師が船漁している最中に獲ったイカを器にぶっこんで醤油をたらたら。
数時間漬けこんでおけばイカが吐き出す墨と混ざって味が濃くなる。
そういう仕方で造りこんだのかどうか判らないが美味いのだ。
次もまた、イカであるが、レーンに廻ってこない。
メニュー画面を押して頼んだ姿やりいか。
いくら待てどもやってこない注文の品。
メニューを押して頼んだ品は到着間近になれば、チャイム音が鳴りだすのだが・・・。

鳴らないが廻ってきた姿やりいかに思わず手をだした。
食べていたら音が鳴った。
2皿も食べれば飽きてしまう。
そうそう寿司は食べてられない。
今日の目当ては牡蠣ラーメンである。
新聞ちらしに載っていた割引券は牡蠣ラーメンの税込み294円を特別値段に・・・。
ものは試しにと思って注文した。

店員さんが持ってきた牡蠣ラーメンは大きな牡蠣が三つも入っている。
お味はどうか。
牡蠣の味なのか、それとも貝出汁なのか判らないが美味しくいただける。
麺はカニ味噌のときと同じ。
ネギとモヤシが入っていてさっぱり味。
味がさっぱりだが、コクがある。
カニ味噌より断然こちらをお勧めする。
ヒラメかどうか判らないようなえんがわも取った。

サクサクでしっとり感がないえんがわはコリコリ感もない。
一体、何の魚なのだろうか。

あじのにぎりも手にとった。
イカ類はワサビが利いているが、その他はそれほどでも。
廻ってくるワサビをちょびっと盛る。
これで美味さが引き立つ。
「はま寿司」が気にいったのはフライものである。
今回も手にした鶏のからあげ。

大きいからあげがこつんと載っている軍艦巻き。
これが大好きなのだ。
揚げものついでにもう一品はカキフライだ。

ラーメン同様にどちらも大きい牡蠣は一口ではみ出す。
二口でいただく。
満足いっぱいになってもう手が出ない。
支払いは二人で税込1839円。
次回に入店するころは消費税が8%になっているだろう。
(H26. 3. 7 SB932SH撮影)