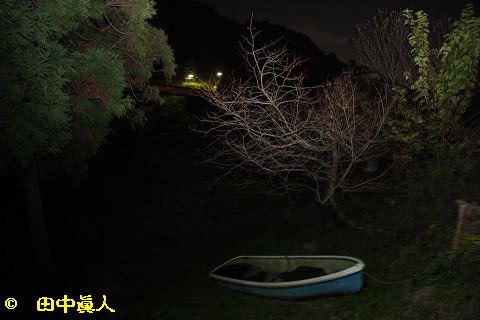砂撒き風習があるのかどうか確かめるには正月三が日に訪れて調査した方がいい。
それ以前であれば撒いていたとしても絶対的に砂跡は雨に流れて消えているはずだ。
大和郡山市内の調査はそうしてきた。
正月三が日は無理だとしても、訪れるには一月以内。
少なくともそういたいと思ってはいるものの、遠隔地であれば度々出かけるわけにはいかないから、時期を逃してしまう。
ただ、どのような場所地にあるのかだけでも見ておく方が良い。
そう思って出かけた京都府の南部地域。
まずは木津川市の加茂町銭司(ぜず)。
していると仮定しての場所は春日神社である。
この日も同行調査する写真家のKさんとともに行動する。
カーナビゲーションにセットした銭司。
県道163号線に架かる信号を北にあがる。
地図を見れば参道筋の右に小字神田。
さらにあがった四つ辻の左に小字城ノ垣内がある。
前方の具合がわからないから辻にある民家の婦人に道を尋ねた。
結果は上流である。
その筋に沿って上流の谷沿いは小字金谷。
もっと奥の最上流手前に車を停めてその奥にある建物を目指していたときだ。
左前方にある樹木がわっさわっさと揺れる。
得体のしれない獣の声も聞こえる。
どうやら野猿のようだ。
さて、その奥の建物は・・。
石の鳥居が見られるから神社であろう。
そう思って足を運ぶ。

鳥居を潜って石段を登れば朱塗りの三社が並ぶところに出た。
中央はお稲荷さんが祀られているから稲荷社に違いないが、左右に建つ社は何であろうか。
社札のようなものがあり「妙法二神」と書かれた金色、赤色二色の幣がある。
右の社の幣札は判読し難いが「八大龍王」。
帰宅して調べた結果は「山の神」さん。
中央の社は「森飛騨大明神」を祀っているそうだ。

その台場にあった赤い実。
トウガラシのようである。
もしかとして、初成りのお供え。
そう思って撮っておいた。
そこより下った処にも社がある。
これも帰宅してわかった銭司(ぜず)妙見宮。
詳しくは日蓮宗妙見山本照寺のHPを参照していただきたい。

その銭司妙見宮社の脇においてあった竹製の札がある。
たぶんに、お百度参りのときの数取りの札であろう。

そこから一段下がった処に木製の「白馬」があった。
愛くるしい表情で語りかけてくれるような白馬妙見さんにお仕えする馬の姿の神である。
ここでは「馬神様」と呼ばれている神馬である。
下っていけば人影が動いた。
庫裏と思われる建物がある。
お声をかけさせてもらったら若い女性が出てこられた。
ふとしたことから妙見宮に参らせてもらったことを伝えて興味をもったそれぞれを教えてもらった。
女性は僧侶の妹さん。
大正11年に大阪の能勢町にある妙見さんより勧請、祀る銭司の妙見山本照寺。
石の鳥居はかつての妙見宮の名残であるらしい。
歴史的な縁起については日蓮宗妙見山本照寺のHPを参照していただきたい。
女性に尋ねた竹の箆棒。
それはお百度参りに使途する数取り道具。
願掛けの人が竹の箆棒を作ってもってくる。
その箆を手にしてお堂の周りを願掛けしながらお参りをするということだった。
神馬は妙見さんの眷属。
他所では亀の姿もあるらしいが、本照寺では白馬であると話された。
また、水行の場にある仏像は妙見さん。
剣をもっているから妙見さんと話してくれた。
ところで、春日神社の所在地は、と尋ねたら、ここよりすぐ近く。
木の根っこが見られる山林道を下れば神社が見えてきますと云われて道を下る。
その場に建っていた春日神社にようやくご対面できる。

社殿は近年にゾーク(造営)されたかのように美しい姿で建之されていた。
参拝するとともに境内の様相を見て回る。
愕然としたのはこれだ。

石の灯籠が無残な状態になっている。
元々の姿を見ていないので、なんともいえないが、なんとなく人為的に倒されたような感がする。
向こうに並ぶ3基の灯籠が同じ方向に倒れている。
地震があったとは思えないような倒れ方である。
人影はまったく見られないが、社務所か参籠所と思える建物に貼ってあった情報に目がとまる。
その情報は「平成29年勧請縄奉仕者名」であった。
東頭(東座であろう)に4人の名、西頭(西座であろう)は7人である。
勧請縄を結って掛ける行事の役目をもつ東、西の頭が11人。
その年度の当番の人たちだと思うが、いつ掛けているのだろうか。
来た道とは別の道を下ることにした。神社から下りてすぐ近く。
割り合い広い処にでる。
そこが参道であろうか、地蔵尊を納めた祠があった。
供えて間もないと思われるお花を立てていた。
参拝者が供えた花であろう。

鬱蒼とした森林に囲まれる社叢地に昇ってきた朝の光が射し込む。
神々しい光に照らし出された地蔵さんにも手を合わせて四つ辻まで下った。
ここでまたもやお聞きする春日神社の勧請縄掛け。
お話してくださったのは男性。
登り口に尋ねた婦人の旦那さんのようだ。
男性がいうには行事日は1月3日。
当番の人たち(座中)は朝に集まってきて、午前中いっぱいは縄結い。
午後の時間帯に再び集まって縄を掛けているそうだ。
話しているそのときだ。
大きな図体でのっし、のっしと四つ足歩行でもない、前足はまるで手のよう・・。
お尻の赤い色がはっきりとわかる野生の猿だった。
ここらで栽培している野菜は猿のエサのようになってしまったという。
林のなかで動いていた獣は間違いもなく猿である。
こんな大きな野生の猿が銭司(ぜず)に住み着いてしまって・・とぼやいていた。
その辻から東に行けば左手にお寺が見える。
福田寺だと教えてくれたのは散歩する男性。
小字宮ノ前か、右手の蔵ノ垣内にお住まいであろう。

男性が云うには、その福田寺の際を登っていけば春日神社に着くらしい。
ここは小字馬場道の名がある。
馬に乗った人たちが神社と往来した道であろう。
その付近にあった彫りの深い石仏があった。

地蔵菩薩であろう。
それはともかく福田寺(ふくでんじ)の普段は無住時であるが、年に何度かは相楽郡笠置町の笠置寺の僧侶がくるという。
福田寺は真言宗智山派。
笠置寺も同宗派である。
笠置寺の僧侶とは一度お会いしている。
訪れたのは平成19年11月24日。
山寺の錦織りなす景観を求めて来訪した。
そのときに出会った住職の詞は今も私のHPに書き残している。
これを機会にこのブログに転載しておく。
このとき書いたタイトルは「古代色」。
コメントは「某山寺の和尚さんが形よりも色を表現したいと話された古代の色」。
某山寺というのが真言宗智山派笠置寺である。
「幽玄を感じさせる霧の世界に昔より伝えられる日本古来の色の呼び名に憧れる和尚。古来色の呼び名で景観を表現するのは難しいが、私もその視点を大切したい。心の中でつぶやいてシャッター押すように心がけたいものだ。」であるが、あらためて読んで見れば恥ずかしいものだ。
未だに住職が思う境地には達していない。
もっと精進しなければと、思った。
ちなみに散歩していた男性の話しによれば、12月の大晦日の日に砂撒きをしていたそうだ。
今は宮守さんの都合、或は考え方によって砂撒きは「道」にすることもあるらしい。
参考までにネットにあった3例を挙げておく。
一つはこちら。
もう一つは秋祭りの所作が大柳生のハナガイを装着して田の草取り所作とそっくりな様相を伝えていたので大いに参照したい。
もう一つは京田辺市の宮津の砂撒きに続いてアップされた銭司の砂撒きである。
(H28.12.18 EOS40D撮影)
それ以前であれば撒いていたとしても絶対的に砂跡は雨に流れて消えているはずだ。
大和郡山市内の調査はそうしてきた。
正月三が日は無理だとしても、訪れるには一月以内。
少なくともそういたいと思ってはいるものの、遠隔地であれば度々出かけるわけにはいかないから、時期を逃してしまう。
ただ、どのような場所地にあるのかだけでも見ておく方が良い。
そう思って出かけた京都府の南部地域。
まずは木津川市の加茂町銭司(ぜず)。
していると仮定しての場所は春日神社である。
この日も同行調査する写真家のKさんとともに行動する。
カーナビゲーションにセットした銭司。
県道163号線に架かる信号を北にあがる。
地図を見れば参道筋の右に小字神田。
さらにあがった四つ辻の左に小字城ノ垣内がある。
前方の具合がわからないから辻にある民家の婦人に道を尋ねた。
結果は上流である。
その筋に沿って上流の谷沿いは小字金谷。
もっと奥の最上流手前に車を停めてその奥にある建物を目指していたときだ。
左前方にある樹木がわっさわっさと揺れる。
得体のしれない獣の声も聞こえる。
どうやら野猿のようだ。
さて、その奥の建物は・・。
石の鳥居が見られるから神社であろう。
そう思って足を運ぶ。

鳥居を潜って石段を登れば朱塗りの三社が並ぶところに出た。
中央はお稲荷さんが祀られているから稲荷社に違いないが、左右に建つ社は何であろうか。
社札のようなものがあり「妙法二神」と書かれた金色、赤色二色の幣がある。
右の社の幣札は判読し難いが「八大龍王」。
帰宅して調べた結果は「山の神」さん。
中央の社は「森飛騨大明神」を祀っているそうだ。

その台場にあった赤い実。
トウガラシのようである。
もしかとして、初成りのお供え。
そう思って撮っておいた。
そこより下った処にも社がある。
これも帰宅してわかった銭司(ぜず)妙見宮。
詳しくは日蓮宗妙見山本照寺のHPを参照していただきたい。

その銭司妙見宮社の脇においてあった竹製の札がある。
たぶんに、お百度参りのときの数取りの札であろう。

そこから一段下がった処に木製の「白馬」があった。
愛くるしい表情で語りかけてくれるような白馬妙見さんにお仕えする馬の姿の神である。
ここでは「馬神様」と呼ばれている神馬である。
下っていけば人影が動いた。
庫裏と思われる建物がある。
お声をかけさせてもらったら若い女性が出てこられた。
ふとしたことから妙見宮に参らせてもらったことを伝えて興味をもったそれぞれを教えてもらった。
女性は僧侶の妹さん。
大正11年に大阪の能勢町にある妙見さんより勧請、祀る銭司の妙見山本照寺。
石の鳥居はかつての妙見宮の名残であるらしい。
歴史的な縁起については日蓮宗妙見山本照寺のHPを参照していただきたい。
女性に尋ねた竹の箆棒。
それはお百度参りに使途する数取り道具。
願掛けの人が竹の箆棒を作ってもってくる。
その箆を手にしてお堂の周りを願掛けしながらお参りをするということだった。
神馬は妙見さんの眷属。
他所では亀の姿もあるらしいが、本照寺では白馬であると話された。
また、水行の場にある仏像は妙見さん。
剣をもっているから妙見さんと話してくれた。
ところで、春日神社の所在地は、と尋ねたら、ここよりすぐ近く。
木の根っこが見られる山林道を下れば神社が見えてきますと云われて道を下る。
その場に建っていた春日神社にようやくご対面できる。

社殿は近年にゾーク(造営)されたかのように美しい姿で建之されていた。
参拝するとともに境内の様相を見て回る。
愕然としたのはこれだ。

石の灯籠が無残な状態になっている。
元々の姿を見ていないので、なんともいえないが、なんとなく人為的に倒されたような感がする。
向こうに並ぶ3基の灯籠が同じ方向に倒れている。
地震があったとは思えないような倒れ方である。
人影はまったく見られないが、社務所か参籠所と思える建物に貼ってあった情報に目がとまる。
その情報は「平成29年勧請縄奉仕者名」であった。
東頭(東座であろう)に4人の名、西頭(西座であろう)は7人である。
勧請縄を結って掛ける行事の役目をもつ東、西の頭が11人。
その年度の当番の人たちだと思うが、いつ掛けているのだろうか。
来た道とは別の道を下ることにした。神社から下りてすぐ近く。
割り合い広い処にでる。
そこが参道であろうか、地蔵尊を納めた祠があった。
供えて間もないと思われるお花を立てていた。
参拝者が供えた花であろう。

鬱蒼とした森林に囲まれる社叢地に昇ってきた朝の光が射し込む。
神々しい光に照らし出された地蔵さんにも手を合わせて四つ辻まで下った。
ここでまたもやお聞きする春日神社の勧請縄掛け。
お話してくださったのは男性。
登り口に尋ねた婦人の旦那さんのようだ。
男性がいうには行事日は1月3日。
当番の人たち(座中)は朝に集まってきて、午前中いっぱいは縄結い。
午後の時間帯に再び集まって縄を掛けているそうだ。
話しているそのときだ。
大きな図体でのっし、のっしと四つ足歩行でもない、前足はまるで手のよう・・。
お尻の赤い色がはっきりとわかる野生の猿だった。
ここらで栽培している野菜は猿のエサのようになってしまったという。
林のなかで動いていた獣は間違いもなく猿である。
こんな大きな野生の猿が銭司(ぜず)に住み着いてしまって・・とぼやいていた。
その辻から東に行けば左手にお寺が見える。
福田寺だと教えてくれたのは散歩する男性。
小字宮ノ前か、右手の蔵ノ垣内にお住まいであろう。

男性が云うには、その福田寺の際を登っていけば春日神社に着くらしい。
ここは小字馬場道の名がある。
馬に乗った人たちが神社と往来した道であろう。
その付近にあった彫りの深い石仏があった。

地蔵菩薩であろう。
それはともかく福田寺(ふくでんじ)の普段は無住時であるが、年に何度かは相楽郡笠置町の笠置寺の僧侶がくるという。
福田寺は真言宗智山派。
笠置寺も同宗派である。
笠置寺の僧侶とは一度お会いしている。
訪れたのは平成19年11月24日。
山寺の錦織りなす景観を求めて来訪した。
そのときに出会った住職の詞は今も私のHPに書き残している。
これを機会にこのブログに転載しておく。
このとき書いたタイトルは「古代色」。
コメントは「某山寺の和尚さんが形よりも色を表現したいと話された古代の色」。
某山寺というのが真言宗智山派笠置寺である。
「幽玄を感じさせる霧の世界に昔より伝えられる日本古来の色の呼び名に憧れる和尚。古来色の呼び名で景観を表現するのは難しいが、私もその視点を大切したい。心の中でつぶやいてシャッター押すように心がけたいものだ。」であるが、あらためて読んで見れば恥ずかしいものだ。
未だに住職が思う境地には達していない。
もっと精進しなければと、思った。
ちなみに散歩していた男性の話しによれば、12月の大晦日の日に砂撒きをしていたそうだ。
今は宮守さんの都合、或は考え方によって砂撒きは「道」にすることもあるらしい。
参考までにネットにあった3例を挙げておく。
一つはこちら。
もう一つは秋祭りの所作が大柳生のハナガイを装着して田の草取り所作とそっくりな様相を伝えていたので大いに参照したい。
もう一つは京田辺市の宮津の砂撒きに続いてアップされた銭司の砂撒きである。
(H28.12.18 EOS40D撮影)