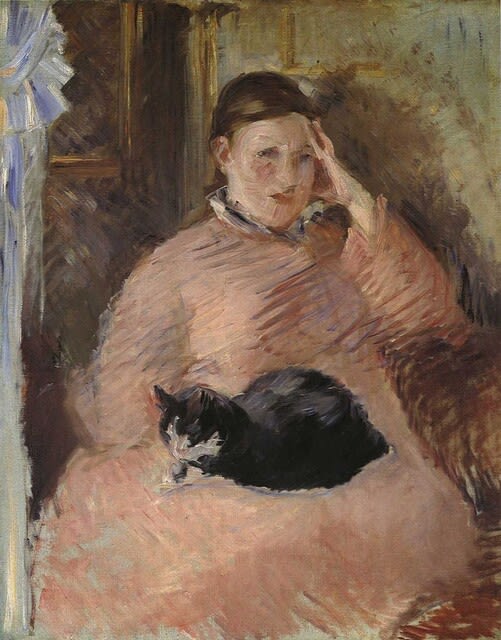エンドウ豆について検索していたら、ウクライナの「豆太郎」に出会いました

「桃太郎」に似たお話で、エンドウ豆から(エンドウ豆を食べたお母さんから)生まれたコティホローシュコ(豆太郎)が竜退治をします。
日本語Wikiにも記事があります:
コティホローシュコ
ウクライナの切手

若いライオン2頭がウクライナからベルギーの保護施設に引き取られます。

何と個人が不法に飼育していたため、管轄機関に押収されました。しかも飼育環境が悪く、栄養失調だそうです。
幾つかの幸運が重なって救出される動物もいますが、砲撃で死んだり飢え死にする動物たちもいると思います

ウクライナのオーケストラがロシア軍の砲撃が続くキエフで自主コンサート

プーチンとロシア軍によるクリミア半島併合と今回のウクライナ侵攻は、まさに第二次世界大戦におけるナチス・ドイツの侵略戦争に匹敵するものです。
しかし、ロシア連邦の国民は56%が現在の戦争支持だと報道されています。
ロシア正教の総主教も「西側の悪魔のような流言飛語」と発言しています。
ロシア連邦は情報管制の中にあり、プーチンを肯定する聖職者が総主教になっているはずですが、それにしても・・・
・・・と、30年以上前の、すっかり忘れていた東欧開放・解放当時のことを思い出しました。
当時、改革・民主化路線を邁進する
ゴルバチョフは、西側では非常に人気が高く、どの国でも歓迎されていましたが、当のソ連では全く人気がありませんでした。当時ソ連に批判的な東欧諸国でも「ゴルバチョフは我々を西側に売り渡したのだ」と言う人々がいて、大きな衝撃を受けたものです。
クリミア半島併合もウクライナ侵攻も「失地回復」と歓迎する社会層が存在するのでしょう。
中央アジアもそうですが、東欧・バルカン半島も古来、様々な民族が交差し衝突するところで、つまり難しい地帯なのです。
それで、もうひとつ思い出したのは、当時読んで深い感銘を受けた本のことです。
著者はドイツのジャーナリストで、タイトルは「ガリツィアへの旅」
サブタイトルは「古きヨーロッパの辺境風景」
この本には
ガリツィアをはじめ、ボルヒニア、ポドリア、
ブコヴィナという、いかにも辺境っぽい地名が出てきます。
古くからラテン民族、ゲルマン民族、スラブ民族の出会うところであり、
アシュケナジム・ユダヤ人の
シュテットルが多く、ウィーンで活躍したユダヤ人の学者や芸術家も多くはシュテットル出身者でした。
そうしたユダヤ人の伝統文化はナチス・ドイツによって抹殺されました。

表紙の写真はユダヤ人墓地に放牧されている(?)ヤギですね。
この本を改めて読んでみようと思います。ですから、多分、続く・・・

恒例、乞無期待

















 でも乞無期待
でも乞無期待













 世界中でブーイングしましょう
世界中でブーイングしましょう













 どっちでもいいけど
どっちでもいいけど