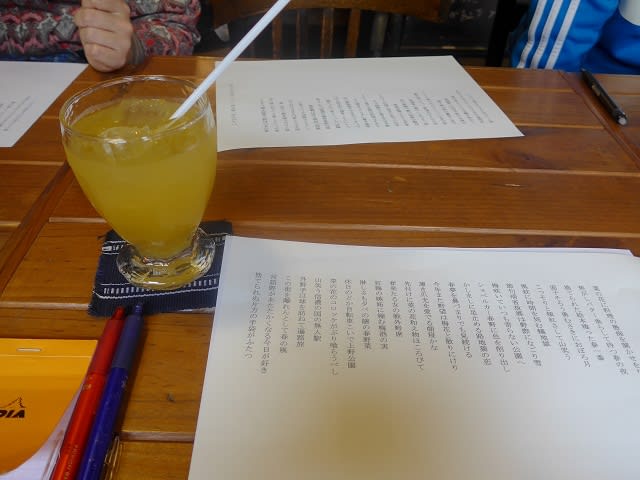7時半、起床。
パン、夕べの残りの唐揚げ、紅茶の朝食。

11時に家を出て、神楽坂へ。今日は12時から「SKIPA」で句会が行われる。
今日の参加者は8名、紀本さん、蚕豆さん、恵美子さん、明子さん、東子(はるこ)さん、私(たかじ)、前回から参加(ただし前回は見学のみ)の青天井さん、そして初参加の格調低郎さん、である。
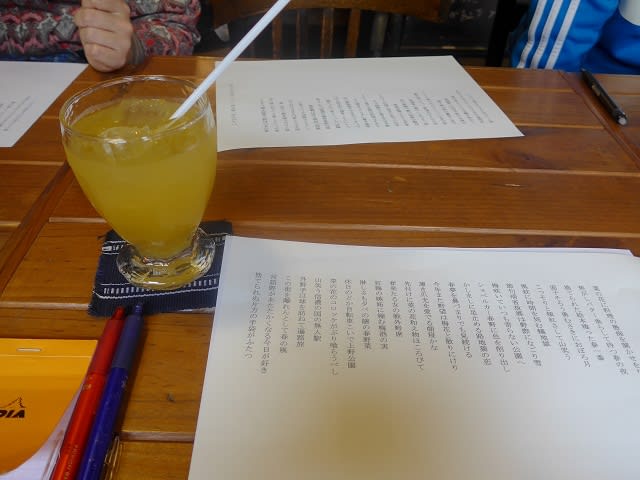
8名×3句(自由題2句、兼題「野」1句)の24句が書かれた紙が配られ、紀本さんが各作品を読み上げてから、選考に入る。「天」は5点、「地」は3点、「人」は1点で、各自が3句を選ぶ。
私は次の3句を選んだ。
天 薄き爪光を愛でる朝寝かな
春眠暁を覚えず。目が覚めてもすぐには起床せず、布団の中でうとうとする気持ちよさはみんな知っているが、この作品ではそこに艶っぽさが加味されている。平安朝の女官のイメージ。
地 春来たる女の戦外野席
これも女性が詠んだ、あるいは女性を詠んだ作品。春は高校野球のシーズンであるが、これはもちろん野球の試合を詠んだものではない。「女の戦」とは春のファッションをめぐる競争であろうか、あるいは恋の戦いであろうか。しかし、読み手はそうした戦いの土俵の外(外野席)に身を置いて、「私には関係ありませんけどね」と達観しつつ、ちょっといじけてみせている。
人 言語野があたたかくなる今日が好き
兼題「野」を「言語野」で使っているところが意表を突くが、言語野があたたかくなる(活性化する)と言葉があふれ出てくるわけで、それがおしゃべりであれ、句作であれ、乗っている感じ、ウキウキした感じで、そういう「今日が好き」と素直に言い放ったところが好感がもてる。ありのままの自分を見せた句である。
さて、全員の選考が終わったところで、各自が自分の選んだ3句を申告。集計の結果、入選は以下の13句(得点順)。選んだ人が選んだ理由を述べてから、作者が明らかにされた。
13点(特選) ショベルカー春野に色を削り出し 明子
13点(特選) この街を離れんとして春の風 たかじ
10点 薄き爪光を愛でる朝寝かな 明子
7点 春来たる女の戦外野席 紀本直美
6点 こっそりと頬紅さして山笑う 恵美子
6点 菜の花のコロッケがぶり喰らうべし 蚕豆
5点 捨てられた絵本捲った春一番 恵美子
4点 淋しさも夕べの膳の春野菜 たかじ
3点 菜の花に料理の愚痴を聞かせをり 東子
2点 言語野があたたかくなる今日が好き 恵美子
1点 かしましに足止める路地猫の恋 格調低郎
休日のどか自転車こいで上野公園 青天井
山笑う信濃の国の無人駅 たかじ
8名全員が一句は入選し、「坊主」の人は今日はいなかった。よかった、よかった(笑)。3句全部が入選したのは恵美子さんと私で、これはけっこう大変なことなのである。自画自賛、たかじさん(笑)。
自分の句に何点入るかだけでなく、誰が自分の句を選んでくれたのかも関心事である。そこから各自の好みがわかるからだ。たとえば、私の句を選んでくれたのは、「この街を離れんとして春の風」が明子さん(天)、青天井さん(天)、紀本直美さん(地)、「淋しさも夕べの膳の春野菜」が明子さん(地)、蚕豆さん(人)、「山笑う信濃の国の無人駅」が格調低郎さん(人)である。明子さんは私の3句から2句を選んでくれている。選考の段階では作者は伏せられているので、私の作風が明子さん好みであるということがわかる。では、明子さん自身の作風と私の作風が似ているかと言えば、そうではない。明子さんの句はファンタジックな乙女の句が多い。たぶん明子さんが私の句を選ぶのは、自分の作風にはない要素に引かれてだろうと思う。それは何なのか?う~ん、自分の口からは言えません(笑)。
通常の句会では、選に漏れた句は選評の対象にはならない。「そっとしておこうね」ということかもしれないし、たんに時間がないからかもしれない。しかし、選に漏れた=駄作ということではないと思う。実際、私が3句に絞り込んでいく過程で落とした句の中に捨てがたい作品がいくつかあった。誰の句かはわからないが、挙げておくと、「焦がしバター垂らして待つ春の夜」、「春夢を鼻づまりでも見続ける」、「捨てられぬ片方の手袋がふたつ」の3作品である。それぞれに味わい深い作品だったので、私が落としても誰かが入れるだろうと思っていた。蓋を開けてみると選外だったので、ああ、私が入れておくのだったと悔やんだが、後の祭りである。選ぶことは、同時に、捨てることでもある。女は自分が捨てた男のことは忘れ去るが、男は自分が捨てた女の幸せを願うものだと聞いたことがある(逆だったかな?)。経験が乏しいので私にはよくわからないが、選句にかんしてはたしかにそういうことがいえるかもしれないと思う。

上位の入選作について私なりの寸評を書き留めておく。
「ショベルカー春野に色を削り出し 明子」
色彩豊かな句である。「削り出し」という表現はよくひねり出したと思う。色鉛筆を削っているような感じがある。「ショベルカー」という機械と「春野」という自然の対比も効果的である。私がこの句を選ばなかったのは、絵画的には美しいが、音楽的にはノイズ(ショベルカーの「ガガガ」という音)が耳障りに感じられたからである。春野に放置された(動かない)ショベルカーであったらよかったのにと思う。
「この街を離れんとして春の風 たかじ」
私の句である。今回の句会のために作った句ではなく、一年前に作った句である。大学の近所に「maruharu」(まるはる)という美味しいサンドウィッチの店があった。はるさんという30代の独身女性がやっていたが、訳あって店をたたみ、郷里に帰ることになった。 最後の営業日、常連客が集まって、はるさんとの別れを惜しんだ。そのとき詠んだ挨拶句である。言うまでもなく「春の風」の「春」は「はるさん」にかけてある。そういう背景を知らなくても、出逢いと別れの季節の句として鑑賞に耐える作品ではないかと思い、今回投句したしだいである。「はるさん」はいまどうしているだろう。
「薄き爪光を愛でる朝寝かな 明子」
私はこの句に「天」を付けた。理由はすでに述べたので繰り返さないが、明子さんは「ショベルカー」の句も特選となり、今回絶好調である。実生活でも新天地(職場)に飛び出していこうとしているのだが、それが作品にのびやかさを与えているのではないだろうか。
「春来たる女の戦外野席 紀本直美」
私はこの句に「地」を付けた。理由は前述。
「こっそりと頬紅さして山笑う 恵美子」
「山笑う」という季語は人気があるそうだ(紀本さん談)。私も今回「山笑う信濃の国の無人駅」を投句したので、最初に作品リストを見たときに、「ああ、他にも使っている人がいるな」と思って、ほくそ笑んだ。「山笑う」は大きな動きを感じさせる言葉なので、それとの対比で、静かな言葉を入れたくなる。私の句では「無人駅」がそれに相当し、恵美子さんの句では「こっそりと」がそれに相当する。句作の思考まで同じで私はもう一度ほくそ笑んだ。
「菜の花のコロッケがぶり喰らうべし 蚕豆」
「菜の花のコロッケ」というものがどういうものか知らなかったが、作者によると、中野の商店街で売っているとのことだった。どのようなコロッケであれ、買ってその場でかぶりつくのがコロッケの一番美味しい食べ方であるが、たかがコロッケに「喰らうべし」という古風で大仰な表現を用いたところが、この句の面白さである。
選評が終わったところで、食事である。定食(メインは鶏肉団子のカレースープ煮)を注文。

食後にアイスチャイ。

次回の句会は5月17日。兼題は「日」(明子さんの出題)。
最後まで残っていた面々。
*恵美子さんが自身のブログ「つぼみな日々」で今日の句会の感想を書いています。

紀本さんと明子さんは相談事があるようだったので、早稲田の「カフェゴト―」にお誘いする。

3人で、洋梨のフラン、バナナタルト、クラシックアップルパイを頼んで、3等分してもらって、シェアして食べる。2種類のケーキのシェア(ハーフ&ハーフ)はよくお願いするが、3種類のシェアは初めてである。わがままな注文に快く応じていただけて感謝。・・・でも、どこまで可能なのだろう(笑)。

5時、帰宅。
夕食は回鍋肉。


デザートは「梅花亭」で買ってきた桜餅(妻は草餅)とみたらし団子。

深夜、ランニング&ウォーキング。風呂を浴びてから、『流星ワゴン』第9話(録画)を観る。主人公の一雄(西島秀俊)は「いい夫」であり「いい父親」だが、それはただたんに自分の大嫌いな父親(香川照之)のようにはなりたっくなくて、つまりは自分自身のためにそうしているだけだと妻(井川遥)に言われてしまう。ずいぶんの言いようだが、これは図星なのである。多くの場合、人は自分の親の真似をしようとするか、反対をやろうとするか、どちらかである。他人の親の真似をするといこともあるが、それは自分の親の真似をするのが嫌だからで、反対をやろうとすることの一種である。