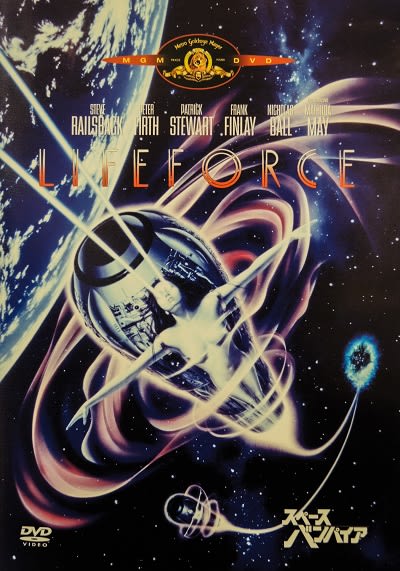東京都庭園美術館に足を運び、クリスチャン・ボルタンスキーの個展「アニミタス-さざめく亡霊たち」を観る。
まずは、本展に際して行われたボルタンスキーへの20分ほどのインタビュー映像を観る。かれは、人をカテゴリーに押し込めることを激しく拒絶する。そのたとえが、「ユダヤ人を皆殺しにせよ」との命令の非論理・非倫理は、「床屋を皆殺しにせよ」との命令と同じ水準であるとする。そして、その対極にあるものとしてかれが表現手段としたものが、それぞれが異なる特別な存在たる者たちの声なき声であり、音声としての声であり、生命のあかしであり、生命の痕跡なのだった。

※映像ルームでの撮影は許可されている
本展では、古い洋館の部屋ごとにおいて、その囁きが提示されている。
最初の「さざめく亡霊たち」では、部屋の四方から人びとの囁きや呟きが聞えてくる。それは日本語ではあるが、聴きとれたり、とれなかったり。我々はもとより、個々を個々として認識する以上のことはできない。まとめてカテゴライズする行為は本質的に暴力を孕んでいるということだ。
次の「影の劇場」では、コミカルなモビールたちの影絵が揺らめき、それらは明らかに死を思わせるものであり、しかし同時にノスタルジックでもある。
書庫での「心臓音」では、人びとの心臓音が増幅され流されている(豊島にアーカイヴとして保存されている)。「MONUMENTA 2010 / Personnes」でも使われた手法だ。その場に身を置くことは、個への一体化を要請されることにもなる。すなわち、かけがえのないもの・取返しのつかないもの・一度限りのものとしての個の生命を、否が応でも実感させられてしまう。
新館の大きな部屋に入ると、そこには、人びとの眼がプリントされた布が数多く吊るされており、「眼差し」と題されている。それらの間をかきわけて歩いてゆくと、「帰郷」という物がある。ナチスの強制収容所で没収された大量の古着の山がイメージされ、それを、金色のシートが覆っている。やはり「MONUMENTA 2010 / Personnes」では古着類が積み上げられ、クレーンが掴み上げては上から放り落とすことを続けていた。それが痛いほど直接的な暴力を示したものであるとすれば、本展はシートの向こうに人の痕跡があることを間接的に想像させられるものだ。いずれも息が詰まってしまうほどの迫真性をもっている。
そして、上映室の真ん中にスクリーンが置かれ、両側から風鈴のプロジェクト風景が上映されている。片方はチリ・アタカマ砂漠におけるものであり、多数の棒の上から風鈴と白い短冊が吊るされ、風に揺れて音を立てている。もう片方は豊島の森におけるものであり、木からやはり風鈴と透明な短冊が吊るされている。短冊には名前や何かが記されている。それらは<無数>であり、かつ<個々>であるものとの共振であるように感じられた。
囁きや存在の予感とともにふるえさせられる、素晴らしい展示だった。美術館の外に出ると、上映室に敷き詰められた稲わらが1本、靴にへばりついていた。世界がシームレスにつながっているように感じさせられた。

●参照
クリスチャン・ボルタンスキー「MONUMENTA 2010 / Personnes」(2010年)