古田徹也『言葉の魂の哲学』(講談社選書メチエ、2018年)。
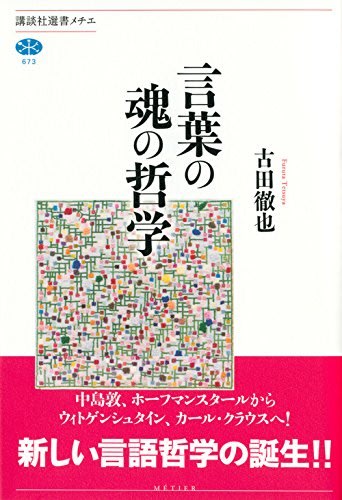
まずは、中島敦「文字禍」とホーフマンスタール「チャンドス卿の手紙」という、ゲシュタルト崩壊を扱った小説が取り上げられる。現実との距離感が揺らぐ現象として、おそらく多くの人がいちどならず感じているだろう。
しかしこのことは、言葉が伝達手段として脆弱だということを意味するものではない。著者はヴィトゲンシュタインを引用しながら、言葉の相互連関、またその連関から、類似しつつも異なる別の言葉を模索し「しっくりくる言葉を選び取る」という実践の大事さを説いている。すなわち、「一つ所に留まらず、いわば次々にアスペクトを渡っていくことではじめて、言葉の輪郭というものを捉えることができる」というわけである。
そしてカール・クラウスの言語論により、言葉とは「わたし」に他ならないことが示される。ここで重視されるのは、言葉による伝達よりも言葉の形成である。言葉とは意のままにならない。その自律性こそが、言葉を選び取るという実践を通じた創造であり、必然の発見でもある。そしてそれは責任でもあるとする。逆に言えば、常套句を安易に反復することは自分の責任を軽視しているということに他ならない。これはとても重要な指摘である。何も首相や官房長官の空疎な常套句のことを思い出すまでもない。
「根源に近づけば近づくほど、戦争から遠ざかるのだ。もしも人類が常套句をもたなければ、人類に武器は無用になるだろうに。」(クラウス)










