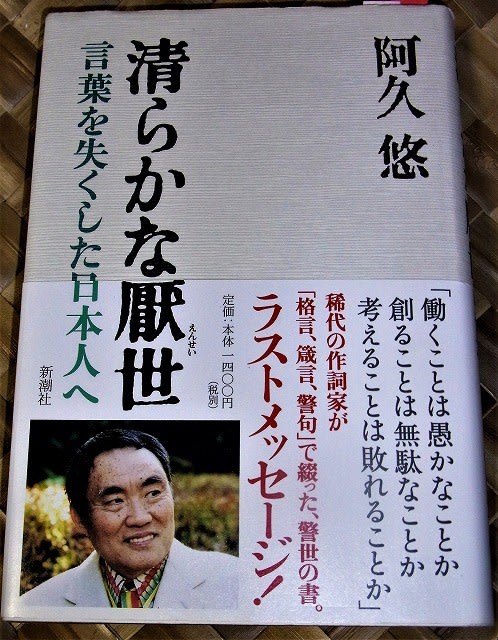わが道草山の日陰で「クリタケ」が出てきた。
そういえば2年前にクリタケの種駒をコナラに打ち込んでいたのを忘れていた。
色といい形といい、かわいい美しさがある。

ときどき、栗の樹の根元にクリタケが出てくることがあったが今年はまだない。
クリタケでもニガクリタケとそっくりの黄色をしたものもある。が、ニガクリタケは苦いので嚙んでみればすぐわかる。同じほだ木に猛毒の「ニガクリタケ」も出ていたので注意が必要だ。

さっそく、和宮様はシチューにクリタケを入れて歯ごたえの良いクリタケを楽しむ。
人口栽培で市販されるようになったが、菌床栽培は難しく原木栽培が主流だという。
晩秋の寒さにぴったりのシチューをついついおかわりして、またもや小さな胃を刺激してしまった。