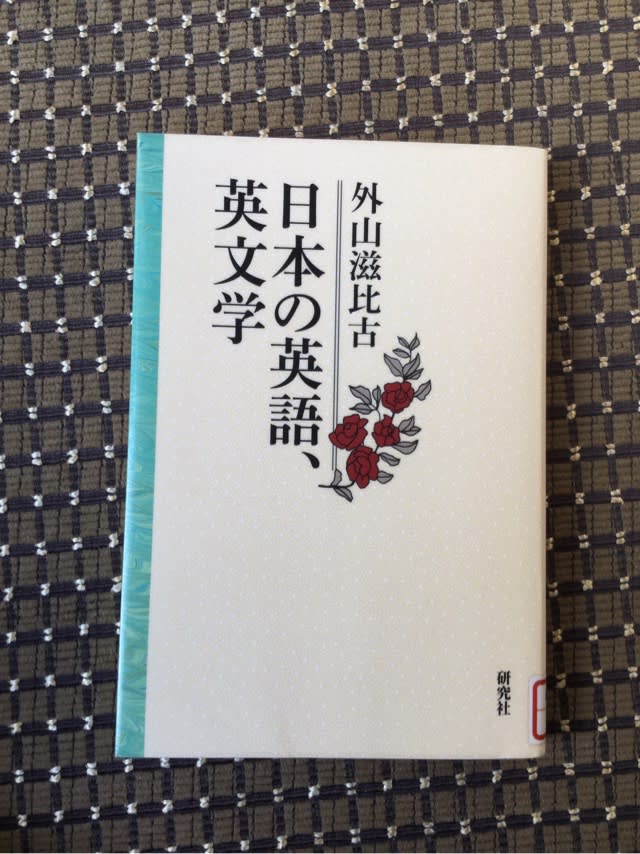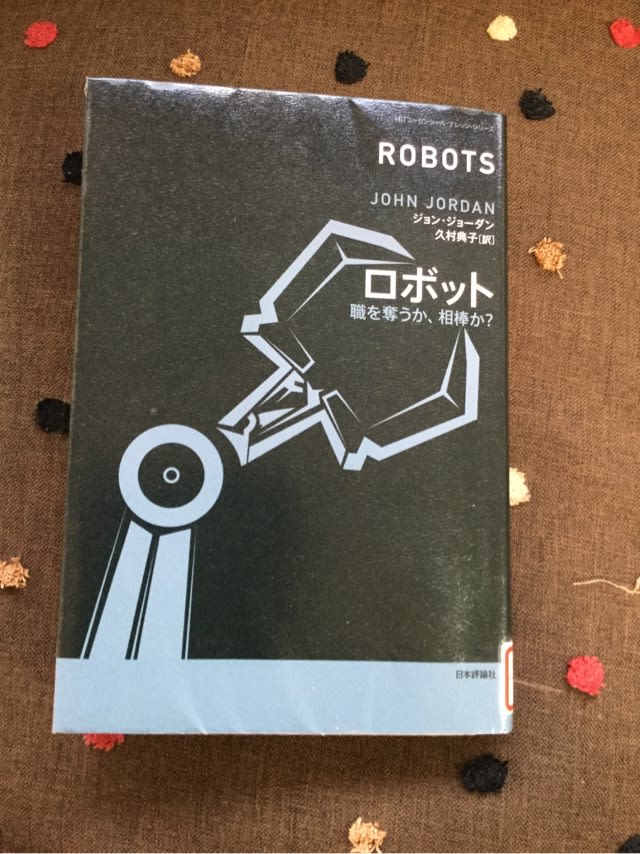藤沢周平の娘さんの遠藤展子さんが藤沢周平の手帳に書かれた日記をおいながら難しいサラリーマンと小説執筆の二足の草鞋生活でも実直な生き方を変えず小説執筆を続けて、遂に直木賞を受賞し、サラリーマンを辞めて作家になった。作家って才能があれば簡単に作品が書けるのかと思っていたが藤沢周平の遺された手帳を読んで、大変さがよくわかった。そればかりでなく地道な資料の読み込みや絶えず書き続けなければならないプレッシャーに打ち勝つには書く事が好きで好きでたまらない人だったのだと思う。
作者の遠藤展子も父のDNAを受け継いで素晴らしい書き手だった。楽しかった!

作者の遠藤展子も父のDNAを受け継いで素晴らしい書き手だった。楽しかった!