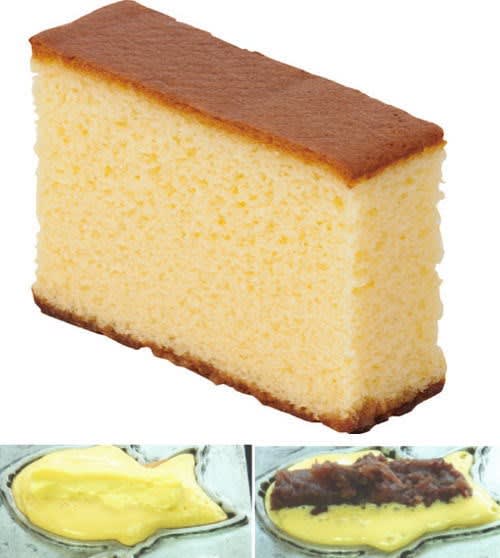5分で分かる「西郷どん」第39回『父、西郷隆盛』
翌年に帰国、兵部権大丞(ひょうぶごんのだいじょう)に任じられる。警察制度の確立にも尽した。
「ポリス?」
「街の治安を守るサムライじゃ」
「ほう」
「俺いは日本の治安を守るポリスを創りたかっち思うちょおぅ」
「そいはよかぁ、そいができればサムライたちに新しか仕事を与えるこっができる」
。。。
「俺いは戊辰のいくさで大勢を死なせてしもた。政をする資格はなか」
。。。
「俺いもいくさは見たくなか、それにはやっぱり、戦わずして勝てるほどの強か軍がいる。政府直属の軍じゃ、そいを兄さあに創ってもらいたか。あいだけの犠牲を払ったんじゃ、あん者んたちの命を無駄にせんでくいやんせ」
と言って兄さあを連れ戻しにきたのだった。
西郷は35歳 愛加那25
西郷隆盛、藩主の島津斉彬(なりあきら)の急死で失脚し、奄美大島に流される。
安政六年 1859 から文久二年 1862(3年2ヶ月)龍郷潜居
半年後西郷再び遠島 徳之島に到着
3日後 愛加那 菊草(のち菊子)を産む
愛加那 徳之島の西郷を訪ねる
西郷沖ノ永良部島での遠島生活に入る
元治元年 1864 赦免 鹿児島に戻る
このとき、愛加那28歳 菊次郎4歳 菊草3歳
以来、愛加那は遂に西郷と再会することはなかった。
慶応元年(1865) 隆盛、糸子(鹿児島藩士岩山八郎太の次女)と結婚
明治2年 (1869) 鹿児島西郷本家に引き取られる。
菊草(菊子)は明治9年(1876)に同じく西郷本家に引き取られる。14歳
菊草は大山巌(いわお)の弟誠之助と結婚。経済的にめぐまれず苦労は絶えなかった。
子供4人
明治38(1905)年 子供二人とともに京都の菊次郎のもとへ移り住む
菊草は龍郷で離れ離れになった母愛加那と、再び会うことはかなわなかった。
明治5年 (1872) 13歳でアメリカ留学
明治7年 (1874) 政府の財政難で帰国
明治10年 (1877) 17歳で 西南戦争に従軍し、右足膝下から切断の重傷を負う
東京では父隆盛の三弟で明治政府の重鎮 西郷従道(つぐみち)の世話になる。
明治13年 (1880)11年ぶり、龍郷で母と再会 なつかしい故郷の山々を見渡す。
明治18年 (1885)外務省書記生 アメリカ公使館勤務
明治20年 (1887)アメリカ留学 右足治療のため帰国
明治26年(1893)久子と結婚 十人の子宝に恵まれる
明治28年 (1895)台湾総督府参事官心得
日清戦争で日本が台湾を得たのは明治28年(1895)
明治28年 鹿児島から台湾への途次 名瀬で母と15年ぶり再会(当時の島司は笹森儀助(のち青森市長)菊次郎が生まれた龍郷の龍家本家跡近くに、笹森儀助島司 顕彰の碑がある。 県道81号 島のブルース歌碑の向かい側にある。
明治29年 (1896)台北県支庁長
明治30年(1897)台湾 宜蘭(ぎらん)庁長に就任(県知事に相当 4年半)
明治35年(1902)母 愛加那死去 1837年生 (65) (台湾で龍郷からの電報をうける)
明治37年(1904)京都市長に就任 1911年辞職
明治42年 (1908) 妹 菊子死去 1862生(46)
明治45年(1911~1920)島津家鉱業館長
昭和3年(1928)11/27 菊次郎 鹿児島で没 68歳
1895年(明治28年)- 台湾台北県基隆宜蘭支庁長に就任
1897年(明治30年)- 台湾宜蘭県宜蘭庁長官に就任
1904年(明治37年)10月12日 - 2代目京都市長に就任
wikipedia