石山寺山門近くのお店に、源氏香と扇が描かれている小さな屏風が飾ってありました。
「この屏風の絵は何かしら」と気になり、写真を撮りました。

知っている人によると、これは投扇興(とうせんきょう)の銘定表だそうです。
紫式部 

この和歌は何と書いてあるのだろう。

私には判読できません。
判読できた人によると、
花園に たはるる蝶の おもかげを
あふき(扇)の風に まかせてぞみる
だそうです。
※たはる【戯る・狂る】は古語
「信行」は、おそらく江戸時代末期・明治時代の歌人 「須川信行」だろうということに落ち着きました。
この銘定表には、源氏香と巻名と得点が書いてあります。

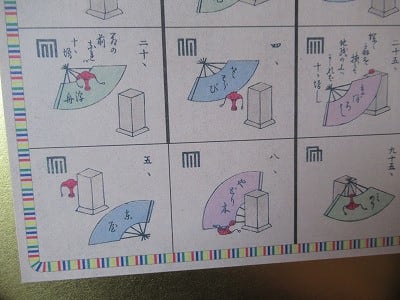
投扇興(とうせんきょう)は、「蝶(的)」「枕(土台)」「扇子(投扇興用)」の3つの道具を使った遊び です。
扇の上に蝶が載ることもあるのですねぇ。
一度この遊びをしてみたくなりました。
いつかそのチャンスがあるかしら。
体験できるところがあるようです。
舞扇堂の投扇興体験では、服の上から法被(はっぴ)を着て体験していただけますので、SNS映えもバッチリ!
八坂の塔を臨む和室で、京都らしい情緒を感じながら楽しく投扇興で遊んでいただけます。
八坂の塔を臨む和室で、京都らしい情緒を感じながら楽しく投扇興で遊んでいただけます。
体験料金は一人3,000円
※2名~4名、45分~60分、お茶菓子付き
----------------------------------------------------------------------
11月1日(金曜)、NHKのEテレの番組(21時~「芸能きわみ堂」)で投扇興(とうせんきょう)が出てくるそうな。
-----------------------------------------------------------------------
https://blog.goo.ne.jp/admin/entry?eid=3488da9f9ad88c032a860ebaea13b10e&sc=c2VhcmNoX3R5cGU9MCZsaW1pdD01MCZzb3J0PWRlc2MmY2F0ZWdvcnlfaWQ9JnltZD0mcD0xより引用
AI による概要
投扇興(とうせんきょう)は、扇子を「蝶」と呼ばれる的めがけて投げ、その形によって点数を競う日本の伝統的な遊びです。
遊び方
土台(枕)に的(蝶)を立て、扇子を投げ、扇子・蝶・台の配置(銘)によって得点を競う
投扇興(とうせんきょう)は、扇子を「蝶」と呼ばれる的めがけて投げ、その形によって点数を競う日本の伝統的な遊びです。
遊び方
土台(枕)に的(蝶)を立て、扇子を投げ、扇子・蝶・台の配置(銘)によって得点を競う
得点の算出
扇と的の落ちた形を源氏物語の54帖になぞらえた図式に照らして採点する
特徴
一対一(2人)で行われる対戦型のゲーム
発祥
安永2年(1773)の「投扇興図式」の序によると京都に起こったものと伝えられている
発想の根元
中国から伝来した投壺(とうこ、つぼうち)という遊戯
投扇興は、江戸時代に大人から子供まで、庶民の間に広まった遊びで、今では舞妓さんのお座敷遊びのイメージがあります。
-----------------------------------------------------------------------
流派
流派としては其扇流(きせんりゅう)・御扇流(みせんりゅう)・都御流(みやこおんりゅう)・戸羽流(とわりゅう)の四大流派が有名。
銘定
流派によって、銘定はいろいろあるようです。
例えば、都御流の銘定(源氏物語形式)「投扇式」という文献に見られる、源氏物語形式の54種の銘定。
御扇流は独自の百人一首形式24種類。
其扇流などは銘定を門外不出としている 。
新扇堂の扇に書かれている銘定は全部で34種類。

























