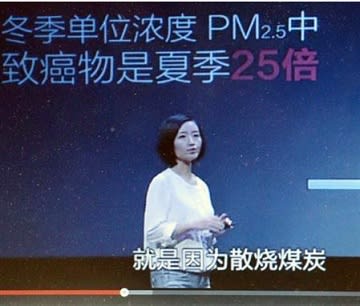(日本のメディアでは「最後に握手した」と紹介されていますが、ドイツ紙では「握手しようとしたが、アシモは反応しなかった」とも。まあ、どっちでもいい話ですが、せっかくならアシモもドイツ語でおもてなしすればよかったのに・・・。
写真は【ドイツ大使館HP】より なお、動画もyoutubeにあります。https://www.youtube.com/watch?v=RAjESb5QWSQ 握手シーンはカットされています。全体に微妙な空気にも思えます。)
【「(答えは日本の)社会の中から出てこなければならない」】
来日したドイツ・メルケル首相は、緊張する東アジア情勢や、日本とは異なる選択をしている原発問題などについては、あからさまな日本批判を避ける慎重な姿勢に留意したそうです。
****慎重に徹したメルケル首相=日本内の議論尊重―独紙報道*****
ドイツ各紙はメルケル首相が行った訪日を10日付の紙面で報道。メルケル氏が日本と近隣国の関係改善やエネルギー政策の在り方について、日本国内での議論を尊重する姿勢を示し、「極めて慎重」(南ドイツ新聞)な発言に徹したと伝えた。
独有力紙フランクフルター・アルゲマイネは、9日のメルケル首相の講演に言及。質疑で日本はドイツの戦後対応から何を学べるかという問いに対し、メルケル氏が「(答えは日本の)社会の中から出てこなければならない」と応じたことを紹介。
「日本に助言をするために来たわけではない」という記者会見での言葉も引用し、同紙はメルケル氏が「(発言に)用心深い態度を保った」と分析した。
南ドイツ新聞はエネルギー政策に関し、「他国へのあからさまな忠告は逆効果を生むとメルケル首相は知っている。首相は日本批判はやめ、ドイツが選んだ(脱原発の)道がなぜ正しいと考えているかを説明するだけにとどめた」と解説した。【3月10日 時事】
*******************
そのうえでのメルケル首相の主な発言は以下のように紹介されています。
****歴史や領土問題に関するメルケル氏の主な発言****
「第2次世界大戦後の独仏の和解は、隣国フランスの寛容な振る舞いがなかったら可能ではなかった。ドイツもありのままを見ようという用意があった」
「アジア地域に存在する国境問題も、あらゆる試みを重ねて平和的な解決策を模索しなければならない」(いずれも9日の来日講演会で)
*
「(ナチスドイツの)過去の総括は和解の前提になっている。和解の仕事があったからこそ、EU(欧州連合)をつくることができた」(9日の日独首脳会談後の記者会見で)【3月11日 朝日】
******************
岡田・民主代表と会談では、“慰安婦問題にも言及し「東アジアの環境を考えると日韓関係は非常に重要で、きちんと和解を進めることが重要だ」と関係改善を促した。”【3月10日 毎日】とも。
こうしたメルケル首相のドイツの経験を語りながらも問題提起ともとれる発言に、日本や周辺国は敏感に反応しています。
****メルケル氏発言に反響 歴史認識巡り各国****
約7年ぶりの日本訪問を終えたドイツのアンゲラ・メルケル首相による歴史認識に絡む発言を、各国メディアは大きく報じた。
中韓メディアは、日本に歴史を直視するよう求めたなどと指摘し、欧州でもドイツが歴史認識をめぐる日本の議論に介入したと報じられた。
■ドイツ 「礼儀正しく批判」
メルケル、礼儀正しく批判を試みる――。リベラル系有力紙の南ドイツ新聞(電子版)は、メルケル首相と安倍晋三首相の9日の首脳会談をこんな見出しで伝えた。
今回の訪日は戦後70年という節目の年に実現し、首脳会談は東京電力福島第一原発事故から4年の2日前に設定された。同紙は今回の訪日に、メルケル氏が「歴史認識」「脱原発」の二つの問題提起を秘めていたと分析。
メルケル氏は「外国への助言がしばしば逆効果になると知っており、日本批判をあえて避け、ドイツの選択の正しさを説明する道をとった」と読み解いた。
ところが、会談後の共同記者会見では、脱原発も歴史認識でも日独首脳の方向性の違いが際だった。
また、メルケル氏は日本科学未来館(東京都江東区)を9日に訪れ、二足歩行ロボット「ASIMO(アシモ)」と面会。握手しようとしたが、アシモは反応しなかったという。「訪日中、メルケル氏をこわばらせたのはアシモと安倍首相だった」。同紙は皮肉たっぷりに書いた。
9日付の独保守系フランクフルター・アルゲマイネ紙(電子版)の見出しは「安倍晋三首相に『ドイツの教訓』」。朝日新聞社などが共催した9日の来日講演会での歴史認識を巡るメルケル氏の発言を取り上げ、「期待されていたあからさまな発言で、安倍政権への批判に喜んで用いられるだろう」と伝えた。
■中韓 「過去の直視を忠告」
中国の国営の中国中央テレビは9日夜のニュース番組で「メルケル首相は、ドイツは過去ときちんと向き合ったから隣国の理解を得られたと語った」とし、「日本に歴史問題で忠告した」と報じた。
国営新華社通信も「ドイツの首相は、歴史を直視することが国際社会復帰の前提になると2度も語った」と伝えた。
一方で、この日の外務省の定例会見では、メルケル氏の発言を引用し「(戦勝国の)フランスは(敗戦国の)ドイツに一定の善意を示した。中国も日本に同様の対応はしないのか」との質問が出た。
洪磊・副報道局長は「このような重要な年に、日本の政治家が正しい選択をすることを希望する」と述べるにとどめた。国際情報紙「環球時報」は10日、「隣国の寛容さがなければ(和解は)成り立たなかったが、最も重要なのはドイツが歴史に向き合ったことだ」と強調した。
韓国の主要紙は10日付の朝刊で、メルケル氏の発言を1面で扱った。いずれも「過去の総括は和解の前提」といった部分を取りあげ、メルケル氏が日本に、過去の歴史の直視や反省を求めたと伝えた。
東亜日報は「ドイツの経験を聞かせる方式で、安倍首相に過去の歴史を直視するよう忠告したものだ」と論評。朝鮮日報は「ドイツと日本は同じ第2次大戦の戦犯国家でありながら、それを清算する努力の面では相反する道を歩んできた」と主張した。
韓国外交省報道官は10日の定例会見で、メルケル氏の発言について見解を問われ、「ドイツが歴史を直視する中で一貫して見せてきた反省が欧州の和解、協力、統合の土台になったことが歴史的教訓だ」と指摘。
「日本が歴史を直視する勇気と過去の歴史の傷を癒やす努力を通じ、周辺国と国際社会に信頼を積み上げていくことを期待する」と述べた。
■英仏 「議論に介入」「近隣も念頭」
英BBCは9日、メルケル氏が、戦後ドイツが国際社会に復帰できたのは「過去ときちんと向き合ってきたため」と述べたと紹介した。
その背景として、安倍首相が戦後70年談話で過去の首相談話での謝罪を骨抜きにするとの見方や、靖国神社参拝に中国や韓国から強い批判があると説明。
メルケル氏の発言は、近隣諸国との緊張関係を抱える安倍政権に、過去との向き合い方を暗に助言したものだととらえて報じた。
英フィナンシャル・タイムズ紙(電子版)はメルケル氏の発言を「日本が第2次世界大戦をどう記憶するかの議論に介入した」と報じた。戦後和平は旧敵国フランスの「寛容な振る舞い」で可能だったとの発言にも触れ、「日本の近隣諸国にもメッセージを発した」とした。
仏紙ルモンド(同)も「過去と向き合う。それがメルケル氏のアドバイスだ」と書いた。(後略)【3月11日 朝日】
*******************
【日本社会の中から出てくる答えは・・・】
日本の反応は・・・と言えば、気にいらなかった向きが多いようです。
****メルケル独首相、ナチスと日本混同か 「中韓のロビー活動の影響」安易な同一視避けるべき****
ドイツのメルケル首相は10日の民主党の岡田克也代表との会談で、ナチスによる犯罪行為への反省に触れつつ、日本に慰安婦問題の解決を促した。
これは、戦前・戦中の日本と独裁者、ヒトラー総統率いるナチス・ドイツとの混同とも受け取れ、問題といえる。
「米国は同盟国で、長年の付き合いがあるのでまだ知識層は分かっているが、欧州各国は韓国のロビー活動に相当影響されている」外務省幹部はこう警鐘を鳴らす。
韓国だけでなく、中国も安倍晋三首相をヒトラーになぞらえたり、南京事件をユダヤ人大虐殺(ホロコースト)と同一視したりするなどの宣伝工作活動を世界で展開している。
メルケル氏が9日の安倍首相との共同記者会見で、日本の行為を指してではないもののホロコーストに言及し、「過去の総括は和解のための前提だ」と指摘したことも、旧日本軍とナチスを一定程度混同している可能性をうかがわせる。
だが、戦前・戦中の日本では、兵士らの暴走による戦争犯罪はあっても、ナチス・ドイツのような組織的な特定人種の迫害・抹殺行為など全く行っていない。
東京裁判でインド代表のパール判事は「本件被告の場合は、ナポレオンやヒトラー(ら独裁者)のいずれの場合とも、いかなる点でも、同一視することはできない。日本の憲法は完全に機能を発揮していた」と主張している。
また、今年1月末に死去したドイツのワイツゼッカー元大統領も、有名な1985(昭和60)年の演説でこう強調しているのである。「ユダヤ人という人種をことごとく抹殺するというのは、歴史に前例がない」
ナチス・ドイツの戦争犯罪を裁いたニュルンベルク裁判では、有罪となった19人のうち16人までが一般住民に対する殲滅(せんめつ)、奴隷化や人種的迫害による「人道に対する罪」で有罪とされたが、東京裁判では誰もこの罪に問われなかった。
同じ敗戦国とはいえ、日本とドイツでは戦いの様相が全く違う。まして日本の隣国は韓国や中国であって、ドイツが和解を果たしたというフランスやポーランドではない。安易な同一視や混同は避けるべきだろう。【3月11日 産経】
*****************
【国家を突き動かす屈辱感】
“組織的な特定人種の迫害・抹殺行為など全く行っていない”にしても、八紘一宇のもとで日本を中心とした政治秩序、日本の価値観・文化を他国へ強要し、その過程で多大な生命・財産の犠牲を強いた歴史が正当化される訳でもないでしょう。
そうした過去と向き合うことは現在では“自虐”と見なされるようにもなり、“兵士らの暴走による戦争犯罪はあっても”全体としては国策を誤った訳ではないと自らを正当化するのが近年の流れにもなっているようです。
そこからは、反省も、謝罪も出てきません。出てくるのは“間違ってもいないのに、批判ばかりされる”という屈辱感でしょう。
そうした屈辱感は、かつての“栄光”を取り戻そうと国際秩序を無視した行動にはやるロシアや中国を突き動かしている感情と同じようなものに思われます。
****ギリシャやロシア、中国に見る「屈辱の政治」人間と同じくらい繊細な国民国家、紛争解決には感情への配慮が必要****
アレクシス・チプラス氏は今年1月にギリシャの首相に選ばれる直前に、有権者にこんな誓いを立てていた。「月曜日には国民の屈辱の日々が終わる。外国からの命令とはおさらばだ」
国民の屈辱を強調したこの発言をギリシャの突飛さとして片づける気になった人は、世界のほかの国々にも目を向けるべきだ。(中略)
傷つけられた国家のプライド
・・・・ギリシャ政府による債権者との衝突と同様に、ロシアによる西側諸国との対立は、国家のプライドを傷つけられたという感覚を糧にしている。
ウラジーミル・プーチン大統領と同氏の世代の指導者たちはかつて、ソビエト連邦という今日よりも広大で強力な国家のために働いていた。
そしてプーチン氏は、現代のロシアは引き続き「偉大な国家」として扱われるべきだと主張している。
ロシア政府はウクライナ介入の理由として、海軍基地や市場、国境といった実在する権益を守ることを挙げているが、これは表向きの理由であり、ロシア政府の言葉には国家が屈辱を味わったという感覚があふれている。ロシアはもう軽視したり無視したりできない国だと訴えているのだ。(中略)
中国の他国に対するアプローチにおいても、国家の屈辱という感覚は大きな位置を占めている。
中国の歴史の教科書や北京の国家博物館の展示は、西洋の帝国主義に初めて遭遇した1840年代から日本が敗戦した1945年までの「屈辱の世紀」について詳しく記述している。
中国の若者たちは、弱かった中国は外国の列強に辱められ搾取されたのだと何度も聞かされている。現代の中国はもう小突き回されない、と教えられている。
中国の習近平国家主席は「新型大国関係」なるものを望んでいる。中国は米国と同等に扱われるべきだ、と求めているのだ。
憎み合うイラン政府とISISにも共通点
イスラム原理主義者たちも、西側諸国はイスラム教徒を侮辱し迫害しているとの考え方に乗じている。(中略)
2011年に中東各地で革命が始まった時、アラブの人々の多くは、自分たちが味わっている窮状と屈辱の真の原因は自国の政府にあると判断していたようだった。
しかしその後は、よそ者や西側諸国のせいにするのが再び流行になっている。イラン政府と「イラク・シリアのイスラム国(ISIS)」は互いに忌み嫌っているが、両者とも、西側から受けていると思われている侮辱をはねつけると約束している(イランは、自分たちには核開発計画を進める権利があると主張しており、片やISISは西側の価値観を批判している)。(中略)
これらのことが意味するのは、国際紛争を解決するためには、利益と同じくらい感情について考える必要があるかもしれないということだ。(後略)【3月10日付 英フィナンシャル・タイムズ紙】
*******************
いわれなき批判にさらされているという屈辱感、自らの正しさを認めてもらいたいという欲求は、周辺諸国との軋轢を強め、抜き差しならないところへ向かうようにも思えます。
また70年前と同じことを繰り返し、また同じような多大な犠牲を自他に強いて、ようやくそうした感情は収まるのでしょう。
しかし、その反省もまた数十年すれば薄れ・・・。
世界に誇れる文化・国民性を有しながら残念なことです。