この勝頼の妻も始めてねずさんに教えて貰いましたが、その若さと教養に唖然とさせられました。
この歳まで、如何に勉強してこなかったかを思い知らされました。それにしても、昔の日本人の素晴らしさは想像を絶するものがあります。
これが、歴史では散々バカにされている武田勝頼の妻ということは、勝頼の教養もそれに劣らないものがあったのじゃないでしょうか。
やはり、教養というのは大切なものです。こういうのを知ると、自分がどんなに情けない人生を送ってきたかと反省するしかない。
何時ものように全文をリンク元で読んでください。
死ねば魂が肉体から離れ去ります。だからこれを「逝去(せいきょ)」といいます。「逝」という字は、折れて進む(辶)です。つくりの「折」はバラバラになることを意味します。肉体と魂がバラバラに離れるから「逝」です。そして魂が去っていくから「逝去」です。魂が行く世界は、時間に縛られた低次元の世界から、時空を超越した高次元の神々の世界まで様々です。ですから位の高い神様は、上古の昔も、今も、未来にも存在します。勝頼の妻の辞世の歌は、そういう理解の上に成り立っています。
歌にある「玉の緒」というのは、魂の緒のことです。魂は紐で肉体とつながっていると考えられていましたから、玉の緒が離れることは、死を意味します。露と消える玉の緒であっても、ひとつの思いは消えることはない。その消えない思いというのが、夫である勝頼と、今生では乱れた黒髪のような乱世を生きることに成ってしまったけれど、きっと来世には平和な時代に生まれて、一緒に仲良く、長く一緒に暮らしましょうね、というのが、この歌の意味です。
そして「黒髪の乱れる」は、和泉式部の歌から本歌取り。失っても失っても、それでも一途に愛する想いを大切にするところで使われる語です。
「玉の緒」は式子内親王の歌から本歌取りしています。たとえ露と消えて死んでしまっても、大切なものを護り通して行きたいという想いが込められた語です。
このとき勝頼の妻、わずか19歳です。
いまから400年も昔の戦国時代。現代日本人の感覚としては、戦国時代というのは、有史以来最も国が荒れた時代です。けれどそんな時代にあってなお、若い女性がこれだけ高い教養を持ち、そして男も女も純粋に、必死で生きていたのです。そうすることができたのが日本の国柄です。
【出典】『女子鑑(じょしかがみ)』大阪府学務部・昭和13年刊
日本を取り戻すや再生が必要と思いますが、並大抵のことでは適わないようです。それ程に、先人は凄かった。










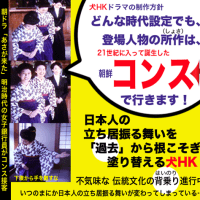
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます