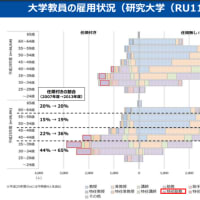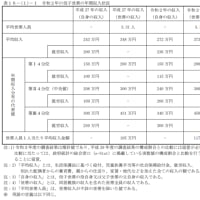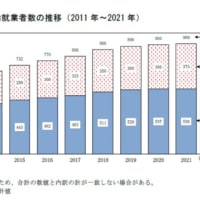朝日新聞に、「大企業病は、大企業に限ったことではないのだな~」という気がする記事があった。
朝日新聞:会議の力「言われたことは一生懸命やります」からの脱却
随分前から、企業が変革できない理由の一つとして挙げられているのが、「大企業病」と呼ばれるものだ。
「トップダウン式」の指示の仕方で、現場で働く人達や若い人たちの意見を吸い上げる事ができず、「前例主義」とか「慣例主義」と呼ばれるような企業体質に陥っている状況が「大企業病」と呼ばれている。
この記事を読む限り、企業規模は決して「大企業」と呼ばれるほどではなさそうだ。
現場で働いている人たちは「言われたことは一生懸命やるけど、それ以外のことはしたくない」と、言っている。
このことは、この企業に限ったことではないと思っている。
何故なら、このような「言われたことだけをやれば良い」という、指示を出している企業は規模の大小に関係なく日本には多いのでは?と、感じることが多々あるからだ。
この「言われたことは一生懸命にする」という言葉に、ある種の「怖さ」を感じたのは、私だけだろうか?
「怖い」と感じた理由は、ナチスの残虐的行為の象徴である「ホロコースト」の指揮を執り、多くの人々をガス室送りにしたアイヒマンが、長い逃亡の後で逮捕をされ、裁判にかけられたときに話した言葉と通じるものがあったからだ。
この裁判については、ハンナ・アーレントの「全体主義の起源」に詳しいはずだが、野心だけはある凡庸で小心者であるアイヒマンが、「ホロコースト」を作り出した理由が「自分は何も悪くはない。すべてヒットラーの指示に従っただけだ」という趣旨の証言をしているからだ。
「自分は何も悪くない。ヒットラーの指示に従っただけ」ということは、アイヒマン自身が自分の行いに対して、何も考えず・疑問も感じずに自身の野望を満たす為に「ホロコースト」の指揮を執っていた、ということでもある。
「ホロコースト」と、一企業の会議と一緒にする事は乱暴な話ではあるが、問題は「自分で考えない」という点なのだ。
「言われたことは一生懸命にするが、そこには自分の責任はない=仕事の責任は仕事の命令者にある」ということでもあるのだ。
そしてこのような傾向が、日本で強いのは「父権主義」あるいは「権威主義」によるところが大きいのでは?と、考えている。
だからと言って、この「父権主義・権威主義」的組織が、その責任者という役割を持っている人物に、責任を負わせているのか?と言えば、決してそうではない。
何故なら、その前に「前例主義」あるいは「慣例主義」があるからだ。
前例や慣例に従うことで、父権主義あるいは権威主義は、責任そのものを逃れる事ができるようになっている。
それは、どこを切り取っても、考えることもなければ責任を負うというある種のリスクも負わない、ということでもあるのだ。
このような考えが社会の中心となっていけば、日本そのものが諸外国から遅れを取っていくのは当然だろう。
因みにこの記事の最後には、「言われたことは一生懸命にやる」と言っていた人たちは、「自分で楽しい仕事」をするために、考え・行動をするようになっていく。
もちろんそこには、考えに基づく行動には責任がある、ということを十分に理解している姿がある。
それは「自分の人生を楽しむ責任」を感じているからなのでは?と、思うのだ。