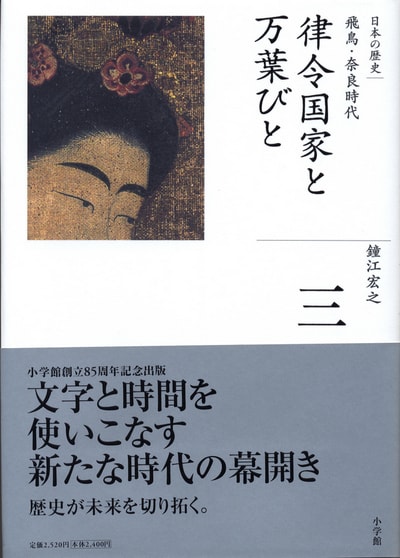
日本の歴史シリーズも3巻目。先は、長いが、寄り道ばかりして、なかなか前に進まない。
3巻目は、オーソドックス。だから2巻目と内容がだぶっている部分もある。こちらは、読み物として読んでいるから、それも面白い。
本書で面白かったのは、歴史の時間に、世の中が変わったと思いっ切り習った大化の改新は、政権が代わったという意味では、重要だが、本当の歴史の大きな変化が起こったのは、ずっと後の701年の大宝律令の頃だということ。大化の改新の頃は、まだ年号も使われておらず、60年で一周する干支を使っていたという事実。その他のいろんな中国の制度が、導入されたのも、それ以降。
漢字はどうか。一番古いと見られるのは、三重県で発見された土器に刻まれた"奉"あるいは"年"のような文字という。2世紀頃というから相当古い。ただし、庶民に浸透するまでには、相当の時間を要した。
暦はどうか。これは、6世紀中ごろからと考えられるが、中国で、暦が切り替えられると後追いで、日本の暦が切り替えられるということが続いたようだ。日本の暦になったのは、17世紀のことだ。
時計は、飛鳥で見た漏刻が最も古い時計と考えられれている。水が漏れる測度を一定にして、水がたまる時間を基準にした時計だ。多賀城でも見た。
人の名前も、"阿弥多"のような仏教に因んだものとか、一つの名前に、"古"、"新"、"若"などを付けただけのものなど、かなりいい加減なものだった。麻呂も良く使われたものだが、後に、"麿"になり、"丸"になった。牛若丸が、奈良時代だったら牛若麻呂だったかもしれない。
まさに、この700年頃を境に、韓国を向いていた日本が、中国を向いて学ぶうようになったのだ。金さんの、日本=百済論を思い出してしまう。
戸籍や、貨幣など、第2巻でも触れられていたように、途中で、廃れてしまった制度も多いのだが。
そして、最初の中国風都城である藤原京が作られた。湿地帯への、結構無理な都建設だったらしい。大きさは、平城京と同規模だったが、こちらも、すぐ、平城京に遷ることとなる。中国の文化、制度の導入を、急ぎ過ぎていたようだ。
飛鳥から奈良の時代を、生き生きと描いてくれる良書だと思う。















