相変らず地震が多い。
それも、場所がばらばら。
能登半島の付け根の方は、地震が少なかったと思うのだが、先端の方で、大地震が連続して発生している。
こればかりは、来たらよけようがないので、来ないことを祈るしかない。
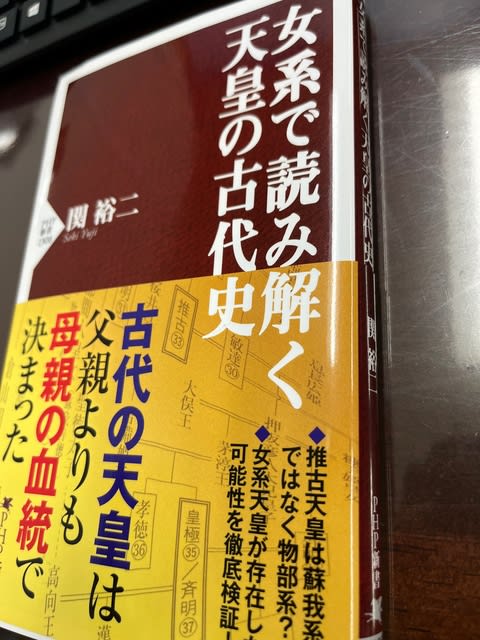
また関さんの本を買ってしまった。
まだ出たばかり。
題名は、異なるのだが、中身は、既書と重複するところが多い。
本書も、女系で読み解くとあるが、結局女性天皇の時代の古代史を、女性天皇中心に再構築しているということで、特に新味はない。
でも、読んでしまう。
ただそうなってしまうのは、無理のないところで、女性天皇と言っても、一括りにできるものではなく、時々の異なる事情を背景に生まれたものだから、そこに一つの法則的なものを導き出すのは難しい。
強いて言えば、最初は、巫女的な存在だったが、女帝(先帝の配偶者が中心)が生まれてきて、律令が整い本格的な女帝が出だすが、孝謙/称徳以来ぷっつりと途絶えるという歴史になる。
まずは、最初の推古天皇が生まれる前の大和朝廷の話になるが、これは、いつものタニハ連合(但馬、丹波、丹後、若狭)の話が中心。
このタニハ連合が、北九州、出雲連合と対抗していたが、吉備と東海の勢力が台頭し、ヤマトを立ち上げたということになる。
そういえば、タニハ連合の地域にはあまり行ったことがなかったので、7月に旅行を計画している。
ヤマト建国には3つの王家(瀬戸内海=物部、東海=尾張、日本海勢力=タニハ)がかかわっており、建国後も、この3勢力が絡みながら政権を支え、天皇を決めていた。
その日本海勢力を代表するのが、蘇我家で、そこに推古天皇が誕生。女帝が巫女的な存在であったことも初の女帝が立った一因かもしれない。
神代の時代から、混乱の時期に、女帝が求められた。
しかし、その子孫が天皇を継ぐことはなかった。
この3つの王家が、融和、対立を繰り返す中で、天皇も決まっていき、天武天皇の時代になって、まとまりが完成したと考えられる。
その後藤原氏が台頭すると、東との対立が再び深まっていく。
記紀以外の歴史書から、真実を探ろうとするのも、関さんの特徴で、推古天皇は、実は、物部系で、蘇我氏と共に、改革事業を推進したと推理する。
古代の女帝の最後となった称徳天皇の時代、道鏡とのスキャンダルが、天皇家の形骸化、藤原氏が実権を握る時代の到来のきっかけとなり、この3つの王家が覇権を争う時代は終わり、女帝を必要とする時代も終わったのではないか。
古代史の面白いところは、いろいろ推理ができることだが、ちょっと推理しすぎ?といつも感じるのだが、気のせいか。
それも、場所がばらばら。
能登半島の付け根の方は、地震が少なかったと思うのだが、先端の方で、大地震が連続して発生している。
こればかりは、来たらよけようがないので、来ないことを祈るしかない。
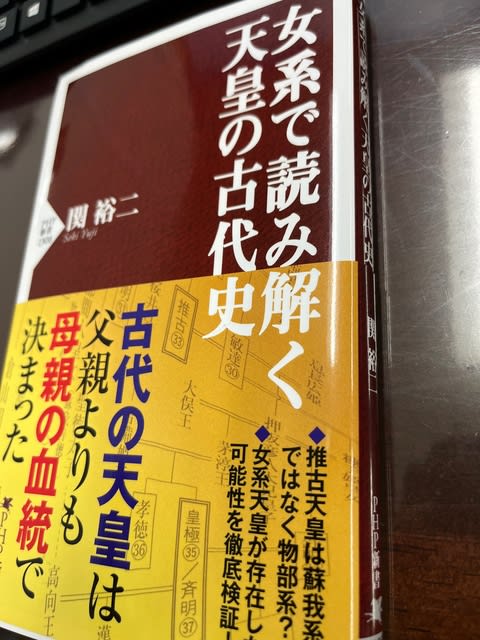
また関さんの本を買ってしまった。
まだ出たばかり。
題名は、異なるのだが、中身は、既書と重複するところが多い。
本書も、女系で読み解くとあるが、結局女性天皇の時代の古代史を、女性天皇中心に再構築しているということで、特に新味はない。
でも、読んでしまう。
ただそうなってしまうのは、無理のないところで、女性天皇と言っても、一括りにできるものではなく、時々の異なる事情を背景に生まれたものだから、そこに一つの法則的なものを導き出すのは難しい。
強いて言えば、最初は、巫女的な存在だったが、女帝(先帝の配偶者が中心)が生まれてきて、律令が整い本格的な女帝が出だすが、孝謙/称徳以来ぷっつりと途絶えるという歴史になる。
まずは、最初の推古天皇が生まれる前の大和朝廷の話になるが、これは、いつものタニハ連合(但馬、丹波、丹後、若狭)の話が中心。
このタニハ連合が、北九州、出雲連合と対抗していたが、吉備と東海の勢力が台頭し、ヤマトを立ち上げたということになる。
そういえば、タニハ連合の地域にはあまり行ったことがなかったので、7月に旅行を計画している。
ヤマト建国には3つの王家(瀬戸内海=物部、東海=尾張、日本海勢力=タニハ)がかかわっており、建国後も、この3勢力が絡みながら政権を支え、天皇を決めていた。
その日本海勢力を代表するのが、蘇我家で、そこに推古天皇が誕生。女帝が巫女的な存在であったことも初の女帝が立った一因かもしれない。
神代の時代から、混乱の時期に、女帝が求められた。
しかし、その子孫が天皇を継ぐことはなかった。
この3つの王家が、融和、対立を繰り返す中で、天皇も決まっていき、天武天皇の時代になって、まとまりが完成したと考えられる。
その後藤原氏が台頭すると、東との対立が再び深まっていく。
記紀以外の歴史書から、真実を探ろうとするのも、関さんの特徴で、推古天皇は、実は、物部系で、蘇我氏と共に、改革事業を推進したと推理する。
古代の女帝の最後となった称徳天皇の時代、道鏡とのスキャンダルが、天皇家の形骸化、藤原氏が実権を握る時代の到来のきっかけとなり、この3つの王家が覇権を争う時代は終わり、女帝を必要とする時代も終わったのではないか。
古代史の面白いところは、いろいろ推理ができることだが、ちょっと推理しすぎ?といつも感じるのだが、気のせいか。















