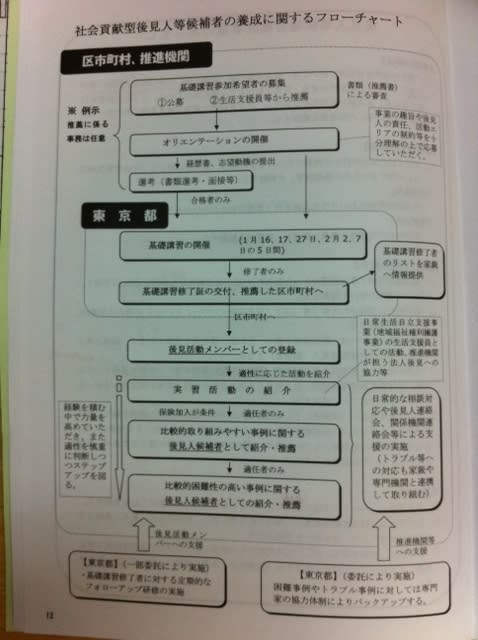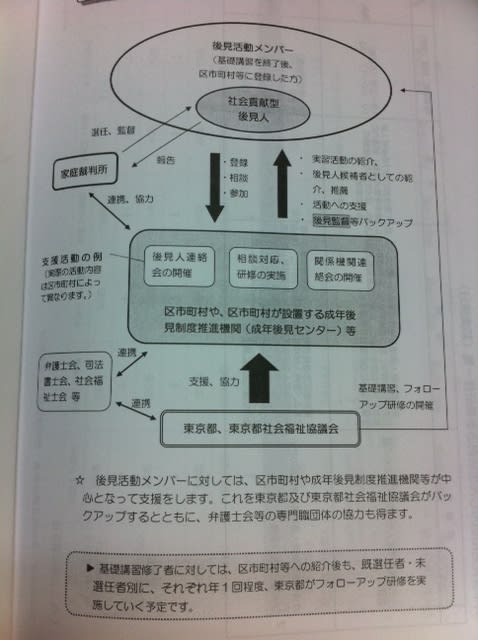東京都 社会貢献型後見人を目指す方のための基礎講習
プログラム2:被後見人等への支援の基本的視点
池原毅和(いけはら よしかず)氏 弁護士、NPO自律支援センターさぽーと代表
すばらしい講義でした。
この講義を聞いているのといないのとでは、今後の活動の深みが大きく異なっていたと思います。
成年後見でもっとも大事なことは、本人の「自己決定」を可能にすること、
能力をよく見極め、支援することで、出来ることの幅をひろげていき、「自己決定」を可能にすることに、後見人の本質があると感じました。
1)自己決定権、オートノミー
日本国憲法には入っていない概念で、欧米では1950~60年代に出てきた。
日本では、1990年代頃登場。
インフォームド・コンセント概念とともに広がってきた。
自己決定権とは、以下、三つのことがらが達成されることでなされる
1.価値観の自由
2.自己実現の自由
3.自己実現の支援を受ける権利
成年後見では、取消権、同意権、代理権を有し、被後見人の自己決定権と葛藤することとなる。
2)能力というものの理解の仕方
*能力があるかないかの「二分法」で分けて考えることは正しくない
*「変動性尺度モデル」で解釈すべき
すなわち、
人の能力(出来るか、出来ないか)は、解決すべき問題の難しさと、援助によって異なる。
*能力の有り無しを見極めるために、「役割交代テスト」を用いると有効である
*自己決定の支援の工夫として
どれくらいまわりの支援があるか、
時には、医師や医療関係者に相談する
問題をバラバラにして考える
3)国連 障害者権利条約
2006年 国連障害者権利条約 採択
2007年 日本政府 署名
批准には、国会の決議が必要
その十二条に、「支援を受けた自己決定」が謳われている
「小さな成年後見制度」のあり方の考え方に通じている
4)自己決定と多数決
いずれも意思決定のルール
多数決:最終的な(十分な意見交換、十分な審議を経て)決定権(決定は覆さない)は、多数者
自己決定:最終的な(熟慮して)決定権は、本人
5)孤立したひとの自己決定
障害のある方々は、人間関係のネットワークを築く機会を失われている
6)説得的コミュニケーションとリスクコミュニケーション
私たちの価値を知らず知らずに押しつけている説得的コミュニケーションになっているため、そのことに注意しようとすること
リスクコミュニケーション、どこまでも一緒にやっていくよ。
他職種のチーム、複数で注意すると良い
7)成年後見人としての判断の基準
1.Best Interest(本人の最善の利益)神様の目から見て
2.Substituted Judgement(代行判断基準)その本人が能力をもっていたらこうしたであろう
3.Wish(願望、希望)
4.Least Restrictive Alternative(最も制限が少ない選択肢、自由最大化原則)
5.Most Integreted Enviroment(総合的環境を選ぶ、できるだけ普通の社会に似た社会、特殊化しない社会)
6.Humane Treatment(人間的処遇)
以上、