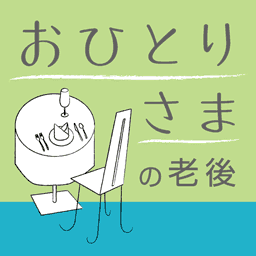最近、ブログにいろんなことを綴らなくなった。
例えば、つい最近、上野千鶴子さん(東大名誉教授・社会学者)のレクチャーを聴きに行ったことも、
もうひとつの別宅ブログにはちょっとサワリだけを書いたが、
本宅(蝶ブログ)には、やっと一週間も経ってから。
べつに、リアルタイムっぽいのは、別宅で、本宅は、後から、というわけでもないのだが。
街で見つけたおもしろいモノも、同じ写真をアップするのは気が引けて、
この蝶ブログには、未熟な、見るに耐えない幼稚園お絵かきみたいな自作のシロモノをアップしている。
私生活も、やたら忙しくて、連絡事項や、通信雑用で、細かい時間を奪われる。
ひとつのコミュニケーションではあるが。
それらは、わたしが、もしおひとり様なら、絶対に、関わっていなかったことばかり。
わたしは、ものすごくめんどくさがりで、ほっておくと、人間付き合いも、まったくしないに等しい。
たまたま家族がいるから、その家族から派生したお付き合いや、交流が生まれる。
自分の交流は、ごく自由度の高い、オアソビ交流しかない。
実は、上野千鶴子さんは、この、自由度の高い縁、「選択縁の社会」を理想としている。
20年ぐらい前にも、「女縁」ということで、取り上げられていたが、
いま、再び、おんなたちは、老後に向かって、また、全盛期の頃の縁とはまた違う角度から、
自分を取り巻く「社会」を見つめなおそうとしている。
結婚しなくなった人が増えるなか、死別、離別、非婚、とさまざまなケースはあるものの
おひとり様が、高齢化に伴い、ますます増加の一途。
家族持ちに代わって、人持ちへ、と、選択する縁を重要視する。
「家族がいる人は、もし、家族がいないとすると、それ以外のお付き合い(縁)って、ありますか?」
自分はおひとり様じゃないから、関係ないわ、とは、わたしは思わなかった。
でも、いざという時は、べっとり、家族に寄りかかっている自分がいる。
子供は、保険か?
趣味の場での皆々様方は、楽しい時間は共有するけれど、いざという時は、
お互い、各々の家族に委ねるだろう。
せいぜい、お見舞いに行くか、葬式に顔を出すぐらいのこと。
親身になって世話をし、フォローするのは、家族の役目、と、しゃしゃり出ることもしないだろう。
いい時だけのお付き合いって、ほんとうのお付き合いなんだろうか?
でも、誰も、家族持ちの人は、お互い、そんな深いシリアスなお付き合いは望んでいないと思う。
だが、おひとり様にとっては、家族に代わる、地縁でも血縁でもない、互助機能する縁、
強いネットワークが必要だと、上野氏は提唱する。
かつては、平均寿命が50歳の時代もあった。
少し前の老人の理想像は、縁側で孫を膝に抱くおじいちゃん、おばあちゃんだったが、
今は、80歳で20歳の孫は、大きくて重くて、膝には乗らない。
(ひ孫なら、わからなくもないが、義母は、ひ孫なんて、もう中学生。膝には乗らない。
自分の子供のうちの末っ子の、一番下の孫の、そのまた一番下のひ孫ぐらい、どうだろう?)
高齢化になり、社会が変化しているので、受け皿としての社会も対応を迫られる。
日ごろ、わたしが思いっきり(ブログで)悪態をついている夫も、強力な保険であるわけだ。
(しかし、これはお互い様である)
おひとり様になって、独自の強力なネットワークを築ける自信はないが、
いざとなると、意識の持ちようで変わるかも知れない。(→必要は発明の母)
例え、わたしが家族持ちでも、選択縁の定義で、いいなあと思ったのは、地縁でも血縁でもない、というところ。
夫の実家のある地域は、
古くからの因習や、旧来の価値観に閉ざされた、時代に合わない、人の出入りのない片田舎で、
その地で、親戚や近隣に、がんじがらめにされた老後を予想し、憂っているわたしとしては、
家族を頼りにせず、自分はおひとり様だという自覚で、新しいネットワークを築くぐらいの覚悟で、
これからの自分の将来を見据えていこうかと考えた。
頑張って、田舎での行事(法事など)に(無理やり、義母の指令で)参加しても、
地元の親戚は、「こっち(地元)に住んでない人だから・・・」と、わたしに距離を置く。
あたりまえ。
地元の人にとっては、その地に住んでいない人は、地元に馴染んでいない、好きでない、
価値観が違う、と、とらえる。
義母の代で、それはオシマイ、
わたしは、わたし流のやり方で・・・ということは、通用しない。
田舎には田舎流の長く続いたやり方があるから。
そして、最大の、どうしようもない不動のものは・・・義母とバトンタッチしても、
義母と同じコピー人間、すなわち、夫がいて、
これぞ長男の役割とばかりに、踏襲しようという固い意志を持って、わたしの前にデデンと立っている。
いずれ、また、息子に嫁が来て(来るんだろうか・・・)
代々踏襲したものを、また踏襲するのが、正しい、バトンタッチの方法なんだろうけれど。
わたしが、不調和音を唱えている限り、息子に嫁は来ないと思う。
仮に結婚したとしても、息子の嫁に、長男の嫁のなんやらかんやら、を、押し付ける役目は、まっぴらごめん。
夫よ、あなたがやりなさい。
こうやって、不出来な嫁(=わたし)を持ったばかりに、長男である夫は、苦労し、息子もまた苦労するわけだ。
だが、夫が嫁教育を、上下の絶対的な権力を背景に、親任せにして、
わたしと意見が合わないと、頭ごなしに怒ったり怒鳴りつけて強制的に従わせるだけで、
わたしを説得させるなり、粘り強く交渉してこなかったとにも原因はある。
素直に昔流のやり方を踏襲してくれる嫁をもう一度、もらう?
どうぞ、ご勝手に。
わたしは、本気で、家族に代わる、選択縁を築くことを目指し、
そういう方向性で、努力しようかと思った。
いまからでも遅くない。
昔のひとは、女に学問をさせることは、嫌う。
へんに、目が開いたかのように、意識に目覚めるからだ。
たしかに。
でも、意識だけではだめ。
イバラの道を歩む覚悟がなければ。そして、不断の努力。
言うだけなら、知っているだけなら、誰でもできる。
学者サマの論理を勝手に都合いいように、自分に応用するなんて・・・
いえ、それでこそ、学問は実用してこそ、生きるというもの。
単なる、こじつけか?
深い意味も理解しないで、自分に有利になるような部分だけを、勝手にピックアップして並べているだけ?
それとも、おんなに学問の機会を与えるな、ですか?
介護保険制度施行が大きい、と上野氏は、おっしゃっていました。
でも、こうやって、地方の活力や、美点が損なわれていく、なんて言われるんだろうなあ・・・