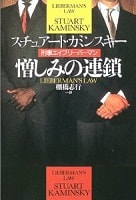
『晩春の雨が降っていた。ここ小さな簡易食堂(ダイナー)のカウンター係は年寄りで白いエプロンをかけて、陶器の容器に低カロリー・シュガーのスィートゥンローとイークウォルと砂糖の袋を詰めていた。
客は韓国人三人と奥のボックス席でサン・タイムズ紙を読んでいるがっしりとした白人の男だけだった。
入り口のドアが開いて降りしきる雨の音と湿った空気が流れ込んできた。三人の若い韓国人が入ってきた。客の三人の韓国人は急に用事を思い出したように、食べかけの料理を残して代金を払った。カウンター係と白人の男は若い韓国人に気づいてもいない風情だった。
カウンターに座った若い韓国人三人のうちサングラスをかけた男が言った。
「集金に来たんだ」
「集金って?」カウンター係が言う。
「みかじめ料、保護代だ」と若い男』
カウンター係はシカゴ市警のリーバーマン刑事、がっしりした男は、同じくハンラハン刑事だった。若い三人の韓国人は、まんまと蜘蛛の巣に囚われたようだ。
これがこの小説の導入部の一部だが本筋ではない。いわばサイド・ストーリーと言ったところ。ミア・シャヴォット教会堂の主礼拝堂の長椅子のクッションが切り裂かれ、聖櫃の中の聖典(トーラー)四冊のうち三冊が広げられ引き裂かれ、一冊は消えていた。
壁には「ユダヤ教徒はわれわれの赤ん坊を食らう」とか「ユダヤ人は出て行け、さもなくば死ね」と赤いペンキで殴り書きされていた。これが本筋のストーリー。
リーバーマンも妻ベスもこの教会の信徒だった。歴史的に貴重な聖典がなくなったことで怒りが沸騰した。この事件を追うリーバーマンとハンラハン。
もう一つサイド・ストーリーがある。リーバーマンの娘リサの結婚である。あらかじめ知らされていたとはいえ、オヘヤ国際空港のゲートでリサの相手アフリカ系アメリカ人と対面したときベスはこう思った。
「若い頃のシドニー・ポワティエには似ても似つかないわ」
リーバーマンは「リサは子供を作るだろう。子供の肌は黒くなるだろう。自分が80歳になる頃、この孫たちは10代になり町を歩くと人々が怖がるだろう」という思いが頭をよぎる。
リーバーマンは空港に立っているにもかかわらずアフリカ系アメリカ人のリサの夫マーヴィン・アレクサンダーに矢継ぎ早に質問の雨を降らせた。横にいるベスの制止を無視して。
「あんたはアメリカ人か?」
「これまで結婚したことは?」
「子供は?」
マーヴィンは、ジャマイカ生まれの両親に育てられ、スタンフォードで医学博士号をとり、結婚はしていたが妻が早くに亡くなり子供はいないという事情が分かった。この辺の記述にはアメリカ社会の人種に対する微妙な感情の揺れのようなもが感じられるところだ。
また、裏社会とのコネで持ちつ持たれつの関係は必要悪と思わせられる。事件捜査は、いろんな関連があって清く正しく捜査をしていればいいというものでもない。警察は犯人逮捕が至上命令だから。極上の警察小説だった。
















