ちょっと遅くなりましたが、東京大空襲(ここでは1945年3月10日のもの)70周年の前日
NZZ(新チューリヒ新聞)に東京大空襲に関する1ページの特集記事が載りました。
タイトルは「炎の地獄を逃れて」

上の写真をちょっとアップ

写真の女性は当時8才で、爆撃から逃げる途中家族とはぐれ、意識を失い、気がついたときには折り重なった死体の下にいました。上の人たちの身体が火を防いだため生き残ったのです。幸いにも空襲後、家族が再会、全員の無事が分かりました。直撃を受けた地域では幸運な例外かもしれません。
8才の少女が前日一緒に遊んだ近所の友達とは2度と会えなかったということです。
彼女は今、東京大空襲が忘れられることのないよう、ボランティアで体験談を語っているそうです。大人よりも小学生に話しているときの方が、しっかりとした手ごたえがあるそうです。8才の少女の体験ということで、感情移入しやすいのかも知れませんが、あるいは大人には、暗い話煩わしい話は面倒だという意識があるのかも知れません。
爆撃を受けた地域の地図をちょっとアップ

ちょっと見分けがつきにくいですが
藤色のところが1944年11月から1945年1月までに爆撃されたところ
灰色が1945年4月
黄土色が1945年5月
ピンク色の濃いところが1945年3月10日の大空襲
それまでの爆撃目的地は軍事施設のある都市だったのですが、東京の空襲では一般市街地が爆撃目標で、市民が大勢犠牲になることは当初から明確でした。
しかも、アメリカ軍は東京のどこに燃えやすい木造住宅が多いかなども詳しく分析した地図によって爆撃目標を決めていたのです。
市民(いわゆる非戦闘員)が犠牲になっても、1日も早く戦争を終わらせるためには正当である、というのがアメリカ軍の基本姿勢でした。










以上が記事の内容(一部割愛)ですが、原爆投下の場合にも同じ「正当化」が行われています。「戦争が1日でも早く終わるように。」
これは明らかに詭弁(屁理屈)ですね。
本当の人道的立場からは「終戦が1日遅れても、一般市民からは犠牲を出さない」というのが正しいと思います。
もちろん、一般市民の犠牲者が無ければ、いくら戦争しても宜しい、などということは絶対ありません。
東京大空襲に関するWikipedia記事は、ドイツ語版の方が英語版よりも詳しく、写真もドイツ語版の方が多いです。
東京大空襲・戦災資料センターHP
東京大空襲と同じような被害を受けたのがドレスデンです。ドレスデン空爆は1944年秋から始まりましたが、1945年2月13日から15日の空爆が最大規模で、つまりドレスデン大空襲です。
この場合は、既に戦局は明白で、連合軍側でも反対者がいたのですが、第二次大戦末期は既に冷戦時代の前夜で、ソ連軍に占領されそうな重要都市は破壊しておこうという下心があったようです。
しかしドイツ全域の重要都市は殆ど漏れなく大規模な空爆を受けています。
Wikipedia:ドレスデン爆撃
現在のドレスデン中心部は、バロック時代の景観を取り戻しています

















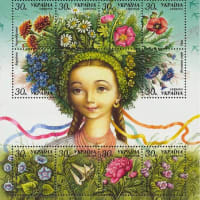
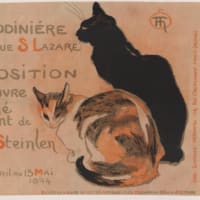


話すのも辛かったのでしょうね、きっと!
今、戦後70年を節目に過去の事実を体験者が立ち上がり、当時の状況やフイルムを通して
私達は破壊される街や廃墟後を見て、改めて考えさせられています
この事実を教訓とし、未来に向かっている筈なのに、戦いや理解出来ない事件が次々勃発、困惑しています
何が正しくて何が当たり前で、何が常識なんだろ~
メジャーとなるものは、見当たらないし、
ただ、言える事は、世の中を良く観察し、人の話を良く聞き、自分なりに、一人一人の考え方をしっかりそれぞれが持つ、答えは出ないかもしれないけど、
次元がもしかしたら異なり、そんな甘い事を言っている場合ではないのかもしれないし、
自然災害の恐ろしさにおびえながら戦争なんて、全く考えられないと思うのですが、答えは一つではない事は確かですね
何が正しくて、何が当たり前で何が常識なのか、世界中にそれぞれ物差しがあったら、、、分かり易いでしょうね
しかし、戦争を始める理由は大抵、詭弁(屁理屈)だと想います。
人道的立場からは戦争を避けて平和的に解決するべきだからです。
でも、経済的利害や覇権争いが背景にあって、そのためには詭弁でも何でも無理に理屈をつけることになります。
更に、戦争を始めた方が悪いから、それを受けた側は何をしてもいい、ということにはなりません。
恐ろしい体験を語り伝えるのも大変なことですね。
この新聞記事の方も、何十年も経ってから漸く話せるようになったらしいです。
昨日ラジオで聴いた体験談の人は、アウシュビッツ強制収容所の生き残りで今90才。漸く1997年から体験を語るようになったということでした。
人道主義の「物差し」は全人類共通だと想います。