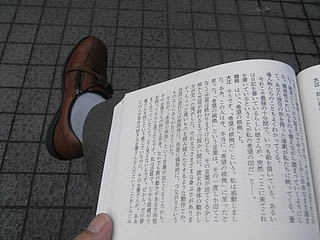9時、起床。朝食は炒飯。午後、授業の準備を1つ済ませてから、散歩に出る。「鈴文」で昼食(とんかつ定食)をとり、有隣堂で『将棋世界』7月号と『群像』7月号を購入してから、「ルノアール」へ食後の珈琲を飲みに行く(読書主体のときは「ルノアール」、珈琲主体のときは「テラス・ドルチェ」というのが最近のパターンだ)。『将棋世界』は「百年に一度の大逆転」と騒がれた名人戦第三局の観戦記(橋本崇載七段)を真っ先に読んだ。
「21時を回った。8五玉と上がった局面で、ずっと覇気のない表情だった羽生が、突然「んん?!」と大きな声を上げた。何かに気付いたようだ。そして先手玉の周りを厳しい表情で睨み、口を真一文字に結んで8二歩と打った。力のこもった手つきだった。森内、同桂成。成桂を進める手つきがかすかに震えた。」
「森内は苦悶の表情を浮かべている。59秒まで読まれて、盤上で手が泳ぐように7六金と上がった。そして、指してすぐに窓の方を向き、どこか一点をキッと睨みつけた。普段の温和な森内からは想像もできない。それはまさに、鬼の形相といった感じだった。鳥肌が立った。」
「歴史的大逆転を目の前にして、控え室ではみな興奮状態である。さっきまで森内勝ちの原稿を用意していた新聞記者も、事態の急変に困惑している。誰かが、はっきりした口調で言った。「間違いありません。100年に一度の大逆転です。羽生勝ちです。」」
勝負事(賭け事ではなく)の醍醐味は、自分の決断する一手一手が勝負に直結するところにある。やり直しはきかない。言い訳もきかない。日常生活のあいまいさとはまるで違う別の世界がそこにある。それはある意味、とても充実した、しびれるような、生の瞬間である。私は将棋を指すことはもちろん好きだが、少年時代から夢見ていることは、名人戦の観戦記を書くことである。昔は名人戦の観戦記は作家に依頼していた。それが観戦記者(新聞社の社員)が書くようになり、いまは、今回の観戦記がそうであるように、プロ棋士が書くことが多くなった。同じプロ棋士が書く方が技術的なこともよくわかるし、棋士の心理もわかるということなのであろう。たしかにそう思うが、文章がものたりない。目に見えること(指し手や仕草や表情)が中心で、それを追って書いているだけのような気がするのだ。たしかに緊迫感は漂っているが、描写が紋切り型なのだ。無声映画の弁士の語りを聞いているような気がする。調子はいいが、深みに乏しい。弁士はそれでもかまわないが、観戦記、それも棋界の頂点を決める名人戦の観戦記は、もっと上質の文章で味わいたい。棋士でそうした文章が書けるのは、島朗九段と先崎学八段の二人だけだ。
「ルノアール」を出て、ジムへ。1時間のウォーキング&ランニングでオムライス一皿分のカロリー(500数十キロカロリー)を消費。ジムの後、ちょうどいい気候だったので、アロマスケアビルの前の公園のベンチで『群像』を読む。今日は区民ホールで氷川きよしのショーがあったようで、公園には中高年の女性たちの姿が目立った。『群像』7月号を購入したのは、大澤真幸と松浦寿輝の対談「他者なき時代の自由」を読みたかったからなのだが、目次を見たら、大江健三郎と岡田利規の対談「あらゆる場所に目があるように書く」が載っていたので、まずそちらから読むことにした。昨夜、岡田の「三月の5日間」をDVDで観たばかりだが、大江が岡田の最新作「フリータイム」を観た感想を述べているのを読んで、これはそのまま「三月の5日間」を観た自分の感想と一緒だと思った。
「私は初めてあなたの芝居を見て、本当に面白く楽しみ、かつ感銘しました。最初は、私が考えてきた演劇のある定型、方向性がどんどん壊されていって、観客も自由になっていくし、俳優さんたちも自由になっていく。なかほどで「ここで第一部が終わります」と俳優さんがいわれて、やはり同じ仕方で第二部が始まる。そのあたりから、こういう自由な舞台と、自由な観客としての自分を初めて経験しているという気持ちで、すっかり新しい気持ちになってしまいました。」(156頁)
大江健三郎に先に言われてしまうと、後から感想を語りにくいじゃないか。また別の機会にしよう。
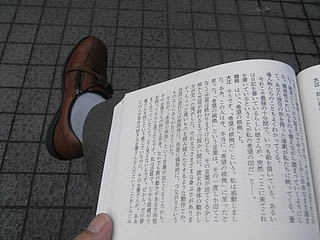
「21時を回った。8五玉と上がった局面で、ずっと覇気のない表情だった羽生が、突然「んん?!」と大きな声を上げた。何かに気付いたようだ。そして先手玉の周りを厳しい表情で睨み、口を真一文字に結んで8二歩と打った。力のこもった手つきだった。森内、同桂成。成桂を進める手つきがかすかに震えた。」
「森内は苦悶の表情を浮かべている。59秒まで読まれて、盤上で手が泳ぐように7六金と上がった。そして、指してすぐに窓の方を向き、どこか一点をキッと睨みつけた。普段の温和な森内からは想像もできない。それはまさに、鬼の形相といった感じだった。鳥肌が立った。」
「歴史的大逆転を目の前にして、控え室ではみな興奮状態である。さっきまで森内勝ちの原稿を用意していた新聞記者も、事態の急変に困惑している。誰かが、はっきりした口調で言った。「間違いありません。100年に一度の大逆転です。羽生勝ちです。」」
勝負事(賭け事ではなく)の醍醐味は、自分の決断する一手一手が勝負に直結するところにある。やり直しはきかない。言い訳もきかない。日常生活のあいまいさとはまるで違う別の世界がそこにある。それはある意味、とても充実した、しびれるような、生の瞬間である。私は将棋を指すことはもちろん好きだが、少年時代から夢見ていることは、名人戦の観戦記を書くことである。昔は名人戦の観戦記は作家に依頼していた。それが観戦記者(新聞社の社員)が書くようになり、いまは、今回の観戦記がそうであるように、プロ棋士が書くことが多くなった。同じプロ棋士が書く方が技術的なこともよくわかるし、棋士の心理もわかるということなのであろう。たしかにそう思うが、文章がものたりない。目に見えること(指し手や仕草や表情)が中心で、それを追って書いているだけのような気がするのだ。たしかに緊迫感は漂っているが、描写が紋切り型なのだ。無声映画の弁士の語りを聞いているような気がする。調子はいいが、深みに乏しい。弁士はそれでもかまわないが、観戦記、それも棋界の頂点を決める名人戦の観戦記は、もっと上質の文章で味わいたい。棋士でそうした文章が書けるのは、島朗九段と先崎学八段の二人だけだ。
「ルノアール」を出て、ジムへ。1時間のウォーキング&ランニングでオムライス一皿分のカロリー(500数十キロカロリー)を消費。ジムの後、ちょうどいい気候だったので、アロマスケアビルの前の公園のベンチで『群像』を読む。今日は区民ホールで氷川きよしのショーがあったようで、公園には中高年の女性たちの姿が目立った。『群像』7月号を購入したのは、大澤真幸と松浦寿輝の対談「他者なき時代の自由」を読みたかったからなのだが、目次を見たら、大江健三郎と岡田利規の対談「あらゆる場所に目があるように書く」が載っていたので、まずそちらから読むことにした。昨夜、岡田の「三月の5日間」をDVDで観たばかりだが、大江が岡田の最新作「フリータイム」を観た感想を述べているのを読んで、これはそのまま「三月の5日間」を観た自分の感想と一緒だと思った。
「私は初めてあなたの芝居を見て、本当に面白く楽しみ、かつ感銘しました。最初は、私が考えてきた演劇のある定型、方向性がどんどん壊されていって、観客も自由になっていくし、俳優さんたちも自由になっていく。なかほどで「ここで第一部が終わります」と俳優さんがいわれて、やはり同じ仕方で第二部が始まる。そのあたりから、こういう自由な舞台と、自由な観客としての自分を初めて経験しているという気持ちで、すっかり新しい気持ちになってしまいました。」(156頁)
大江健三郎に先に言われてしまうと、後から感想を語りにくいじゃないか。また別の機会にしよう。