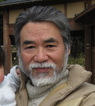森永から回答が来ましたのでアップします。
**************
2008年3月4日
特定非営利活動法人
たまごママネット御中
森永乳業株式会社
栄養食品事業部
謹啓 早春の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、大変遅くなりましたが、平成20年2月2日付けの質問書でいただきました乳児用調整乳の安全な授乳に関する質問につきまして、弊社の見解を下記の通り回答させていただきます。
謹白
質問1、どのような菌が混入しているのでしょうか?病原微生物が開封前からいるという報告もありますがお答えください。
(回答)
乳児用調製粉乳は、最新の衛生基準に沿って製造された製品であっても、無菌の製品ではありません。2004年、2006年に開催されたFAO/WHO専門家会議は乳児用調整乳中における懸念される病原菌としてE.sakazakii等を報告しました。
質問2、その菌はどのような症状を引きおこすのでしょうか?感染した乳児の死亡率はどれくらいでしょうか?
(回答)
FAO/WHOのQ&Aによると、E.sakazakiiは乳幼児の髄膜炎や腸炎の発生に関係しており、特に極低出生体重児、早産児、免疫障害児への感染リスクが高く、感染した乳幼児の20~50%が死亡したという報告もあるとのことです。
日本での感染例は、1例とされています。
質問3、病原微生物が調整乳に混入する経路はどのようなものですか?
(回答)
病原性微生物の汚染要因としては、
製品由来の内的要因と使用時での汚染による外的要因が考えられます。
内的要因は、製造工程での汚染で、原料からの混入や殺菌後の製造環境からの汚染が考えられます。
外的要因は、調乳や授乳の際の汚染された器具(スプーン。ほ乳瓶、手の洗浄不足)や調乳や授乳の環境からの汚染が考えられます。
このため当社では、法的に規定された衛生基準よりも厳しい条件の下で製造を行うとともに、製造工程における衛生管理の徹底とモニタリングを実施し、安全性の高い製品提供に努めております。また、外的要因については、回答4の通り対応しております。
質問4、これまで消費者に菌が混入していることを説明されましたか。お答えください。
(回答)
感染リスクの高い乳児である低出生体重児を対象とする製品の缶表示において、2006年より①本製品が徹底した衛生管理の下で製造されているが無菌製品でないこと、②調乳児に最近が混入する可能性があること、③調乳時に高温(80℃以上)のお湯の使用、または調乳後に80℃以上に加熱してから使用すること、の記載をして注意喚起しております。
その他の乳児用調整乳製品に関しましては、2007年のWHOガイドライン*の内容を勘案して、昨年から調乳時の70℃以上の熱湯の使用、もしくは調乳後の70℃以上への加熱、及び作りおきや飲み残しの使用を行わないよう、注意表示を記載しております。
*WHOガイドライン『乳児用調整粉乳の安全な調乳、保存および取り扱いに関するガイドライン』
質問5、乳幼児粉ミルクに使用されている添加物は?
(回答)
添加物は主にビタミン、ミネラルなどの栄養成分の強化剤です。その使用に当たっては、母乳成分、乳児用調製粉乳の表示基準及びCodex規格等に基づき製品組成を決定し、その種類及び量について厚生労働大臣に届け出て、使用の承認をいただいております。また、使用している添加物は、一括名等を使用せず全て製品に表示しております。
質問6、乳幼児用調製粉乳には、潜在的な危険性があるので安易な使用は乳幼児の健康を害する可能性がある」との表示をすることを勧告していますが御社はどのように表示されるのでしょうか。お答えください。
(回答)
「赤ちゃんにとって健康なお母さんの母乳が最良であること」、「母乳が足りない赤ちゃんに使用できること」及び「必要に応じて医師、管理栄養士などに相談して使用していただくこと」のお願いを明記しております。また、昨年から、調乳時の70℃以上の熱湯の使用、もしくは調乳後の70℃以上への加熱、及び作りおきや飲み残しの使用を行わないよう、注意表示を記載しております。
質問7、「乳業メーカーに対して調整乳を滅菌する開発を指導すること」という勧告があります。どのような開発をされますか?
(回答)
開発について検討を開始しておりますが、多くの課題があります。
質問8
母乳代用品の販売流通に関する国際規準の要約
International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes
1981年 WHO総会で成立、1994年 日本政府が賛成
1 消費者一般に対して、母乳代用品の宣伝・広告をしてはいけない。
とありますが、雑誌等の広告を止める意思はおありですか。お答えください。
(回答)
現在弊社では、テレビ、ラジオ等による不特定多数を対象とした広告は行っていません
また、今後も行わない方針です。育児雑誌に関しては、育児中の読者の方への必要な情報を掲載しております。
なお、雑誌などの広告については一定範囲の消費者に対する、弊社製品の適切な選択と使用について情報提供する手段として捉えておりますことを、ご理解頂きますようお願いいたします。
以上
*******************
テレビ広告は、各社の申し合わせで、TV広告は行わない等の自主基準をおこなっています。
雑誌の広告によって惑わされる人が多い。WHOは宣伝や広告をしてはならないとしている。
我が国では野放しである。
**************
2008年3月4日
特定非営利活動法人
たまごママネット御中
森永乳業株式会社
栄養食品事業部
謹啓 早春の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、大変遅くなりましたが、平成20年2月2日付けの質問書でいただきました乳児用調整乳の安全な授乳に関する質問につきまして、弊社の見解を下記の通り回答させていただきます。
謹白
質問1、どのような菌が混入しているのでしょうか?病原微生物が開封前からいるという報告もありますがお答えください。
(回答)
乳児用調製粉乳は、最新の衛生基準に沿って製造された製品であっても、無菌の製品ではありません。2004年、2006年に開催されたFAO/WHO専門家会議は乳児用調整乳中における懸念される病原菌としてE.sakazakii等を報告しました。
質問2、その菌はどのような症状を引きおこすのでしょうか?感染した乳児の死亡率はどれくらいでしょうか?
(回答)
FAO/WHOのQ&Aによると、E.sakazakiiは乳幼児の髄膜炎や腸炎の発生に関係しており、特に極低出生体重児、早産児、免疫障害児への感染リスクが高く、感染した乳幼児の20~50%が死亡したという報告もあるとのことです。
日本での感染例は、1例とされています。
質問3、病原微生物が調整乳に混入する経路はどのようなものですか?
(回答)
病原性微生物の汚染要因としては、
製品由来の内的要因と使用時での汚染による外的要因が考えられます。
内的要因は、製造工程での汚染で、原料からの混入や殺菌後の製造環境からの汚染が考えられます。
外的要因は、調乳や授乳の際の汚染された器具(スプーン。ほ乳瓶、手の洗浄不足)や調乳や授乳の環境からの汚染が考えられます。
このため当社では、法的に規定された衛生基準よりも厳しい条件の下で製造を行うとともに、製造工程における衛生管理の徹底とモニタリングを実施し、安全性の高い製品提供に努めております。また、外的要因については、回答4の通り対応しております。
質問4、これまで消費者に菌が混入していることを説明されましたか。お答えください。
(回答)
感染リスクの高い乳児である低出生体重児を対象とする製品の缶表示において、2006年より①本製品が徹底した衛生管理の下で製造されているが無菌製品でないこと、②調乳児に最近が混入する可能性があること、③調乳時に高温(80℃以上)のお湯の使用、または調乳後に80℃以上に加熱してから使用すること、の記載をして注意喚起しております。
その他の乳児用調整乳製品に関しましては、2007年のWHOガイドライン*の内容を勘案して、昨年から調乳時の70℃以上の熱湯の使用、もしくは調乳後の70℃以上への加熱、及び作りおきや飲み残しの使用を行わないよう、注意表示を記載しております。
*WHOガイドライン『乳児用調整粉乳の安全な調乳、保存および取り扱いに関するガイドライン』
質問5、乳幼児粉ミルクに使用されている添加物は?
(回答)
添加物は主にビタミン、ミネラルなどの栄養成分の強化剤です。その使用に当たっては、母乳成分、乳児用調製粉乳の表示基準及びCodex規格等に基づき製品組成を決定し、その種類及び量について厚生労働大臣に届け出て、使用の承認をいただいております。また、使用している添加物は、一括名等を使用せず全て製品に表示しております。
質問6、乳幼児用調製粉乳には、潜在的な危険性があるので安易な使用は乳幼児の健康を害する可能性がある」との表示をすることを勧告していますが御社はどのように表示されるのでしょうか。お答えください。
(回答)
「赤ちゃんにとって健康なお母さんの母乳が最良であること」、「母乳が足りない赤ちゃんに使用できること」及び「必要に応じて医師、管理栄養士などに相談して使用していただくこと」のお願いを明記しております。また、昨年から、調乳時の70℃以上の熱湯の使用、もしくは調乳後の70℃以上への加熱、及び作りおきや飲み残しの使用を行わないよう、注意表示を記載しております。
質問7、「乳業メーカーに対して調整乳を滅菌する開発を指導すること」という勧告があります。どのような開発をされますか?
(回答)
開発について検討を開始しておりますが、多くの課題があります。
質問8
母乳代用品の販売流通に関する国際規準の要約
International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes
1981年 WHO総会で成立、1994年 日本政府が賛成
1 消費者一般に対して、母乳代用品の宣伝・広告をしてはいけない。
とありますが、雑誌等の広告を止める意思はおありですか。お答えください。
(回答)
現在弊社では、テレビ、ラジオ等による不特定多数を対象とした広告は行っていません
また、今後も行わない方針です。育児雑誌に関しては、育児中の読者の方への必要な情報を掲載しております。
なお、雑誌などの広告については一定範囲の消費者に対する、弊社製品の適切な選択と使用について情報提供する手段として捉えておりますことを、ご理解頂きますようお願いいたします。
以上
*******************
テレビ広告は、各社の申し合わせで、TV広告は行わない等の自主基準をおこなっています。
雑誌の広告によって惑わされる人が多い。WHOは宣伝や広告をしてはならないとしている。
我が国では野放しである。