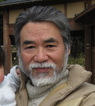今回はサイレントベビーについて考えていただきたいと思いました。
敬愛する、岡村産婦人科の岡村博行先生が書かれた文章を引用させていただきます。
素晴らしい文章ですのでお読みください。
今日の花はゼフィランスです。

清楚で美しい花ですね。

*************
サイレントベビーと引きこもりっ子
それは決して病気ではありません。
誰にでもすぐ分かるというような何か特別の変化でもありません。
しかし確かに今の日本の赤ちゃんに何かが起きているのです。
その赤ちゃんが成人した後のパーソナリティーにまで影響を及ぼしかねない何かなのです。そして放置しておくと情緒は未成熟のまま育ち、周囲の人とコミュニケーションの取れない大人に育ってしまうのではないかと憂慮されています。
もうお気づきと思いますが、それはサイレントベビーの出現です。命名者の柳沢博士によると「静かで表情に乏しく余り泣かず、目の輝きにも強く母親を求めるものに欠けている」のような赤ちゃんですが、その特徴として、国立京都病院の石田勝正博士は検診のとき、母乳で育てられている赤ちゃんは診察者の目を追うが、サイレントベビーは人の顔を見ないで、天井の蛍光燈を見つめると、実に的確に両者の見分けかたを指摘しておられます。
このような赤ちゃんの出現は、その背景に最近の育児文化に一因がある。つまり省エネ育児に代表されるような育児分化や赤ちゃんを取り巻く環境の変化によって、母と子の触れ合いや絆作りが無意識の内に希薄になってしまった事が大きな原因と考えられています。
かつての我が国はおっぱい天国であり、赤ちゃんはスキンシップ過剰ともいえるほど情緒たっぷりに育てられていました。
ところが戦後、我が国古来の川の字育児分化は古臭いもの、子どもの自立を妨げるものとして捨て去られ、代わって超合理主義的西洋式育児法・・・赤ちゃんのときから大人のルールに従わせる事をモットーとし、例えば赤ちゃんにも個室を与え、ミルクも時間を決めて正確に、泣いても決して抱っこしない・・・のようなしつけを重視する育児法にとって代わられました。その結果はどうでしょう。日米の母子関係をその挙動観察から比較した報告があります。
赤ちゃんがまだ母親と一緒に寝ていた1960年と、一人寝をさせるようになった1980年の日本のお母さんを比べてみますと、80年のお母さんは話し掛けは増えたものの、抱っことか頬ずりのような肌と肌との触れ合いが著しく減少しています。アメリカのお母さんと比べても三分の一に減少しています。更に最近は母と子の触れ合いや相互作用の機会をより少なくする安易な哺乳瓶保育、うつぶせ寝、紙おむつの普及がそれに拍車をかけています。加えて現代の我が国に広く行き渡っている「努力」を卑しむ風潮、そしてその風潮の育児への影響がもたらす思わぬ落とし穴に、多くの人はまだ気づいていないようです。
このような現実を目の前にして、母乳育児10ヶ条が我が国に求めているものは何でしょうか。私は今我が国に求められているものは、「今何故母乳か」というより、むしろ「今何故授乳か」という方が理解し易い、つまり母乳という物質より、授乳という行為其のものの持つ意義こそが今我が国に求められているのではないでしょうか。五感を総動員しての授乳行為によってもたらされる母子相互作用の様々とその仕組みについては、ここで改めて述べる要はないと思いますが、この乳房を介してのお互いの心と心の交流こそがサイレントベビーに対する最善の予防法であり、最良の治療法でもあり、最近問題となっている”引きこもりっ子”の予防に通じる道でもあるのです。そして更には肌と肌との触れ合いを通じて得られる母と子の一体感こそが、その後のスムースな自立の道に通じるものでもあるのです。
”モンタギュー曰く”?Ashley Montagu はアメリカにおける一般人類学の第一人者であり、その広範な知識は文化人類学の分野をカバーするのみでなく、生理学・心理学・人類学・動物行動学のデータをもとに、身体精神学的アプローチから次のように述べています。
「人間の皮膚に触れて刺激する事は酸素や睡眠と同じように身体にとって絶対不可欠のものである。ことに、新生児から幼児期にかけて皮膚接触が不足すると、その後の行動の発達に悪い影響を及ぼすそれゆえ赤ちゃんは可能な限り抱かれるべきであり愛撫が過度になり過ぎるという心配は不要である」。
更に、「授乳による結びつきが作り出すものは、人間社会のあらゆる関係の発展のための基礎であり、母親の肌のぬくもりを通じて乳児が受容するコミュニケーションは、子どもの人生における最初の社会化の体験ともなるものである」と。
以上指摘したように、サイレントベビーの発生要因は母と子の間の絶対的な触れ合い不足が大きく拘わっており、この自然な母と子の結びつきを阻害する母子異室制は、避けねばならないというより、寧ろあってはならない早急の改善を要するシステムだということが理解されます。
さてこのようなサイレントベビーの将来が心配されていましたが、1990年代に入り、「引きこもり」とか「引きこもる若者たち」の出現が不登校児童などと共に、俄然注目を浴びるようになってきました。引きこもる若者たちに共通しているのは「人とのコミュニケーションをしたいのに、それが出来ない」と心で葛藤している事であり、更に共通して訴えるのは「人間関係がつらい、分からない、信じられない」という事だといわれます。この人と一緒に生きてゆく事。このごく当たり前の事が出来ずに悩み苦しむ若者たち。私はこの若者たちとサイレントベビーとの間に、大きな共通点があるように思われてなりません。
**************
母子分離が生み出す不幸についてお考えください。
我が子の将来を見据えた子育てをしてくださいね。
敬愛する、岡村産婦人科の岡村博行先生が書かれた文章を引用させていただきます。
素晴らしい文章ですのでお読みください。
今日の花はゼフィランスです。

清楚で美しい花ですね。

*************
サイレントベビーと引きこもりっ子
それは決して病気ではありません。
誰にでもすぐ分かるというような何か特別の変化でもありません。
しかし確かに今の日本の赤ちゃんに何かが起きているのです。
その赤ちゃんが成人した後のパーソナリティーにまで影響を及ぼしかねない何かなのです。そして放置しておくと情緒は未成熟のまま育ち、周囲の人とコミュニケーションの取れない大人に育ってしまうのではないかと憂慮されています。
もうお気づきと思いますが、それはサイレントベビーの出現です。命名者の柳沢博士によると「静かで表情に乏しく余り泣かず、目の輝きにも強く母親を求めるものに欠けている」のような赤ちゃんですが、その特徴として、国立京都病院の石田勝正博士は検診のとき、母乳で育てられている赤ちゃんは診察者の目を追うが、サイレントベビーは人の顔を見ないで、天井の蛍光燈を見つめると、実に的確に両者の見分けかたを指摘しておられます。
このような赤ちゃんの出現は、その背景に最近の育児文化に一因がある。つまり省エネ育児に代表されるような育児分化や赤ちゃんを取り巻く環境の変化によって、母と子の触れ合いや絆作りが無意識の内に希薄になってしまった事が大きな原因と考えられています。
かつての我が国はおっぱい天国であり、赤ちゃんはスキンシップ過剰ともいえるほど情緒たっぷりに育てられていました。
ところが戦後、我が国古来の川の字育児分化は古臭いもの、子どもの自立を妨げるものとして捨て去られ、代わって超合理主義的西洋式育児法・・・赤ちゃんのときから大人のルールに従わせる事をモットーとし、例えば赤ちゃんにも個室を与え、ミルクも時間を決めて正確に、泣いても決して抱っこしない・・・のようなしつけを重視する育児法にとって代わられました。その結果はどうでしょう。日米の母子関係をその挙動観察から比較した報告があります。
赤ちゃんがまだ母親と一緒に寝ていた1960年と、一人寝をさせるようになった1980年の日本のお母さんを比べてみますと、80年のお母さんは話し掛けは増えたものの、抱っことか頬ずりのような肌と肌との触れ合いが著しく減少しています。アメリカのお母さんと比べても三分の一に減少しています。更に最近は母と子の触れ合いや相互作用の機会をより少なくする安易な哺乳瓶保育、うつぶせ寝、紙おむつの普及がそれに拍車をかけています。加えて現代の我が国に広く行き渡っている「努力」を卑しむ風潮、そしてその風潮の育児への影響がもたらす思わぬ落とし穴に、多くの人はまだ気づいていないようです。
このような現実を目の前にして、母乳育児10ヶ条が我が国に求めているものは何でしょうか。私は今我が国に求められているものは、「今何故母乳か」というより、むしろ「今何故授乳か」という方が理解し易い、つまり母乳という物質より、授乳という行為其のものの持つ意義こそが今我が国に求められているのではないでしょうか。五感を総動員しての授乳行為によってもたらされる母子相互作用の様々とその仕組みについては、ここで改めて述べる要はないと思いますが、この乳房を介してのお互いの心と心の交流こそがサイレントベビーに対する最善の予防法であり、最良の治療法でもあり、最近問題となっている”引きこもりっ子”の予防に通じる道でもあるのです。そして更には肌と肌との触れ合いを通じて得られる母と子の一体感こそが、その後のスムースな自立の道に通じるものでもあるのです。
”モンタギュー曰く”?Ashley Montagu はアメリカにおける一般人類学の第一人者であり、その広範な知識は文化人類学の分野をカバーするのみでなく、生理学・心理学・人類学・動物行動学のデータをもとに、身体精神学的アプローチから次のように述べています。
「人間の皮膚に触れて刺激する事は酸素や睡眠と同じように身体にとって絶対不可欠のものである。ことに、新生児から幼児期にかけて皮膚接触が不足すると、その後の行動の発達に悪い影響を及ぼすそれゆえ赤ちゃんは可能な限り抱かれるべきであり愛撫が過度になり過ぎるという心配は不要である」。
更に、「授乳による結びつきが作り出すものは、人間社会のあらゆる関係の発展のための基礎であり、母親の肌のぬくもりを通じて乳児が受容するコミュニケーションは、子どもの人生における最初の社会化の体験ともなるものである」と。
以上指摘したように、サイレントベビーの発生要因は母と子の間の絶対的な触れ合い不足が大きく拘わっており、この自然な母と子の結びつきを阻害する母子異室制は、避けねばならないというより、寧ろあってはならない早急の改善を要するシステムだということが理解されます。
さてこのようなサイレントベビーの将来が心配されていましたが、1990年代に入り、「引きこもり」とか「引きこもる若者たち」の出現が不登校児童などと共に、俄然注目を浴びるようになってきました。引きこもる若者たちに共通しているのは「人とのコミュニケーションをしたいのに、それが出来ない」と心で葛藤している事であり、更に共通して訴えるのは「人間関係がつらい、分からない、信じられない」という事だといわれます。この人と一緒に生きてゆく事。このごく当たり前の事が出来ずに悩み苦しむ若者たち。私はこの若者たちとサイレントベビーとの間に、大きな共通点があるように思われてなりません。
**************
母子分離が生み出す不幸についてお考えください。
我が子の将来を見据えた子育てをしてくださいね。