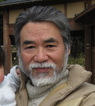このところ、食事についての質問がよくありますので今回は乳幼児の食事について書きます。
「3歳3ヶ月の娘について質問があります。1週間前に食事の際りんごがのどに詰まってから、食事を嫌がるようになりました。翌日の朝はそれなりに食べていたのですが、昼にまたりんごを 出したら怖くなったようで、何も食べたがらなくなりました。
現在はワッフルと摩り下ろしりんご、チーズは食べ てくれるので、そればかり食べさせています。
ほかのものを無理やり食べさせようとすると、大 喧嘩になります。
お菓子は今のところ与えていません。もともと肉はあまり好きではありません でしたが、それ以外は何でも食べていたのに、大好きなブロッコリーも食べなくなりました。
赤 ちゃんのころより華奢な体型で、このまま食べないとどんどんやせていきそうで心配です。
性格的に怖がりなところがあり、大きい音を怖がったりします。
どうしたらまた食べてくれるようになるでしょうか?そして、そうするためにはどんな食事を出せばよいでしょうか? 」
***************
リンゴを詰まらせてとても苦しかったのでしょうね。
それ以来、恐怖でりんごが食べられなくなってしまったのでししょうね。
怖いリンゴがまた出てきたのがショックで、恐怖が甦ってきたのです。
リンゴを見たショックのあまり他の食べ物も食べられなくなってしまったのですね。
乳幼児も成人と同じように、心を病みます。
親は、子どものこころのことについて、あまりにも無知です。
ある意味では、私たちよりも乳幼児の「こころ」の方がデリケートなこともあります。
生後間もない赤ちゃんがこころを病んで円形脱毛症になるとも言われています。
恐ろしい思いをしたものを、その記憶が消えないうちにまた与えようとすると恐怖が上塗りされて、心の中に強く残り、時に記憶の底のほうで心的外傷体験として残ってしまいます。
そうなると再度食べることが困難になりかねません。
死ぬかもしれないほど恐ろしい思いをしたりんごを目の前にして、何も食べられなくなってしまったように思います。
「怖かったね。もうりんごは食べなくてもいいよ。」と言って食べさせないでいると、しばらくして、心の傷が癒えたら食べるようになります。
最初は、リンゴはすりおろしてあげるといいです。
いきなり固形のリンゴは食べられません。
食卓は家族団らんの場で、叱られたり怒られたりする場ではありません。
楽しく食卓を囲むことがとても重要です。
叱られながらの食事は、子どもにとって「地獄の苦しみ」となります。
そのような苦しみが毎日続いたら誰でも食事が嫌になります。
言葉が出来ない乳児は、拒食で意思表示をします。
食事中に叱ったりすると、拒食することもあります。
ただし、拒食症や過食症などの食行動の異常は、食事だけの問題ではなく、親子の関係性障害による愛着障害が根底にあるといわれています。
食事を嫌がったり食べないことが続く場合には、何か問題があるはずです。
その問題を見つけることはとても重要です。
躾と称して、スプーンや箸で食べることを強要したりすると、次第にいやがることもあります。
また、口の中に何かが出来たり、のどの腫れなどの痛みがある場合もあります。
楽しい雰囲気で食事をすることはとても大切です。
対処法の一つとして効果があるのは、子どもと一緒に、食事を作ることはいいです。
自分が作ったものが食卓に並ぶと、嫌いなものでも喜んで食べてくれます。
遊びの要素もありますし、少し早いですが食育にもなるのではないでしょうか。
食べたくないのに、食べたら「褒めてあげてください。
食卓を叱ったり、子どもに恐怖を与える場にしないでください。
楽しく食事をしましょう。
こどものこころの健やかな成長のためにも、ぜひ実行してください。
「3歳3ヶ月の娘について質問があります。1週間前に食事の際りんごがのどに詰まってから、食事を嫌がるようになりました。翌日の朝はそれなりに食べていたのですが、昼にまたりんごを 出したら怖くなったようで、何も食べたがらなくなりました。
現在はワッフルと摩り下ろしりんご、チーズは食べ てくれるので、そればかり食べさせています。
ほかのものを無理やり食べさせようとすると、大 喧嘩になります。
お菓子は今のところ与えていません。もともと肉はあまり好きではありません でしたが、それ以外は何でも食べていたのに、大好きなブロッコリーも食べなくなりました。
赤 ちゃんのころより華奢な体型で、このまま食べないとどんどんやせていきそうで心配です。
性格的に怖がりなところがあり、大きい音を怖がったりします。
どうしたらまた食べてくれるようになるでしょうか?そして、そうするためにはどんな食事を出せばよいでしょうか? 」
***************
リンゴを詰まらせてとても苦しかったのでしょうね。
それ以来、恐怖でりんごが食べられなくなってしまったのでししょうね。
怖いリンゴがまた出てきたのがショックで、恐怖が甦ってきたのです。
リンゴを見たショックのあまり他の食べ物も食べられなくなってしまったのですね。
乳幼児も成人と同じように、心を病みます。
親は、子どものこころのことについて、あまりにも無知です。
ある意味では、私たちよりも乳幼児の「こころ」の方がデリケートなこともあります。
生後間もない赤ちゃんがこころを病んで円形脱毛症になるとも言われています。
恐ろしい思いをしたものを、その記憶が消えないうちにまた与えようとすると恐怖が上塗りされて、心の中に強く残り、時に記憶の底のほうで心的外傷体験として残ってしまいます。
そうなると再度食べることが困難になりかねません。
死ぬかもしれないほど恐ろしい思いをしたりんごを目の前にして、何も食べられなくなってしまったように思います。
「怖かったね。もうりんごは食べなくてもいいよ。」と言って食べさせないでいると、しばらくして、心の傷が癒えたら食べるようになります。
最初は、リンゴはすりおろしてあげるといいです。
いきなり固形のリンゴは食べられません。
食卓は家族団らんの場で、叱られたり怒られたりする場ではありません。
楽しく食卓を囲むことがとても重要です。
叱られながらの食事は、子どもにとって「地獄の苦しみ」となります。
そのような苦しみが毎日続いたら誰でも食事が嫌になります。
言葉が出来ない乳児は、拒食で意思表示をします。
食事中に叱ったりすると、拒食することもあります。
ただし、拒食症や過食症などの食行動の異常は、食事だけの問題ではなく、親子の関係性障害による愛着障害が根底にあるといわれています。
食事を嫌がったり食べないことが続く場合には、何か問題があるはずです。
その問題を見つけることはとても重要です。
躾と称して、スプーンや箸で食べることを強要したりすると、次第にいやがることもあります。
また、口の中に何かが出来たり、のどの腫れなどの痛みがある場合もあります。
楽しい雰囲気で食事をすることはとても大切です。
対処法の一つとして効果があるのは、子どもと一緒に、食事を作ることはいいです。
自分が作ったものが食卓に並ぶと、嫌いなものでも喜んで食べてくれます。
遊びの要素もありますし、少し早いですが食育にもなるのではないでしょうか。
食べたくないのに、食べたら「褒めてあげてください。
食卓を叱ったり、子どもに恐怖を与える場にしないでください。
楽しく食事をしましょう。
こどものこころの健やかな成長のためにも、ぜひ実行してください。