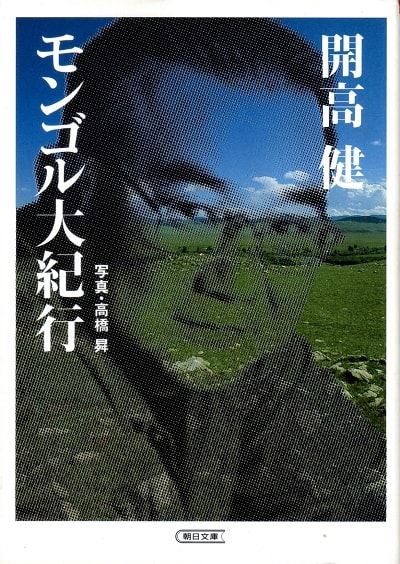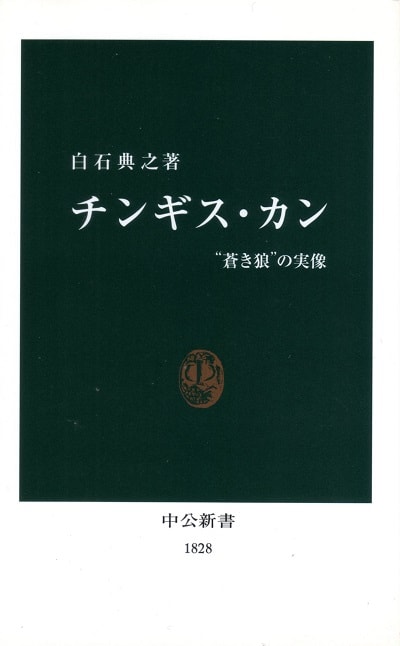科学映像館により、『チャトハンとハイ』(1994年)が配信されている。ロシアのハカス共和国における伝統音楽であり、チャトハンは箏、ハイは喉歌を意味する。
>> 『チャトハンとハイ』
私は1997年に公演「草原の吟遊詩人」を聴き、特に喉歌の不思議な響きと技巧に驚いた記憶が強く残っている。この映像は、1994年5月4・6日、カザフスタンにおいて行われたシンポジウム「チュルク諸民族の音楽」での記念コンサートを記録したものであり、来日メンバーのエヴゲーニイ・ウルグバシェフとセルゲイ・チャルコーフも含まれている。

パンフレットを探したら取ってあった

上記パンフレットより
チュルク(テュルク)とはトルコ、のちに西方の中央アジアやトルコに移動していった人々の末裔であり、モンゴルの北西に位置する共和国(ロシア内)としては、ハカス、トゥヴァ、アルタイがある。またロシア北東に位置するサハも同様である。モンゴルを含め、それぞれに喉歌や口琴が発達しており、不思議なのか、当然なのかわからないが、奇妙な思いにとらわれてしまう。喉歌は、ハカスではハイ、トゥヴァではホーメイ、モンゴルではホーミーと呼ぶ。ヴォイス・パフォーマーのサインホ・ナムチラックはトゥヴァの出身である。

上記パンフレットより
映像『チャトハンとハイ』では、次の演奏が行われている。当日のパンフを見ると、公演で演奏した曲も入っている(突然で区別できず、覚えていない)。
○エヴゲーニイ・ウルグバシェフ(チャトハン、ハイ) 「アルグィス(山と海への祈り)」
○ユーリィ・キシティエフ(ハイ、口琴) 「即興曲」
○エヴゲーニイ・ウルグバシェフ+セルゲイ・チャルコーフ(チャトハン、ハイ) 「草原(ステップ)の祭り」
○セルゲイ・チャルコーフ(ホムィス、ハイ) 「我がハカシア」
○エヴゲーニイ・ウルグバシェフ(チャトハン、ハイ) 「アルトイン・アルィグ(英雄叙事詩)」
曲の間に、ウルグバシェフがチャトハンについて面白い解説をしている。基本的に金属の7弦(昔は腸)、弦を支える柱(じ)は羊の後足のくるぶし、下部のほうがやや広め。昔は底板や共鳴口はなかった。なぜなら祖先の霊が大地に眠っているため、座って直接大地に向けて響かせるためであった。また、上記公演のパンフレットには、ハカスでチャトハンが国民楽器的な地位を占めたのは、彼らの牧畜が比較的定住型だったことも関連しているかもしれないとの考察がある(直川礼緒『ハカスの喉歌と楽器』)。
チャトハンだけでなく、ハイもシャーマニズムと密接な関係にあり、精霊に語りかけるものであった。そのハイには3種類があり、やはりウルグバシェフが実演してみせている。中音域のハイに加え、地鳴りのような低音域のチョーン・ハイ、キーンという音が鼓膜を刺激する高音域のスィグルトィプ。
この喉歌について、やはり、パンフレットに素晴らしい解説があった。
「浪曲の声のような、あるいはアメ横で聴かれるような、倍音成分を多く含んだいわゆる「喉声」による歌唱は、チュルク系の民族であるカザフやカラカルパクのものを含め、比較的広範にみられる。が、その「喉声」から、口腔の容積や形を変化させることによって意識的に特定の倍音を強調し、「メロディ」(実は音色の変化なのであるが)を紡ぎ出す技法を重要な要素とする「喉歌」は、アジア中央部を中心とした、ごく限られた地域の民族が持つのみである。
例えば、日本でも最近知られるようになってきた西モンゴルのホーミーは、倍音によるメロディの「演奏」を主眼とした、器楽的な面が強いのに対し、そのすぐ北隣のロシア側、「アジアのへそ」を自負するトゥヴァでは、倍音によるメロディーなど出ていて当然、それよりもそこに謡い込まれる歌詞の内容や即興性、その場にあっているかどうか、といった点が重視される。 (略) 特にアルタイ・ショル・ハカスでは、英雄叙事詩と深く結びついていることが特徴として挙げられる。」(直川礼緒『ハカスの喉歌と楽器』)
ここから、トゥヴァがサインホを輩出したことの背景を読み取ることができるかもしれない。また、映画『チャンドマニ~モンゴル ホーミーの源流へ~』(亀井岳、2009年)に描かれたように、モンゴルの中でも喉歌は異なり、国とスタイルは1対1ではないのだろう。私の棚には、喉歌のCDはトゥヴァのものしかない。これまで口琴には興味を持っていくつか聴いていたのだが、改めて聴いてみると、俄然、この拡がりと多様性が興味深いものとなってきた。
●参照
○亀井岳『チャンドマニ ~モンゴル ホーミーの源流へ~』
○サインホ・ナムチラックの映像
○TriO+サインホ・ナムチラック『Forgotton Streets of St. Petersburg』
○姜泰煥+サインホ・ナムチラック『Live』
○酔い醒ましには口琴
○宮良瑛子が描いたムックリを弾くアイヌ兵士
●科学映像館のおすすめ映像
○『沖縄久高島のイザイホー(第一部、第二部)』(1978年の最後のイザイホー)
○『科学の眼 ニコン』(坩堝法によるレンズ製造、ウルトラマイクロニッコール)
○『昭和初期 9.5ミリ映画』(8ミリ以前の小型映画)
○『石垣島川平のマユンガナシ』、『ビール誕生』
○ザーラ・イマーエワ『子どもの物語にあらず』(チェチェン)
○『たたら吹き』、『鋳物の技術―キュポラ熔解―』(製鉄)
○熱帯林の映像(着生植物やマングローブなど)
○川本博康『東京のカワウ 不忍池のコロニー』(カワウ)
○『花ひらく日本万国博』(大阪万博)
○アカテガニの生態を描いた短編『カニの誕生』
○『かえるの話』(ヒキガエル、アカガエル、モリアオガエル)
○『アリの世界』と『地蜂』
○『潮だまりの生物』(岩礁の観察)
○『上海の雲の上へ』(上海環球金融中心のエレベーター)
○川本博康『今こそ自由を!金大中氏らを救おう』(金大中事件、光州事件)
○『与論島の十五夜祭』