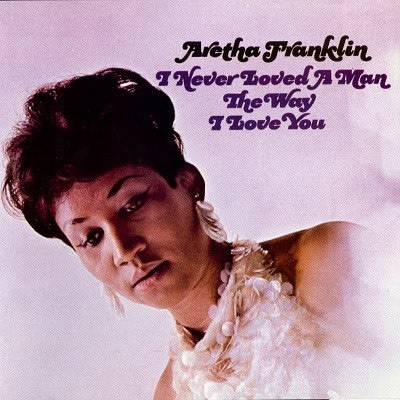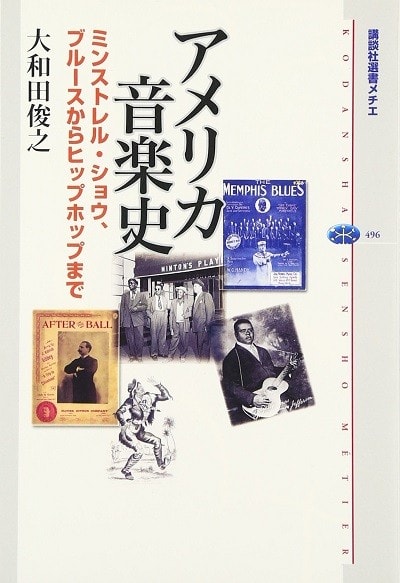リッキー・リー・ジョーンズ『Pop Pop』(Geffen、1991年)は、彼女がカバー曲ばかりを歌ったアルバムである(最近はじめて聴いた)。

Rickie Lee Jones (vo, g)
Robben Ford (g)
Michael O'Neill (g)
Charlie Haden (b)
John Leftwich (b)
Walfredo Reyes, Jr. (bongos, shakers)
Bob Sheppard (cl, ts)
Joe Henderson (ts)
Dino Saluzzi (bandoneon)
Charlie Shoemake (vib)
Steven Kindler (vln)
Michael Greiner (hurdy-gurdy)
April Gay, Arnold McCuller, David Was, Donny Gerrard, Terry Bradford (backing vo)
なんというか、凄いメンバーである。チャーリー・ヘイデン、ディノ・サルーシ、ジョー・ヘンダーソン。ボブ・シェパードはこういうところに出てくるんだな(この間、ピーター・アースキンのバンドで観た)。曲によってメンバーをうまく変えていて、個人技も楽しめる。「My One and Only Love」や「The Ballad of the Sad Young Men」でのヘイデン、サルーシ、ロベン・フォードとのカルテットとか、ジョーヘンが吹いている「Bye Bye Blackbird」とか、なかなか最高である。
もちろんリッキー・リーの鼻にかかったような歌声がまた魅力的。(なのに、ウィキペディアによれば、レナード・フェザーはひどい言い方である。かれにはわからなかったのだろう)
同じ1991年の、このコンセプトで行った2枚組ライヴ盤『Pop Pop at Guthrie Theater 1991』(JM、1991年)がある。こちらは豪華メンバーを集めることができなかったようなのだが、これはこれで普段着みたいで悪くない。

Rickie Lee Jones (vo, g, p)
Michael O'Neill (g, vo)
Sal Bernardi (accordion, g, harmonica, vo)
John Leftwich (b)
Keith Fiddmont (sax)
Ed Mann (perc, vib)