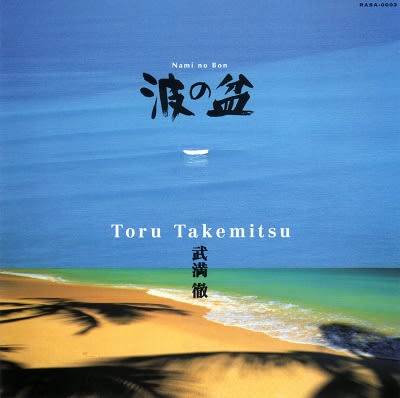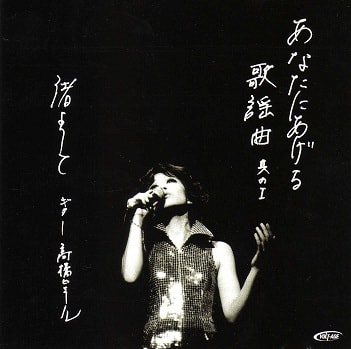スティーヴィー・ワンダー『Talking Book』(Tamla、1972年)。恥ずかしながら聴くのは初めて。
冒頭曲の「You are the Sunshine of My Life」がいい(これだけは知っている)。奇妙なイントロからはじまって、"You are the sunshine of my life / That's why I'll always be around / You are the apple of my eye / Forever you'll stay in my heart" なんて泣けてしまうな。
他の曲もラヴソングばかり、スティーヴィーの高い声は絶好調。いやカッコいい。「Tuesday Heartbreak」では、デイヴィッド・サンボーンがアルトサックスを吹くが、さすがの存在感。

なぜ思いだしたかのようにスティーヴィーを聴いたかというと、飛行機の中で、メイシー・グレイ『Talking Book』(Columbia、2012年)を聴いたからである。オリジナルから40年を経ての完全カヴァー盤。やはり、冒頭の「You are the Sunshine of My Life」に、痺れてしまった。帰国後早々にCDを買った。
こうして聴き比べてみると、それぞれ味があって良い。メイシーの方は、ハスキーというレベル以上のかすれ声。「You are ...」では可愛く唄い、スティーヴィーと違って、"... of my life" のあとに、いちいち、"yeah" と付けるのだが、これがまた可愛い。
この名曲は、どうやら数多くの歌手にカヴァーされている模様だ(>> リンク)。メイシー同様にかすれ声のアニタ・オデイのヴァージョンなんて聴いてみたいな。
「Tuesday Heartbreak」では、オリジナルと違い、トランペットが参加していた。サンボーンと比較されたのでは分が悪いし、正解か。