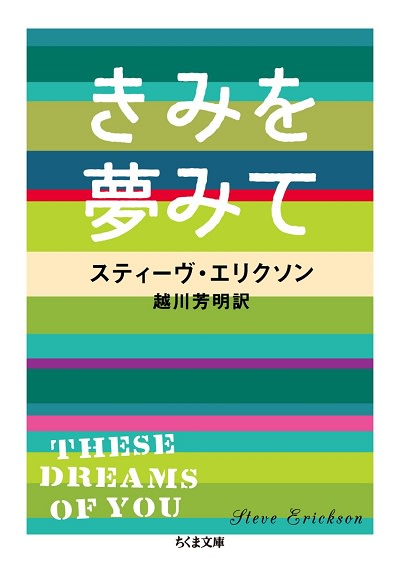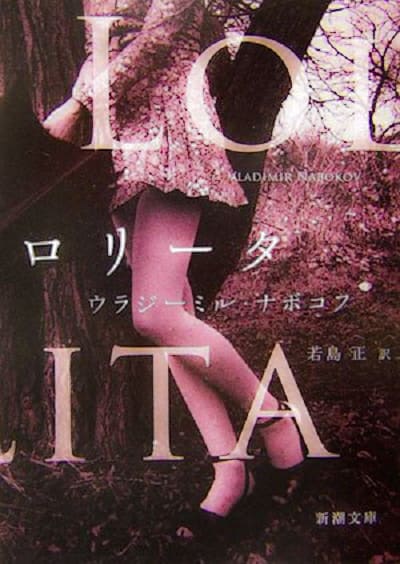ウィリアム・サローヤン『僕の名はアラム』(新潮文庫、原著1940年)を読む。

ここには、極めてヘンな大人たちばかりが登場する。妙に堂々として、妙に自信満々に我が道をゆき、それ以外の自分になることなどできるわけがない人たち。現代の日本であれば、確実に共同体から排除されているであろう人たち。
ところが、サローヤンは、主人公の子どもアラムの目を通して、かれらを実に温かく描いている。共同体から排除されるどころか、共同体を、ヘンな人の集合体としてとらえているとしか思えないのである。アラムの言動も相当におかしい。面白くて腹筋が痙攣してくる。
これを読んでいると、誰もが、ああ自分にも恥ずかしくて消してしまいたい記憶がある、などと思い出してしまうに違いない。いや、穴があったら入りたい(何が)。
サローヤンも、ここに登場する人物たちも、アルメニアからアメリカに流れ着いてきた移民の血をひいている。1915年には、オスマン帝国政府によるアルメニア人大虐殺という事件が起きているわけだが、それを直接体験していなくても、それぞれが抱えているものはいろいろな形で影を落としていたり、人格形成になんらかの影響を及ぼしたりしていたのかもしれない。この小説も、「アメリカ」も、そのことを抜きには語れない。
●参照
ホイットニー美術館の「America is Hard to See」展(アルメニア人大虐殺(1915年)によって母親を失ったアーシル・ゴーキー)
カーソン・マッカラーズ『結婚式のメンバー』(村上柴田翻訳堂)