多田隆治『気候変動を理学する 古気候学が変える地球環境観』(みすず書房、2013年)を読む。
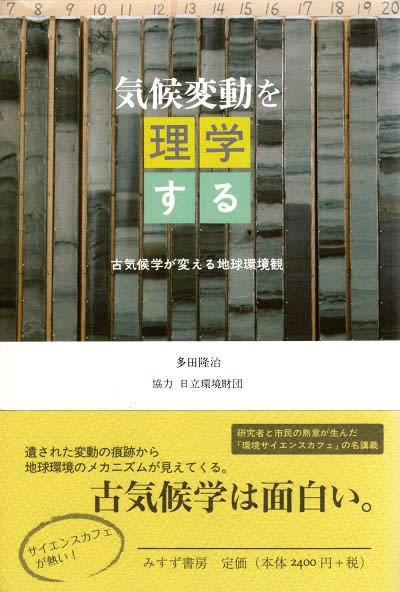
一般向けの「環境サイエンスカフェ」における講演をもとにしているだけに、みすず書房には珍しくやわらかい作り。しかし、内容は「ガチンコ」である。それも当然のこと、何しろ相手は地球なのだから。
ここで示されるのは、気候という極めて複雑なシステムが、深堀していくと実に面白いメカニズムを持っていることだ。太陽との関係、ミランコビッチ・サイクル、海という巨大なバッファーの挙動、氷期と間氷期、プレートテクトニクスと気候との関係、正と負のフィードバック。かつて、全地球凍結(スノーボール・アース)という時期もあった。
太陽活動の変動や紫外線によるオゾン量の変化についても適切に評価されている。しかし、気候変動の大きな媒体となっていたのは、やはりCO2であった。
もちろん、気候変動は一様ではありえず、局所的な異常気象を含めてシステムの変動を考えなければならない。言うまでもないことだが、ここのところ異常に暑いだの寒いだのといった理由で地球温暖化を云々するものではないということだ。そうではなく、もっとも重要な機能を担ってきた媒体たるCO2が、かつてとは比べ物にならないほどの勢いで増加しているのだから、異常を引き起こさないわけがない。これはドグマではなく、まさに「理学」的な判断である。
かたや、温暖化は原子力ロビーの陰謀であるとか、氷が溶けても海面上昇は起こらないだとか、森林保全を行ってもCO2は減らないだとか、そのような陰謀論や言いがかりとでもいうべき言説に左右される日本社会の現状は情けない限りだ(テレビに出る人のいいおじさん風の「学者」や、「巨悪」を攻撃してきた「評論家」が言うことだからといって、鵜呑みにしてはならない)。
「・・・問題を極端に単純化して、断片的観察を拡大解釈して巧みに二者択一の問題にすり替えるような議論です。政治や巨額の研究費などが絡むと、こうしたエセ科学的議論が出てきて人心を惑わせます。そして、こうしたエセ科学が人類の地球環境問題への対応を大きく誤らせる危険性さえ含んでいるのです。これからの時代は、一般市民も、こうしたエセ科学的議論を見分ける目を養う必要があると私は考えています」
米国では様相が異なり、長年、温暖化に対する懐疑論が巣食っている。たとえば、それを告発するノーム・チョムスキーのテキストを読み、まずはそれらの言説の相対化を図ってみるべきだろう。
下らぬ陰謀論などは置いておくとして、本当に面白い良書。大推薦。
●参照
○小嶋稔+是永淳+チン-ズウ・イン『地球進化概論』
○米本昌平『地球変動のポリティクス 温暖化という脅威』
○ノーム・チョムスキー+ラレイ・ポーク『Nuclear War and Environmental Catastrophe』
○ダニエル・ヤーギン『探求』
○吉田文和『グリーン・エコノミー』
○『グリーン資本主義』、『グリーン・ニューディール』
○自著
○『カーボン・ラッシュ』
○『カーター大統領の“ソーラーパネル”を追って』 30年以上前の「選ばれなかった道」
○粟屋かよ子『破局 人類は生き残れるか』




















