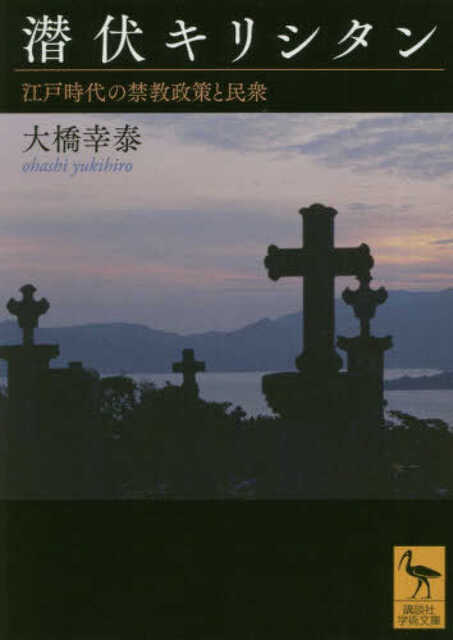
五島へ行くついでに『潜伏キリシタン:江戸時代の禁教政策と民衆』を読み始めた。まだ途中なので結論めいたことは言えないが、今のところ一番興味を引くのは、潜伏キリシタン自体より江戸幕府や諸藩による統制のあり方である。
一向一揆との戦いや島原の乱を経て、江戸幕府が厳しい宗教統制を敷いたことはよく知られている。まず、生まれた子供はどこの寺に所属しているかを「宗門人別改帳」というものに記載された。これは実質戸籍のような役割を果たし、そこに載っていない者たちは「無宿人」として不利益を被るなどでメリットがあったが、こうして言わば「自動登録」される形で江戸時代の人々はどこかの寺(宗派)に所属させられたわけである(いわゆる寺檀制度)。このようにして、実質仏教は「国教」に祭り上げられたような形となっていた。
ただ、そのことは仏教が特権的に何でも許された、という話ではもちろんない。ローマ帝国の「ミラノ勅令」によるキリスト教公認を踏まえた諸々の公会議(=正当・異端を決める必要に迫られる)ではないが、日蓮宗の不受不施派のように、幕府にとってコントロールから逸脱していると思われた宗派は仏教であろうが弾圧されたのである(まあ過去の一向一揆を思えばそれはそうなるだろう、という話だが)。
こうして言わばオフィシャルに認められた宗派のみ人々は所属できたわけだが、私があまり認識できていなかったのは、こういった統制の中に、仏僧でない人=俗人が仏の有難みを説くといった行為までも、「逸脱」として警戒された事例が複数確認されることである。というかむしろ、江戸時代の宗教統制は(島原の乱以降だと)切支丹として認定・弾圧される例はほぼなく、前述のような行為が「異宗」の兆候として報告・吟味された事例が多い点が注目に値する(実際のところ「普通とちょっと違うことをやってる」ぐらいの感じなのか、それとも新たな宗教運動の芽吹きと呼べるレベルだったのかは史料からはよくわからない)。
「いや教団の正規職員じゃない人間が勝手に仏法を語っているわけだから、尋問されてもまあわからなくはないのでは?」とか「まさにそういう草の根の活動から分派していったりするわけだから、そこを注視するのは間違っていない」といった意見も出てくるだろう。
私もそれを不自然とか異常だと言うつもりはない。ただ、江戸幕府による統制が思いのほか私的な領域にも入り込んでいて、それは民衆の宗教的情熱をあくまで決められたフォーマットの中に限定しようとするものとして、言い換えれば既存の教団とその言い分に従ってその外では活動しないことが、「出る杭」にならず平穏に暮らせる条件として意識されていたのだとすると、近世における仏教「国教化」とそこへの自動登録という仕組みは自分が想定していた以上にルート化されていたようだ(ちなみにこの「出る杭」にまつわる構造は、コロナ禍における「自粛警察」のように現代でさえ存続していることに驚かされる)。とするなら、江戸時代の宗教政策が(善悪はさておき)民衆の宗教的帰属意識を形骸化していったという解釈は、時間の経過で漸進的に進んでいったというより、むしろ幕府・諸藩による積極的な介入・監視によってある種必然的に生じたものとみなすことができるのではないか。
まあとはいえ、富士講や伊勢詣を始めとして宗教に根差した行為そのものはそこかしこに見られる点には注意を要する。ここで限定的に指摘できるのは、「仏教教団への帰属意識の希薄化」である(この他、修験などに対してどういう対応を取っていたのかなども並行して見ていく必要がありそうだ)。
というわけで、日本人の「無宗教」を考える場合にはそれを超歴史的にとらえるのではなく時間の経過による変化の観察が重要だと度々述べてきたが、この「近世における日本版デノミネーション」と宗教的帰属意識の希薄化についてはやはり重要な問題として分析していく必要がありそうだ(同じ近世という観点では、ヨーロッパにおけるナントの王令やウェストファリア条約などと比較してもおもしろい)。
というのも、こういった土台の上に、幕末からの近代化の波が訪れ、明治政府による神仏分離とその意を受けたハレーションとしての廃仏毀釈(地域性が大きい点に注意)、仏教の梯子外しと神道の特権化などが行われていく事態を見ていけば、また違った解釈も可能ではないかと思うからである(まあ帰属意識の観点で言えば、世代交代に加え仏教の哲学化・道徳化が大きな影響を与えたのではないかと個人的には思っている)。
以上、「日本における宗教的行為と宗教的帰属意識の分離の背景」を考えるにあたって、江戸時代の宗教政策とそれによる民衆の意識の変化に改めて注目していきたいと思った次第。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます