都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
六輝(ろっき)ともいう。暦日の注。先勝(せんしょう)、友引(ともびき)、先負(せんぷ)、仏滅(ぶつめつ)、大安(たいあん)、赤口(しゃっく)のこと。
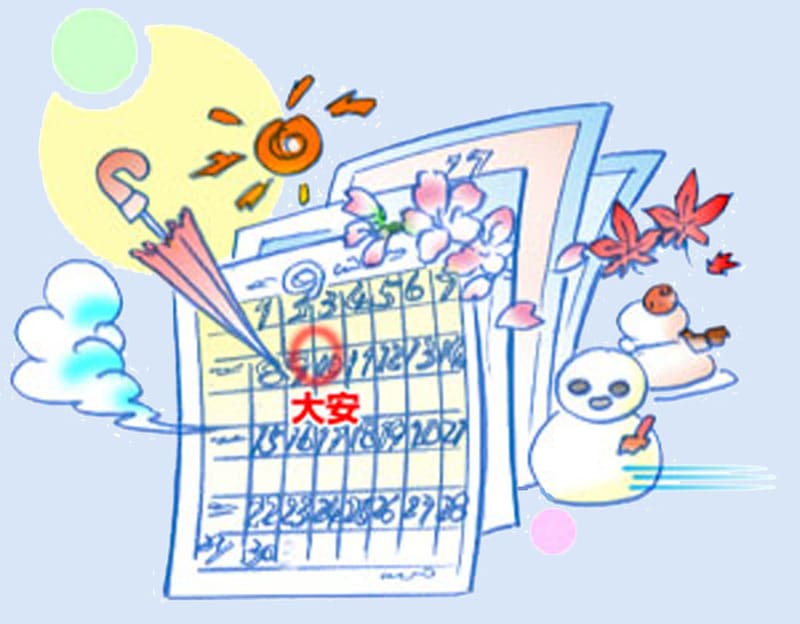 14世紀に中国から伝えられた当時は、大安、留連(りゅうれん)、速喜(そくき)、赤口、将吉(しょうきつ)、空亡(くうぼう)といったが、その後、名称、順序ともに幾度か変わり、いまの形に落ち着いたのは天保(てんぽう)(1830年~1844年)のころという。
14世紀に中国から伝えられた当時は、大安、留連(りゅうれん)、速喜(そくき)、赤口、将吉(しょうきつ)、空亡(くうぼう)といったが、その後、名称、順序ともに幾度か変わり、いまの形に落ち着いたのは天保(てんぽう)(1830年~1844年)のころという。
六曜は中国の六壬時課(りくじんじか)と呼ばれる時刻占いの一種でした。これは一日を12刻に分け、ある日の最初の一刻を大安、次 の一刻を留連、次を速喜、次を赤口、次を小吉、最後を空亡とするもので、その次の日は、第一刻を留連から始めるというものです。この時刻の占いがわが国に伝わり、日の占いに変化したもので、旧暦の朔日ごとに繰方が変わる。
の一刻を留連、次を速喜、次を赤口、次を小吉、最後を空亡とするもので、その次の日は、第一刻を留連から始めるというものです。この時刻の占いがわが国に伝わり、日の占いに変化したもので、旧暦の朔日ごとに繰方が変わる。
六輝の方は、明治以後現在もなじみ深い「七曜」(月火・・土日)が有名になったので、間違わないように名前を変えたという感じで、明治以前の暦には記載されていない比較的歴史の浅い暦注である。
 六曜(ろくよう)は、日本では、暦の中でも有名な暦注の一つで、一般のカレンダーや手帳にも記載されている。今日の日本においても影響力が強く、「結婚式は大安がよい」「葬式は友引を避ける」など、主に冠婚葬祭などの儀式と結びついて使用されている。
六曜(ろくよう)は、日本では、暦の中でも有名な暦注の一つで、一般のカレンダーや手帳にも記載されている。今日の日本においても影響力が強く、「結婚式は大安がよい」「葬式は友引を避ける」など、主に冠婚葬祭などの儀式と結びついて使用されている。
先勝(せんしょう)
諸事急ぐことによし、午後よりわるし。
友引(ともびき)
朝夕よし、午後わるし、葬式を忌む。
先負(せんぷ)
諸事静かなることによし、午後大吉。
仏滅(ぶつめつ)
万事凶、口舌を慎むべし、患えば長びくおそれあり。
大安(たいあん)
移転開店婚礼旅行その他すべてによし、大吉日。
赤口(しゃっく)
諸事ゆだんすべからず、用いるは凶、正午のみ吉。
この関係をもう少し一般化して書けば旧暦の月と日から、簡単に六曜を導くことが出来ます。
(旧暦月 +旧暦日)÷ 6 = A 余り N
ここで知りたいのは余りのNです。
このNと、六曜は次のような関係になります。
N |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
六曜 |
大安 |
赤口 |
先勝 |
友引 |
先負 |
仏滅 |
旧暦の月日さえわかれば六曜は簡単にわかります。
旧暦が使われていた時代では六曜は現在の「曜日」のように分かり切ったものでした。この分かり切った六曜の並びで、大安が目出度いなどと言うことは現代でいえば、「日曜日は大吉の日、結婚式に良」と言っているようなものなのです。
六曜の読み
先勝:せんしょう せんかち さきかち
友引:ともびき ゆういん
先負:せんぷ せんまけ さきまけ
仏滅:ぶつめつ
大安:たいあん だいあん
赤口:しゃっく じゃっこう じゃっく しゃっこう せきぐち
したっけ。


















