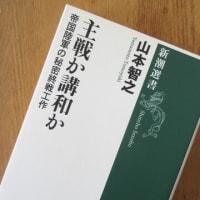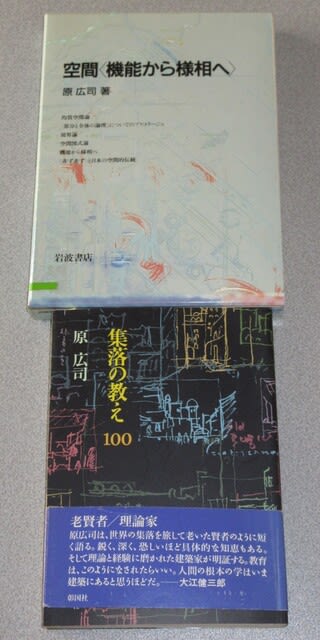

■『空間〈機能から様相へ〉』(岩波書店1987年3月24日第1刷発行、1989年12月5日第6刷発行) この本を1990年に読んでいる。30年以上経過して、内容を忘れてしまっている。ただ、ヤマトインターナショナルビルは、この本に書かれていることが体現されているんだな、と思ったのではなかったかな。今読んだらどんな感想を持つだろう・・・。そして『集落への旅』(岩波新書1987年)も。こうして読む本が増えていく。
『集落の教え 100』(彰国社1998年)で、タイトル通り、100の教えを示している。なるほどな教え、15と81を載せる。
**幾何学的な形態と不定形な形態、一義的に意味づけられた場所と多義的な場所、明るさと暗さ、荘厳された場所と日常的な場所、古いものと新しいもの等々の二律背反するものを混在せしめよ。また、それらのグラジュアルな変化を混在せしめよ。そして、全域をなめらかに秩序づけよ。**(15 混成系 36頁)
**材料が同じなら、形を変えよ。形が同じなら、材料をかえよ。**(81 材料 168頁)
原さんの建築は上の教えに忠実だ。
『集落の教え 100』の帯の文章を大江健三郎さんが書いている。原さんと大江さんは友人同士で、大江さんの出身中学校を原さんが設計している。建築雑誌に掲載されたが残念ながら手元にその雑誌はない。
大江さんも自身の作品に原さんをモデルにした建築家を登場させている。以下は2008年02月02日に書いた記事だが、すこし手を加えて再掲する。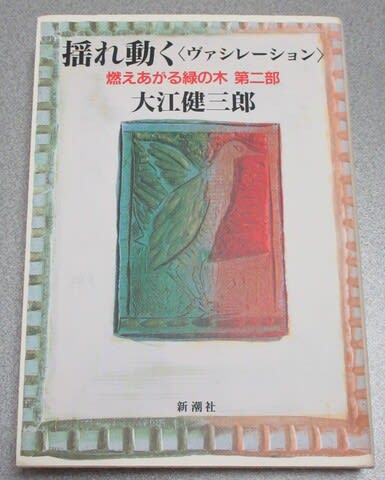
『揺れ動く 燃えあがる緑の木 第二部』大江健三郎(新潮社1994年)
■ この本は大江さんがノーベル文学賞を受賞した直後に出版されて、よく売れたのではないかと思う。第三部の帯には**ノーベル賞作家の最後の小説、完結!**とある。
大江さんはこの小説に荒先生として原さんをモデルにした建築家を登場させている。「あら」と「はら」、よく似ている。
**荒さんは、その独創的な構想を、粘り強くあらゆる細部にわたって実現する建築家だった。** 小説から引用したこの文章は原さんの評価そのものだ。
こんな記述もある。**この土地の民家の建物と集落をイメージの基本に置いて、木造小屋組みの上に和瓦を載せたものだった。**
こんなくだりもある**教会のために建設しようとしている礼拝堂は、直径十六メートルの真円が基本形です。**(185頁)これは原さんが設計した大江さんの出身中学校の音楽室ではないか。音楽室の直径はどのくらいだろう。
円形は音響的には好ましくない。そこで**荒さんは、かれの建築事務所の費用で、生産技術研究所の同僚の専門家に実験を依頼されました。二十分の一の縮尺模型を作って、実験が行なわれたわけです。**(185頁) この先もまだ続く。こうなれば、この中学校の設計の解説文だ。
作家はこのように実話を小説のなかに取り込む。それが時に問題になったりすることもあるが、この小説を読んだであろう原さんはどんな感想だったんだろう・・・。
原さんは大江さんと同じ88歳で旅立たれた。ご冥福をお祈りします。