
■ 6月に読んだ本は以下の6冊。珍しく新書が1冊もない。新たに買い求めたのは『山に立つ神と仏』のみ。後は再読。
『山に立つ神と仏 柱立てと懸造の心性史』松崎照明(講談社選書メチエ2020年第1刷)
『ひとり日和』青山七恵(河出書房新社2007年8刷)
『梟の城』司馬遼太郎(新潮文庫1999年83刷)
『流れる星は生きている』藤原てい(中公文庫2008年改版12刷)
『喜作新道 ある北アルプス哀史』山本茂実(角川文庫1978年再版)
『夏目漱石』江藤 淳(講談社文庫1971年第3刷)
『山に立つ神と仏 柱立てと懸造の心性史』**明治元(一八六八)年の神仏分離令によって神仏混淆の信仰は禁止され、その建築は破壊、転用されて壊滅的な打撃を受けるが、かろうじてそれを逃れた懸造の建築には、日本建築の本来の造形的特徴と文化的古層が残っている可能性が高く、おそらく、その在りように日本列島に住んできた日本人の心が強く反映している。これを解明することは建築ばかりではなく、日本人の信仰心の基層となるものを明らかにする試みにもなるはずである。**(6頁) このような見解に基づく論考。建築論に終始しているわけではないので、なかなか理解が及ばなかった。
青山七恵の『ひとり日和』は芥川賞受賞作。この作品を選考委員だった石原慎太郎と村上 龍が絶賛したという。本の帯に**非常にビビッドで鮮烈、素晴らしいと思った。**という石原慎太郎の記者会見でのコメントが載っている。だが、私は朝もやの中を漂っているような感じを受けながら読み進んで、特に印象には残らなかった。感性がますます鈍くなったのかもしれない。
司馬遼太郎の小説では『梟の城』を初めて読んで、おもしろいと思った。その後司馬遼太郎作品を何作も読むきっかけになった。
藤原ていの『流れる星は生きている』を読んで今回も涙した。終戦を満州で迎えたていさんは3人の幼い子供と共に命がけで日本に引き上げてくる。長男が5歳、次男(数学者の藤原正彦さん)が2歳、末っ子はまだ乳飲み子。ていさんを支えたのは我が子を死なせてなるものか!という強い意志、深い愛情だった。
『喜作新道 ある北アルプス哀史』 解説によると、山本茂実は5年かけて600人もの関係者に取材して書いた2万枚もの原稿をまとめて、この作品を書いたそうだ。取材した多くの人たちの証言が地元(穂高や大町)の方言でそのまま再現されている。喜作と息子は本当に雪崩で死亡したのか、それとも・・・。
『夏目漱石』 江藤 淳がこの論文を発表したのは22歳の大学生の時だったという。江藤 淳はこの論文で既に提示されている漱石論に反論していく。**(前略)しかしこれらの尊敬すべき批評家達によって代表される否定的な見解には、「猫」が今日いまだにぼくらを魅了するのは何故なのか、という問に対する解答が含まれていない。**(61頁) などと中村真一郎らにも手厳しい。ただ驚くほかない。 **小林秀雄の死後は文芸批評の第一人者とも評された。**とウィキペディアにあるが、大学生でこのような論文を書いてしまうのだから、その後の活躍は当然といえば当然か。
コロナ、コロナで早くも半年が過ぎる。今年の後半はどんな本を読もうかな・・・。












 320
320

 320
320

 320
320 480
480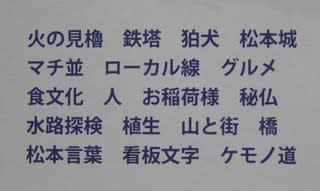 240
240 320
320

 320
320
 360
360 320
320


 320
320 320
320
