 480
480
■ 「少年老い易く学成り難し」この言葉を実感している。
2月の読了本は9冊。うち、7冊が単行本で新書が1冊もない。珍しい。
『「お静かに!」の文化史 ミュージアムの声と沈黙をめぐって』今村信隆(文学通信2024年)
ひとり静かに対峙したい作品もあれば、同行者とあれこれ感想などを語りながら鑑賞したい作品もあるということになんとなく気がついてはいた。本書を読んで私なりにそのことがはっきりした。
『諏訪の神 封印された縄文の血祭り』戸谷 学(河出書房新社2014年12月30日初版発行、2023年1月30日6刷発行)
諏訪は深い。それはなぜ? ドキュメンタリー映画「鹿の国」を見たことにより、「諏訪学」を勉強したくなり読んだ。
『古代諏訪とミシャグジ祭政体の研究』古部族研究会 編(人間社文庫 2017年9月15日初版1刷発行、2024年1月28日7刷発行)
同上。
『狛犬学事始』ねず てつや(ナカニシヤ出版1994年1月20日初版第1刷発行、2012年6月10日初版第7刷発行)
狛犬と括られる一対の獅子と狛犬。両聖獣の違いは口の開閉、角の有無、体の色。それから設置位置の左右、そのどちらか。参道狛犬の大半は石造で体に色は付けられていない(例外はあるだろう。岡谷で見た参道狛犬は木造で着色されていた。過去ログ)。設置位置は両者の相対的な関係だ。像の固有の違いに注目するなら、それは口の開閉か角の有無。
このふたつの特徴の違いのどちらかで獅子か狛犬かを見分ける場合、著者は角の有無に着目し、角が有れば狛犬、無ければ獅子だと判断するとしている。角は制作時、設置時、設置後のそれぞれのフェーズで欠損してしまうことがあり得るのに、なぜ、角の有無なのか、その理由を本書から読み解くことはできなかった(読み落としてないないと思うが)。
言うまでもなく、前提が違えば、その後の論考から導き出される結論も違ってしまう。狛犬に角が必須であるなら、頭頂部にほぞ穴をあけ、別のパーツにした角を穴に差し込むという方法もある。この方法を採れば前述のようなトラブルに対処することができる。
ぼくは獅子と狛犬それぞれの顔の造形で、口の開閉が異なるから、それで判断する方が蓋然性が高いと思う。
『イモと日本人 民俗文化論の課題』坪井洋文(未来社1979年12月25日第1刷発行、1983年1月31日第8刷発行)
『稲を選んだ日本人』坪井洋文(未来社1982年11月25日第1刷発行、1983年2月15日第4刷発行)
弥生は稲作社会という単一的な捉え方ではなく、稲作と畑作は等価値であって両者が互いに影響を及ぼしあっているとみなければならないという主張。
『Y字路はなぜ生まれるのか?』重永 瞬(晶文社2024年10月23日初版、2025年2月10日3刷)
Y字路に関することを、もれなく網羅的に、そして論理的に論じている。すばらしい!文章は硬くなく、楽しく読むことができた。
『「戦後」を読み直す』有馬 学(中央公論新社 中公選書2024年)
内容をきちんと理解することができなかった・・・。専門用語が使われているわけでもないが。
『青い壺』有吉佐和子(文春文庫2011年7月10日新装版第1刷、2025年2月15日第34刷)
帯に累計70万部突破!!とある。およそ50年前に発表された作品が今よく読まれている。人間模様の「あるある描写」故か・・・。
松本清張の短編推理小説にありそうなラスト。
積読解消に向けて、3月も読む。











 280
280
 360
360
 ⑥
⑥





 ①
① ②
②  ③
③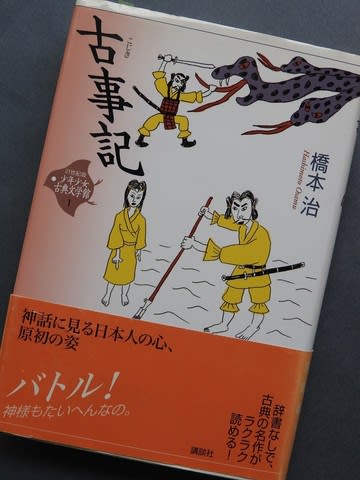 ④
④










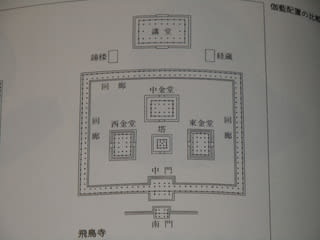 ①
① ②
② ③
③ ④
④ ①
①
 ②
② ③
③ ④
④