
1246 松本市梓川倭 4脚〇〇型 撮影日2020.07.31
■ 今朝7時半過ぎにはこの火の見櫓を見ていた。中学生が火の見櫓の横を歩いて登校していく。
松本平では櫓の平面が3角形、即ち脚(柱)が3本のタイプが多く、およそ8割を占めるがこれは脚が4本のタイプ。背が高く、総高は14mくらいありそうだ(*1)。櫓の中間に踊り場があり、双盤を吊り下げてある。
屋根と見張り台の様子。屋根頂部には避雷針があり、かわいらしいという形容しかできそうにない飾りがついている。半鐘は屋根の中心あたりに吊り下げてある。踊り場は円形、直径は2m超と見る。

脚元 梯子の下端がずいぶん高いところにある。この位置だと昇り降りできない。おそらく火の見櫓を使わなくなってから安全のためにカットしたものと思われる。地面に梯子の下端を固定していたコンクリート基礎が残っている。
このアーチ状の部材は構造上どの程度有効なのだろうか・・・。脚部の下半分以上が山形鋼の単材であることは少なくとも視覚的にはあまり効果が期待できないのではないか、という印象を与える。
*1 消火ホースを干すためのフック付きハンガーと踊り場床面の位置に付けてあるハンガーを引き上げるための滑車などから、火の見櫓の高さを推測した。












 320
320 320
320
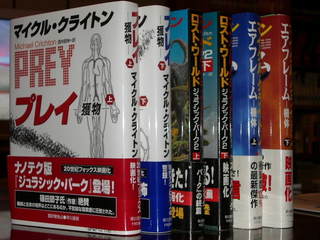

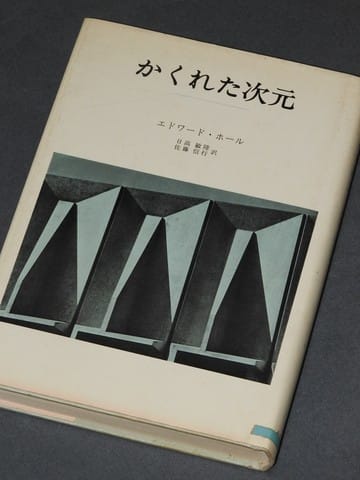 320
320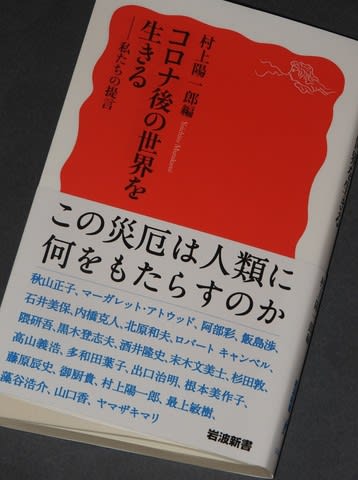 320
320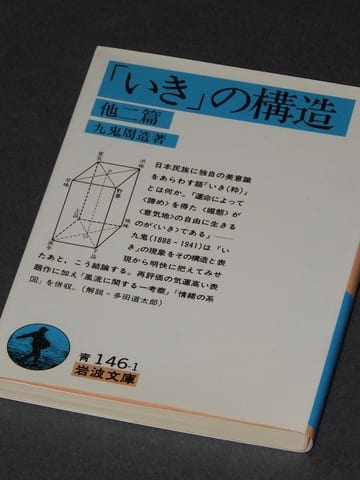 320
320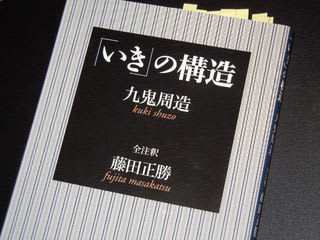
 320
320



 320
320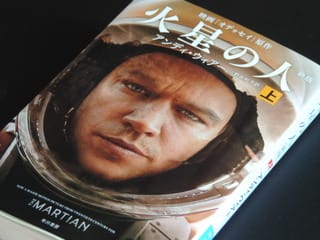


 320
320 320
320
