■ 前回、4月のブックレビューがちょうど200回目だった。毎回4冊取り上げたとすると800冊にもなる。そんなに読んだのか・・・。
5月に読んだ本は8冊だった。
『源氏物語 上』角田光代訳(日本文学全集04 河出書房新社2021年6刷)
安定した貴族社会という恵まれた環境に非常に才能のあるひとりの女性が生まれ合わせたという奇跡が、千年も読み継がれるような文学を生んだ。いつか読みたい、と思い続けてきた。その長年の念願が叶いつつあることがうれしい。
『場所』瀬戸内寂聴(新潮文庫2022年4刷)
塩尻の「えんぱーく」という市民交流センターで開催される本の寺子屋。今年度初回の講演会に参加した。荒川洋治さんが「短編小説と世界」と題した講演を聴き、取り上げられた短編の中で『場所』が読みたいと思った。瀬戸内寂聴さんが我が人生の来し方を、ゆかりの場所を訪ね歩いて振り返る。文章に魅せられた。
『あ・うん』向田邦子(文春文庫2006年4刷)
諏訪市の「楽茶」というカフェで売っていた古書の中にこの本があった。既に読んだと思っていたが、どうもまだ読んでいないようだ。書架から取り出してざっと目を通してみて、こう思って買い求めた。時は太平洋戦争前、ふたりの男の友情がその家族の暮らしぶりとともに描かれる。現代社会ではありそうにないなぁ と思いつつ読んだ。
『鬼煙管 羽州ぼろ鳶組④』今村翔吾(祥伝社文庫2022年11刷)
『菩薩花 羽州ぼろ鳶組⑤』今村翔吾(祥伝社文庫2022年9刷)
火消が大活躍する時代小説。江戸の火消事情が分かる。映画も小説もこのくらい起伏に富み、ジェットコースターのような激しい展開にしないと感性の鈍い現代人(と決めつけてしまって良いのかどうか・・・)には受けないのかもしれない。例えば小津安二郎の映画、永井荷風の小説がもつ静かな雰囲気では物足りないと感じてしまう現代人は多いだろう。
『鉄道ひとつばなし』原 武史(講談社現代新書2003年)
鉄道マニアではないけれど、鉄道がテーマの本は好き。この本は『本の駅・下新文庫』で買い求めた(過去ログ)。日本の鉄道整備は東日本より西日本の方が遅れた。なぜか・・・。難しいテーマ設定だが、原さんはその理由につて実証的に論考している。収録された76話はどれも内容が濃い。この本はエッセイ集というより小論文集。
『親不孝旅日記』北 杜夫(角川文庫1983年)
『本の駅・下新文庫』で200冊くらい並ぶ文庫・新書の中には読んだ本も少なくないし、読みたいと思う本も多い。好みが重なっているのだと思う。北 杜夫ファンとして未読本は読みたいと思う。昭和55年の年末の1週間くらいのヨーロッパ、母親孝行旅行、のはずが・・・。
『クモの世界 ――糸をあやつる8本脚の狩人』浅間 茂(中公新書2022年)
クモについては何も知らないなあ、と思って読んでみた。クモはどれも網を張って昆虫を獲らえているのだろうと思っていたが、約半数は歩き回って獲えているという。中には地中で暮らすクモもいるそうだ。知らなかった。読んでいて、思わず「え!」と声に出してしまったのは次のくだりを読んだ時だ。**世界のクモの餌の消費量が人間の肉と魚の消費量に匹敵することが発表された。**(108頁)信じられない。本当なのかな、と思う。
第5章「自分の子孫を残すために」の第1節「クモの求愛、交尾行動」には「雌にプレゼントするクモ」「催眠術をかけるクモ」「花嫁を糸で縛る」など雄クモのビックリ婚活が紹介されている。交尾後に交尾栓をつけて他の雄が交尾できないようにするクモがいることを読んだ。
だいぶ前に読んだ『モンシロチョウ』小原嘉明(中公新書2003年)にも交尾栓のことが書かれていた。この本を自室の書棚から取り出して確認した。**【その2・貞操帯戦術】 雄が交尾した雌に自分の子を産ませるために編み出した、第二の戦術は驚きに値します。雄はなんと、交尾栓、つまり貞操帯で雌の交尾口を封じるのです。**(134頁)クモにはもっと徹底的な対策、交尾後に雌の生殖器を破壊してしまうものがいるという。
他にもいろいろ驚きの生態が書かれていて、興味深く読んだ。











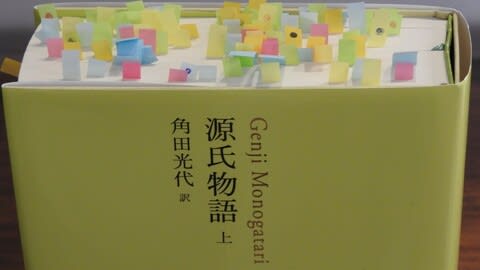 360
360






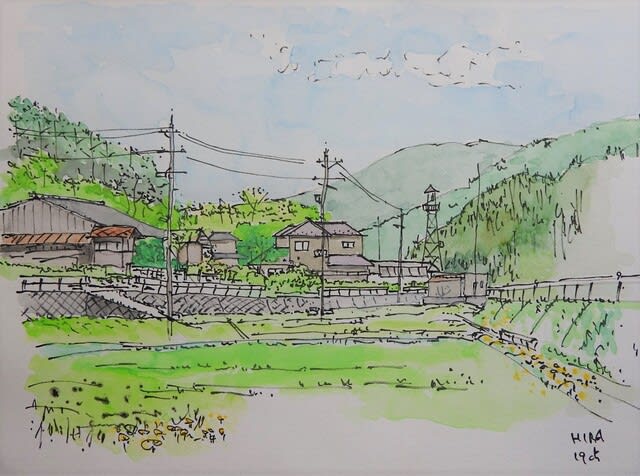

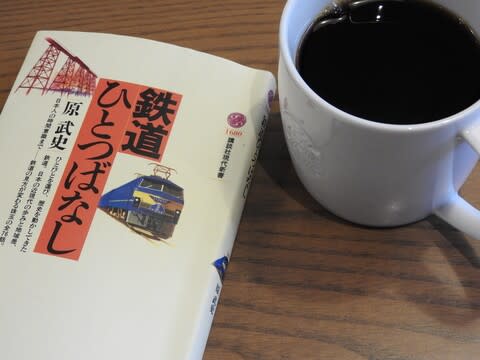 420
420



