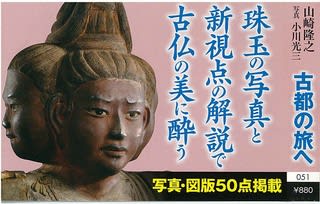△松本駅前の播隆像
■ 今日で5月も終わり。6月最初の本は新田次郎の『槍ヶ岳開山』文春文庫。
**百姓一揆にまきこまれ、過って妻のおはまを刺殺した岩松は、国を捨てて出家した。罪の償いに厳しい修行をみずから求めた彼を絶え間なく襲うのは、おはまへの未練と煩悩であった。妻殺しの呵責に苦しみつつ、未踏の岩峰・槍ヶ岳初登攀に成功した修行僧播隆の苛烈な生きざまを、雄渾に描く長篇伝記小説。** カバーの裏にこのように紹介されています。やはりプロの文章は上手いですね、簡潔で。
このところ仏像に関心が向いています。でもこの播隆上人について描かれた小説を読んでみようと思ったのは、別にそのためではありません、と言いきれるかどうか、あるいはそのためかもしれません。繰り返しの美学が思わぬところにまで関連してきたような気もします。
新田次郎。昔何冊か読みました。やはり新潮文庫で。
松本駅前に立つ播隆、いったいこの人はどんな人生を送ったのでしょう・・・。どうしてあの槍の頂上に立とうと思ったのでしょう・・・。
△常念の肩から槍の先が見えます。