

■ 原宿駅 061126撮影
日本の駅舎はどれも似ていて個性的ではない、と先日書いたが、もちろん中にはこのような個性的で美しい駅舎もある。
原宿駅の建設年は資料によって少し違いがあるが、既に80数年経っている。都内で木造の駅舎というのは今では珍しいのでは。
下はホームから撮ったフィーレンディール構造の橋。構造部材にレールが使われている。中央2箇所の交差ブレース、どちらを勝たせているかに注目。両側のブレース(斜材)の向きからも鋼材の使い方の基本が分かる。橋の全体を写すべきだったと反省。
余分な要素のない「構造の美学」。
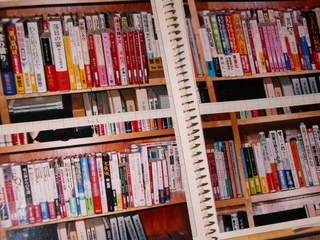
■ 読み終えた本を書棚に順番に並べていく。それを写真に撮ってダイアリーに貼っておく。1979年の読了本が5枚の写真に納められている。実に簡単な方法。
この年は『鷲の驕り』服部真澄からスタート。藤沢周平をまとめて読んだ。最後は『河童が覗いた「仕事場」』妹尾河童。
ダイアリーからブログに移してからも同じ方法。

ブックレビュー0811、読了本9冊。
『どこから行っても遠い町』川上弘美/新潮社 読了。
連作短篇集。ある小説の脇役が別の小説の主役になってまた登場するという仕掛け。
最後に収められている「ゆるく巻くかたつむりの殻」が一番印象に残った。
**死んでいても、まだ死なない。大好きな人の記憶の中にあれば、いつまでも死なない。** これは、『真鶴』のテーマにも通ずる。
**あたしが死んでから、もう二十年以上がたちます。あたし、春田真紀という女が、今でもこうして生きているのは、平蔵さんと源二さんの記憶の中に、まだあたしがいるからです。**
既に亡くなっている人も、生きている人も、記憶の中では共に等しい存在感っていう感覚、よく分かる。
さて、この作品について、川上さんは何を語るんだろう・・・。12月6日の週刊ブックレビューが楽しみだ。


「Mちゃん、隈研吾って建築家、知ってるよね」
「ええ。先日U1さんがブログで取り上げていましたけど、サントリー美術館や広重美術館の設計者ですし、それからしばらく前までテレビでやっていましたよね。吉永小百合が出ているシャープのテレビCMに使われた中国の竹のリゾート施設でしたっけ、あの設計もしたんですよね。もしかしてリゾート施設じゃなくて住宅でしたっけ?」
「Mちゃんって建築に興味あるって聞いてるけど、詳しいね。あれはどっちだっけ、確かリゾート施設だったと思うけど。この間読んだ『自然な建築』で隈さんが自然な建築って、「場所と幸福な関係を結んだ建築」のことだと説明しているんだよね」
「そのこともブログに書いてましたよね。私、毎日U1さんのブログを読んでますから」
「そう? なんだか恥かしいな。いつも書き急いで、まともな文章になってないからね。でね、隈さんの表現に倣えば内藤廣さんの建築理念って「場所と時間と幸福な関係を結んだ建築」とでも表現できると思うんだよね。場所と幸福な関係を結んだ建築に関しては、ボクは同じ意味で安曇野ちひろ美術館について、風景に歓迎されている建築だと書いたけどね」
「そうですか、記憶に無いです」
「場所との幸福な関係って、周辺環境との調和と表現しても、ま、意味に違いはないと思うけどね」
「そうですね。それはわかるんですけど、時間との幸福な関係って・・・」
「時間を味方につけた建築、分かりにくいか。時間の経過と共に魅力が増す素材でできた建築、とでもいったらいいのかな」
「あ、そういう意味ですか。じゃ、「わび」とか「さび」とかいう、例えば茶室なんかを評価する時に使われる美意識に通じる捉え方なんですか」
「そう! まさにそうだね」
「それなら分かります。例えば石とか・・・」
「そうだね。でも表面を磨いた薄い石を外壁に張るって、ちょっと違うのかな。だから都庁は違うような気がする。基本はやはり積まないと。もう今はやらないと思うけど。他に時の経過と共に魅力が増してくる素材って?」
「レンガもそうです、ね?」
「レンガってそうだよね。それから、スクラッチタイルもそうだね。この写真だけど、この外壁もスクラッチタイル。名前の通り表面の引っかき傷がミソだね。あと左官材、漆喰とかさ」
「そうか、そうですね。私、高校生のころは、建築にあまり関心がなかったからスクラッチタイルって知りませんでした」
「例えば県外から訪れた観光客がこの外観見たら、伝統校だってことを知らなくても、歴史を感じると思うんだよね」
「ええ」
「それって、建築が記憶している歴史を、見る人が感じる・・・、それが生徒たちにも語りかけている、ということかなと・・・。生徒達はこの建築から影響を受けていた、教育されていた・・・」
「なんだか、U1さん、技術者らしくない表現ですけれど、なんとなく分かります。そうか、そういうことですか。よく環境が人を育てるって聞きますけど・・・。でも、校舎から教育されたんだっていわれても、そうなのかなって思いますけど・・・」
「そうだと思うけど。環境って、単なる建築的なハードな環境だけじゃないとは思うけど。でも、教育施設ってやはり記憶力のある材料で造らないといけないと思うね。金属パネルやガラスを多用した外壁ってよくないね。時間を蓄積する力がないからね。だから、こういうタイルとかレンガ、内壁は左官材で仕上げないと・・・」
「それって、つまり、時間の経過と共に汚れて行くだけで、魅力的な風合いというか雰囲気が出てこない材料ではダメってこと・・・ですね?」
「そう。それから、せっかく長い歴史を記憶している建築を安易に取り壊すこともやはりいけないと思うね。この校舎を取り壊すってことになったら、Mちゃんだって反対するでしょ」
「ええ。署名活動とかになったら、署名します。でも、この校舎は登録有形文化財ですから、取り壊されることはないですよね。最近U1さんが紹介していた、函館の弥生小学校のことを取り上げたブログにも保存について書いてありますね。とても観察眼のある方が書いているんでしょうね、きっと。亀井勝一郎もあの小学校の卒業生なんですってね。それに啄木が教鞭をとっていたとか」
「そうなんだってね。Mちゃんも読んだんだ・・・。あの論考を読むと確かに観察力のある人だって思うよね。街の構造を的確に読み取っているよね。街の人々と学校との関わりについても指摘している。ボクにはとても書けない文章」
「でも、U1さんは何でも興味があるって感じで、私は楽しくブログ読んでます」
「ありがと、ときどきHなことも書いているけど」
「はは、でも、楽しいですよ。アルコールな夜のブログ、とかって断って書いたりして」
「そうしないと書けないよ」
「ところで、U1さん、本、何か今読んでますか?」
「これ、川上弘美」
「この表紙の絵、えーと 週刊新潮の・・・」
「谷口六郎」
「そうでした。私、川上弘美って読んだことがないから・・・ 面白いですか」
「面白いというか、なんだろう、落ち着くというか。この作家に限らないけれど、作品の魅力って説明するのが難しい。読んだら貸してあげるから」
「あ、はい。読んでみます」

■「民家 昔の記録」というシリーズなのだが、この写真の記録がない。
撮影年が1985年の9月ということは当時のダイアリーで確認できた。27日から3日間東北を旅行している。
撮影場所はたぶん山形県内。具体的に山形県のどこなのか特定できない。鶴岡あたりではないかと思うがはっきりしない。これでは「民家 昔の記録」にならない。
茅を葺き替えて数年位しか経っていないと思われる中門造りの民家。中門造りは東北に広く分布しているから、山形県内という記憶とは一応整合する。
棟のグシの数がこの写真では確認できない。左側の鉄板葺きの部分はなんだか違和感がある。後から増築されたと思われる。壁が軒際まで板張りになっているのは雪に対する配慮であろう。
この旅行で谷口吉生設計の土門拳記念館を見学したことは記憶にあるし、チケットも残っていた(写真)。
1985年のダイアリーに貼ってあるチケット、この習慣はいまも続いている。
数少ない駅舎の記憶からこのような結論に帰納させていいのかなという思いもちらついた。
でも、テレビでよく放送される旅番組を観ていると、駅舎をバックにタレントが「○○に着きましたね」「さあ、行きましょうか」といった会話するところから始まることが多いが、そのとき映し出される駅舎は確かに没個性的だ。新幹線の通っている路線の駅舎などはどれも箱型で、外壁は白やグレーの横長の(たぶん)鋼板パネルに覆われている。
なぜだろう・・・。理由がいくつも浮かんでくる。 短期間で完成させるのに適した構法が採用されるから? ローカル色をデザインに活かそうにも、もはやそのようなものは消えてしまっている? そもそも現代建築は同じ技術で世界を覆い尽くすことを目指しているのだから地方性などという概念は無く、それは駅舎も同じ?
身近な駅舎を思い浮かべる。
長野駅も松本駅も塩尻駅も建て替えられているが、以前の駅舎のほうが親しみやすく、地方都市の玄関口にふさわしかったように思う。隈さんが『自然な建築』に書いていた「場所と建築との幸福な関係」があったと思う。
駅舎がデパートやホテルなどの機能も備えた大きなビルになってから顔が見えなくなり個性も失ってしまった・・・。
そうかな、とここでまた異論が浮かんでくる。
原さんの京都駅はどうよ、巨大な複合ビルだけれど「個性的」じゃないか。磯崎さんの由布院駅はどうよ、黒塗りの板張りの駅舎は個性的じゃないか。内藤さんだって、スチールと木を使った繰り返しの美学な日向市駅を設計したじゃないか。坂さんだって確か東北で個性的な駅舎を設計したぞ。
確かに。でもこれらの駅舎に表現されているのは建築家の個性であってその地域の個性じゃない・・・。京都駅は京都にふさわしいデザインじゃないって批判されたし、由布院駅だってハラミュージアムアークだっけか、あれと同じようなデザインで別に由布院を表現したってワケじゃない・・・。
じゃ、地方性を建築で表現するってどういうこと? 松本駅なら蔵か。京都駅なら寺院か・・・。まさか、まさか。
地方性を建築が表現する?、違う、建築が地方性を創っていく、創っていかなくちゃいけないんじゃないのか・・・。あの東京駅だって、東京を表現しようという意図でデザインされたわけじゃないだろう。京都の寺院だってそうだろう。
その地域の歴史や文化を担うに足るように少なくとも100年、いや200年の時の流れに耐える建築を創ることだ。安易にペナペナのインスタント建築なんかつくっちゃいけないんだ。そこに必要なのは人々の200年使うという意志というか建築は文化だという見識だ。
この辺まで考えて夢の中へ・・・

■ 「教育環境は学校に限定されるものではなく、街にまで及ぶものだと思います。」 数稿前の記事にいただいたコメントにこう返信して、この本のことを思い出した。
ファストフードに掛けたタイトルは少し軽薄な感じがしないでもないが、地方都市の変容がもたらす病理を鋭く指摘している。一読に値する本だと思う。
カバーの折り返しにこの本で著者が指摘するポイントが載っているので引用する。**地方はいまや固有の地域性が消滅し、(中略)全国一律の「ファスト風土」的大衆消費社会となった。このファスト風土化が、昔からのコミュニティや街並みを崩壊させ、人々の生活、家族のあり方、人間関係のあり方もことごとく変質させ、ひいては人々の心をも変容させたのではないか。(後略)**
最終章に「生きた街こそが学校だ」という小見出しの論考がある。書き出しに都市計画家 蓑原 敬氏の指摘が引用されている。以下、引用の引用。
**私たちは、歩きながら、単に視覚だけでなく、音や匂い、肌触りなどを全身で知覚しながら発育してきたし、そのような生活環境全体を背景として、多様な人間関係を経験しながら成熟した大人になっていくのだ。街は、知覚や感性を獲得していく文化の伝承装置だった**
「街は文化の伝承装置」 重層的な時を負う建築群から成る歴史的な街並み、その教育的な効果を実証的に示すのはおそらく無理だと思う。けれども私たちはそのことを経験的に知っているのではないか。
街は長い時をかけて織り上げるタペストリーだと思う。織り込まれた歴史的な建築を取り壊すことによってタペストリーが次第に解けていく。そして街の教育力も低下していく・・・。どうもこの国は織り上げたタペストリーを簡単に解いてしまうことにあまり抵抗感がないようだ。
私が函館の歴史的な街並みを観察して歩き、美しい夜景を眺めたのはもうかなり昔のことだ。
どうやら函館というかけがえのない美しいタペストリーも危機にさらされているらしい。それもタペストリーを織り上げてきた人たちの手によって・・・。


■ 長野県の大北(だいほく、たいほく:大町以北)地域では昨晩 2、30cmの積雪がありました。もうすっかり冬景色です。
ある建物、大屋根からの落雪で既にこんな状態です。軒先に雪除けを設けてありますが、リアルにこの様子がイメージできないと案外このような設えは設計段階ではできないものです。こうすれば冬期間除雪の必要がなく、安全な通路が軒下に確保できます。雁木(がんぎ)ですね。
赤い鉄骨柱の間に建てた木の柱は着脱式。簡単な仕掛けで、容易に柱を建てることができるような工夫がしてあります。このような対策を講じた設計者に拍手です。繰り返しの美学な木の柱は常設でもよかったかもしれません。
■『構造デザイン講義』王国社 で内藤廣さんは建築と土木の構造材であるスティールやコンクリート、プレキャストコンクリートなどについて章立てで論じています。木造についても一章割いていますが、なかなか興味深い指摘がありました。
「木」が均質化、標準化、工業化に馴染みにくい素材であり、そのことが近代建築から排除された理由だと指摘しています。近代建築はまさにこのような指向の所産だったのですから。
部分破壊が全体破壊に繋がらない木造の方法論は、極めて東洋的な世界観に通じるところがある、と内藤さんは指摘し、続けて部分の矛盾を許さない「無矛盾系」の技術が建築の主流という状況にあって、(アメリカが主導した今日の世界観そのものですね)小さな矛盾がたくさんあっても安定した構造が保たれる木造という「多矛盾系」こそが21世紀に求められる世界観に通じるということを述べています。
錦帯橋はこの多矛盾系の極致のような構造でいまだに解析がうまくできないそうです。五重塔もなぜ倒れないのか諸説あってよく分からない構造だそうですね。

内藤さんは「海の博物館」で初めて大断面集成材を構造に使ったそうですが、それ以降「安曇野ちひろ美術館」「牧野富太郎記念館」「倫理研究所富士高原研修所」「日向駅」などを木造で解いています。
木造・・・、経験や勘がなかなか認められない状況で木を使った構造を美しく解くことには高いハードルがいくつも並んでしまいます。コンクリートやスティールとの混構造にすると適合判定行き・・・。でも内藤さんがみごとに解いてみせた作品に接すると、チャレンジしてみたくなります。
高知駅のスケッチ
■ デザインについて昨晩考えた。
デザインとは「もののありようを決めること」。ここに「美」を加えて「もののありようを美しく決めること」としてもいいかもしれない。デザインには「美」が不可欠の要素だと思われるので。ここで「美」とは何かという新たな問いが生まれるが・・・。
なんだか曖昧模糊とした表現だが、デザインの汎用性のある定義となるとこんなことになりそうだ。この定義にデザインの対象を具体的に当て嵌めればいい。車、食器、料理、本、名刺、都市、建築、インテリア、テレビ番組、ゲームソフト、人生、・・・、ものは何でもデザインの対象になる。
建築のデザインとは建築のありようを決めることだ。その際、判断する材料にはいろいろあるだろう。
内藤さんは判断材料に「場所」と「時間」が欠落していると近代建築を批判し、地理的・歴史的な文脈を断ち切って、時間の経過を考慮していない近代建築を宇宙船のようだと指摘する。
「場所」と「時間」を判断材料に取り込んで、「技術」という手段によって「美しく」具現化された建築。内藤さんが『構造デザイン講義』で挙げたキーワードを使えば、望ましい建築をこのように捉えることができるだろう・・・。
この辺まで考えて、昨晩は夢の中に入り込んでしまった。今夜続きをまた考えよう。

『構造デザイン講義』内藤廣/王国社 読了。
内藤さんはデザインとは何かと自問し、「技術」「場所」「時間」を翻訳することだと自答している。この場合の対象は建築、土木だが、もっと対象を広げて、デザインとは何かと自分に問うてみる。ブックデザイン、工業デザイン、食のデザイン、服飾デザイン、・・・。いかなる対象にも当て嵌まるデザインの定義・・・。
今夜は布団の中でデザインとは何か考えてみよう。このところ寝不足気味だから、あっという間に夢の中かもしれないが。
ということで今夜は早めに切り上げる。


■「源氏物語」の予習テキスト『源氏物語の女君たち』瀬戸内寂聴/NHK出版を購入。
今月からエッセイストの大塚ひかりさんの現代語訳「源氏物語」ちくま文庫が刊行されるという。週末に書店に行ってみよう。既に第一巻が並んでいるかもしれない。
大塚さんは小学生のときから古典に親しんでいるそうだ。日曜日の朝、ラジオ番組で源氏物語について語っていた。男と女の営みについては暗喩的な表現が多いとのことだった。「寂聴源氏」はその辺をどのように訳しているのだろう。
そろそろ予習を終わりにしないと・・・。

■ 善光寺の参道に続く通りには何件もの蔵造りの商店が並んでいます。この写真もその内の一軒です。持ち出し梁の先に桁を載せた出桁造りは蔵造りの一般的なデザインです。通常はこの軒先周りは壁と共に漆喰で包んでしまうのですが、この蔵造りは、塗装ではないかと思われます。きちんと観察してこなかったことを反省しますが、この写真ではそのように見えます。
この持ち出し梁の下面は平らではなくR状に加工されています。見た目に軽やかで、通常の重厚な印象がありません。木造の洋館のようにも見えます。
漫然と見ているとみんな同じように見えてしまいますが、よく観察すると各パーツのデザインがそれぞれ違うことに気がついて楽しいものです。
今回も「繰り返しの美学」として載せておきます。

■『公立学校の底力』志水宏吉/ちくま新書読了。
長野まで高速バスで出かけたがその往復の車内と信濃美術館のカフェでこの本の大半を読んだ。はしがきによると著者は公立の頑張っている学校を応援するというスタンスで書いたという。
本書は序章と終章を含め14章で構成されているが、第1章から第12章まで大阪を中心に「力のある」12校の公立の小、中、高校を紹介している。
著者は高い総合力を発揮している学校を「力のある学校」というキーワードで捉えている。子どもたちを元気づけ、やる気にさせるような人間関係のきずなと多彩な教育活動を組織できるのがその内実だと説明していて、その実現に必要な八つの要素を示している。その一つとして「気持ちのそろった教職員集団」を挙げているが、八つの要素、それぞれを詳しく論じている。
偶々、今朝の新聞のコラムでこの本が取り上げられていた。教育のありようを考える手がかりになる、と紹介されている。確かにとかく点数至上主義に陥りがちな教育現場を再考するのに有用な1冊だと思う。

善光寺境内のポスター
■ 「美しい木の椅子展」
長野県信濃美術館(長野市)で開催されている展覧会を観てきました。
共通の機能を持ちながら、椅子のデザインって実に多様ですね。寸法も形も色も材質もみんな違う。建築とデザインの基本的な条件が似ているな、と思いつつそれぞれの作品を鑑賞しました。
展示は四部で構成されていて、第二部の「暮らしの中の木の椅子展」では一部の作品を除いて座ってみることもできます。観て美しく、座って寛げる椅子が何点かありました。
「High back Chair 35」という椅子はホワイトアッシュという木の細いフレームと布製のやや大きめの座面、背もたれとのバランスが良くて美しく、座り心地も抜群でした。すーっと体の力が抜けていきました。やはりハイバックで頭まで支えてもらうと、リラックスできます。 機能的にも意匠的にも優れた作品だと思いました。
第四部の「日本の名作椅子」では、柳宗理の洗練されたデザインのバタフライスツール、剣持勇の華やかな藤丸椅子、磯崎新のモンローチェアなど、有名な椅子が展示されていました。モンローチェアは神岡町の庁舎(磯崎新設計)で黒塗りのものを昔見た記憶があります。
前後しましたが第一部の「世界の名作椅子100点」では本でしか見たことのなかった有名な椅子を何点か観ることができました。
充実した展覧会、会期は11月16日までです。









