「風景」:目を楽しませるものとしての、自然界の調和の取れた様子。
「光景」:その人が実際に目で見た、印象深い景色や、ショッキングな事件の様子。
新明解国語辞典
「風景」:けしき。風光。風姿。風采。
「光景」:目のひかり。ありさま。様子。景色。
広辞苑
新明解国語辞典の方が、意味を分かりやすく説明しようという意図が窺える。
広辞苑のけしきと景色、表記の違いに意味があるのだろうか・・・。
今読んでいる年越し本『生命を捉えなおす』清水博/中公新書に**アトミズムには、単に対象を微視的観点から捉えるだけでなく、動的な現象を静的な状態に分解して、興味を「現在」に絞って観察をするという性格があるのです。**という記述がある(17頁)。
この説明は連続的な変化、動態を瞬間的な状態に微分して捉えるという意味だと理解できるだろうが、この意味とは関係なく、風景は広範囲のどちらかというと静的な状態を、光景は目前の動的な現象を指しているという説明って、なかなかいいのではないかと、ふと思った。
でもまだまだ、映画評論家と映画エッセイストの違いについて「映画評論家は映画を観て泣かない、映画エッセイストは泣く」という分かりやすい説明には及ばない・・・。
風景と光景の違いを分かりやすく・・・。

■ 川端康成の『古都』読了後、年越し本を書店で探し求めた。できれば小説、と思っていたがなかなか見つからず、結局中公新書からこの本を選んだ。なかなか難しいテーマ、内容だ。
**生命は秩序を自己形成する能力である**と考えている著者。**細胞から、組織、器官、個体、社会、生態系に至る様々な系に固有の生きている状態が存在するという観点に立って、生きている状態の統一的な理解を考えてみようという立場をとります。**
このように本書で著者は各ヒエラルキーの生命体に共通する、生きているという状態の統一的な理解を示そうという興味深い試みについて書いている。これは数日で読了というわけにはいかない。年越し本に相応しい名著と見た。
■ 昨日(22日)、NHKの「ラジオビタミン」を少し聴いた。番組で「映画評論家」と「映画エッセイスト」ってどう違うのですか? という問いにゲストが評論家は映画を観て泣きません、エッセイストは泣きます、と答えていた。これはなかなかの答えだ。
「風景」と「光景」の違いは? 「特有」と「固有」の違いは? 前から気になっているのだが、明解に説明できないでいる。先のような上手い説明ができないものだろうか・・・。

■ 『古都』川端康成/新潮文庫を読み終えた。
川端康成の作品を再読したことも今年の読書の成果。『山の音』 『千羽鶴』 『みずうみ』 『日も月も』 『伊豆の踊子』そして『古都』。以前『雪国』と『眠れる美女』も再読したから、川端作品はもういいか。来年もひとりの作家の作品を集中的に読んでみようかな・・・。
さて『古都』。
主人公の千重子は庭のもみじの古木の幹に咲く二株のすみれを見て、**「上のすみれと下のすみれとは、会うことがあるのかしら。おたがいに知っているのかしら。」と、思ってみたりする。** 少し離れて咲くすみれの花は、違う環境で別々に育ったふたごの姉妹・千重子と苗子との出会い、心の交流を描くこの物語を暗示するもの。
川端康成は小説に日本の美しい自然を織り込んだが、この作品も同様で、京都の美しい自然や名所が織り込まれている。この小説は雪降る静かな夜に読むのがいい。北山杉の美林に雪が降る光景を思い浮かべながら・・・。
■ 今年も残すところあと10日ほどになった。今年の読み納め本は何になるのかまだ分からないが、今年印象に残った3冊を挙げる。


『日本辺境論』内田樹/新潮新書
「辺境性」という観点から日本文化の特殊性を説く。和辻哲郎の『風土』に通じると見た。
一方通行的にこの国に流れ込んできた外来文化の受容とこの国なりの変容。日本の文化の歴史は辺境という地理的な条件からの必然か・・・。
『進化の設計』佐貫亦男/講談社学術文庫
神(造物主)をデザイナーに見立てて、神の様々な生物デザインを評価する。神のデザインは常に完璧、というわけではもちろんなかった・・・。
このことを指摘する関連本2冊。

『おそめ 伝説の銀座マダム』石井妙子/新潮文庫
起伏の多い人生を「さだめ」と受け止めて生きぬいたおそめさんの生涯。多くの文人や政財界人を魅了し続けたおそめさんの魅力とは・・・。
書棚にはこんな本も。

197901
■ 昨日(18日)、瓦屋根の写真をアップして、30年以上も前に都内で撮ったこの写真のことを思い出した。瓦の雪が陽の当たる部分だけ融けている。
このパターンを美しいと感じてカメラを向けたのだろうが、当時は「繰り返しという単純なルールによって秩序づけられた状態は美しい」などと、繰り返しの美学のことは考えもしなかった・・・。
今ならこの屋根の瓦と雪のパターンも繰り返しの美学と捉えることができる。

安曇野市豊科田沢にて
■ 「かわら」ということばの起源についてはいくつか説があるようだ。
丸栄陶業㈱の社史、『日本の瓦・三州の瓦 栄四郎瓦の二〇〇年』には、器や蓋、陶器片などを意味するサンスクリット「カパーラ」、亀甲(かはら)、屋上の皮(かは)、土が焼かれて板状に変わるところから「かはる」などの説が紹介されている。瓦が遥か昔、大陸から瓦造りの専門家とともにこの国に伝わったことも同書に書かれている。
以来、千数百年の長い長い時を経る間、瓦そのものも、瓦を葺く技術も洗練されてきた。やはり長い歴史を負うているものや技術には嘘がなく、そして美しい。その美を単に「繰り返しの美学」などと記していいものだろうか・・・。

123

安曇野市豊科田沢の火の見櫓
■「完成度の高いフォルム」 この火の見櫓をひと言で評すると、こうなるだろう。
屋根と見張り台の大きさや離れのバランス。上方に絞り込まれている櫓の緩やかなカーブ。脚部のシンプルなアーチ。これらのどれもが美しい。そして細部の端正なデザイン。櫓の中間の踊り場は最初から設けられていたのだろうか、その手すりの横材が櫓のアクセントになっている。
火の見櫓と周囲の家屋や樹木との高さのバランスが良い。集落によく馴染み、そしてまたランドマークにもなっている。地元の鉄工所の作だろうが、洗練されたデザインに職人の優れたセンスが窺える。
建築のデザインのありようをも示唆しているかのようだ・・・。

■ 『おそめ』を読んだことが、『古都』を再読するきっかけになった。
川端康成は京都の下鴨泉川町に居を移して1年ほど暮らし、長編小説『古都』と『美しさと哀しみと』を同時に執筆した。昭和35、6年のことだ。先日読んだ『おそめ』にこのことが書かれていた。おそめさんは、川端康成や大佛次郎ら、京都を描く作家の取材を助けたという。
『古都』を書棚に捜したが見つからなかった。仕方なく先日買い求めた。新潮文庫「九十七刷改版」、長年読み継がれてきていることがわかる。活字が大きくて読みやすいのは助かるが、薄茶色に変色した用紙の細かな活字を読むのとは明らかに気分が違う。再読しているという気持ちにならない。
今年話題になった「電子書籍」を読むときもおそらくそうだろう。電子書籍で再読する時、「ああ、この小説は30年前に読んだな~」、などと感慨を抱くことはないのではないか。電子書籍は時の流れとは関係なく、いつでも新しい。
今朝は何を書きたいのだろう・・・。この辺でやめて、読了後にまた書こう。

『ことばと思考』今井むつみ/岩波新書
■「サピア・ウォーフの仮説」については以前も取り上げた。これは言語が世界の見え方を規定する、認識の仕方を規定するという仮説だが、本の帯の「異なる言語の話し手は世界の見え方が違う?!」 から分かるように、著者はこの仮説に認知心理学の立場から回答しようという興味深い試みについて書いている。
**ことばを持たないと、実在するモノの実態を知覚できなくなるのではなく、ことばがあると、モノの認識をことばのカテゴリーのほうに引っ張る、あるいは歪ませてしまうということがこの実験からわかったのである。66頁**
**言語は私たちにとってなくてはならないもので、言語をわざわざ使えなくするような人工的な状況でなければ、脳は無意識に、そして自動的に、なんらかの形で言語を使ってしまうのである。これを考えれば、言語を介さない思考というのは、言語を習得した人間には存在しない、という極論も、あながち誤っていないかもしれない。202頁**
言葉を覚える前の赤ちゃんや、異なる言語を使う人たちを被験者にした実験などを通じて、本書のテーマに迫る論述を興味深く読んだ。日本人が虹を赤橙黄緑青藍紫の7色だと認識するのはなぜか、本書を読めば理解できるだろう。
**かつて銀座に川端康成、白洲次郎、小津安二郎らが集まる伝説のバーがあった。その名は「おそめ」。マダムは元祇園芸妓。小説のモデルとなり、並はずれた美貌と天真爛漫な人柄で、またたく間に頂点へと駆け上がるが―。私生活ではひとりの男を愛し続けた一途な女。ライバルとの葛藤など、さまざまな困難に巻き込まれながらも美しく生きた半生を描く。隠れた昭和史としても読める一冊。**
巻末に参考文献一覧が載っているが、その数がすごい。著者はこのノンフィクションの執筆に約5年を費やしたという。
読了後にまた書こう。
注)**内は引用文。

■ 『おそめ 伝説の銀座マダム』 石井妙子/新潮文庫を読み終えた(1212)。
大正12年、上羽秀(うえば ひで)は京都木屋町、高瀬川のほとりの裕福な石炭問屋に生まれた。家庭内にあってはならない不幸な出来事で母親は秀と掬子、ふたりの娘と共に婚家を出る。妹の掬子は養女に出されて・・・。 やがて秀は祇園芸妓になる。 そして運命の人、俊藤浩滋との出会い・・・。秀の人生をトレースしようとすればかなり行数を要す。
ここでは起伏の多い人生を「さだめ」と受けとめて生きぬいたひとりの女性、その生涯を綿密な取材に基づいて綴ったノンフィクション と括っておく。
巻末の参考文献一覧は2段組で18頁に及ぶ。取材協力者は100名近くになるという。これはもう凄いという他ない。著者・石井妙子さんの執念と評すべきだろう。

『車窓の山旅 中央線から見える山』山村正光/実業之日本社
■ 1985年だから、25年前に読んだこの本のことをふと思い出した。
カバー折り返しに載っているプロフィールによると、著者の山村さんは昭和2年生まれ。国鉄で40年間、主に中央線の車掌として新宿―松本間をおよそ4000回乗務したという。
旧制甲府中学で山岳部だったという山村さんは、中央線から見える山々を車窓から観察し続けた。観察した山々について本書にまとめた。紹介されている山は100座を越える。見開き2頁に1座、塩尻松本間では鉢盛山、鉢伏山、鍋冠山、燕岳、仙丈岳、王ヶ鼻、常念岳、大滝山、有明山、そして最後に乗鞍岳が取り上げられている。
有明山の頁では山の名前の由来について、『日本名勝地誌』の有明山の項の「霖雨ある毎に河水汎濫上流より巨石を押流し来たりて雨後は必ず沿岸の景色一変す」という記述を紹介し、有は荒の転化、明は『古代地名語源辞典』から崖、湿地ではないかとし、中房川の氾濫で生じた「荒れはてた湿地」あるいは花崗岩の風化による「荒れた崖」の源頭の山という意味ではないか、と記している。さらにこの説を補強する文献が紹介されているが、引用は省略する。「荒れた崖」は有明山の特徴をよく示しており説得力がある。
このように、山村さんは取り上げたそれぞれの山を内容濃く紹介している。山に関する興味、知識がなければ中央線の車窓から、この本に紹介されている山々は見えないだろう。脳は伝えられる情報を既得の情報に照らし合わせて認識するのだから。
知らないことは見えない、認識できない。昔、撮りためた民家の写真をまとめたときも、これと同じことを書いた(下)。考え方は変わらないものだ。
ところで、山梨県にはあお向けに寝た裸の女性を思わせる山があって、勝沼駅あたりから見えるという(新宿に向かって右側)。こんど電車で東京に出かけるときに観察してみよう・・・。
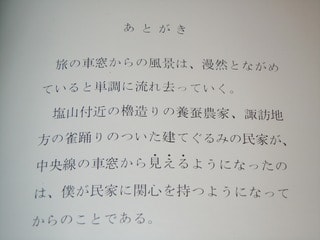

ゑしんの里記念館
豊田市美術館
■ 新潟県上越市にある「ゑしんの里記念館」(上)。人工的につくられた「水庭」と鉄骨のフレームの繰り返しは豊田市美術館(下)のファサードの構成とよく似ている。そう、「繰り返し」が美しいということを池原さんも谷口さんも承知している。でなければこのようなデザインをするはずがない・・・。

■ 「市民タイムス」(タブロイド版のローカル紙)に火の見櫓解体の記事が載っていることをFさんから電話で教えていただいた。
松本市波田で、不用になった5カ所の火の見櫓を解体する事業を始める、と記事にある。その第一弾として6、7日で2区の火の見櫓を解体するという・・・。
*****
今朝(7日)、撤去が報じられた火の見櫓を見に行った。既に時遅し。火の見櫓は撤去され、自然石往復積の擁壁に梯子が残されているのみだった。
昭和30年代に全国で盛んに建てられた火の見櫓が次第に撤去されていることは承知している。でもそれはどこか遠くの市町村の出来事のような気がしていた。地元の鉄工所が住民の期待に応えて誠意を尽くしてつくった火の見櫓が解体されて消えてしまう。そんなことがこの松本平でも起こるなんて・・・。

■ 先日 上越市板倉区(旧板倉町)にある「ゑしんの里記念館」の見学会があった。この記念館は親鸞の妻・恵信尼ゆかりの資料や関連書物などの展示のために、恵信尼が晩年を過ごしたとされる板倉区に計画された。設計は池原義郎氏。繊細な意匠が施された建築だ。是非見学したかったが残念ながら私は参加できなかった。
参加した同僚が撮った写真(上)、遠くに火の見櫓が写っている! この火の見櫓にTさんは気がついた(拍手)。で、写真を撮ってきていた(下)。もっと近づいて撮って欲しかったが、仕方がない。
121
この屋根は6角形だろうか、見張り台と比べると小さい。それに松本平の火の見櫓とは形が少し違う。
松本から、ここまでは車で2時間だと聞いた。いつか出かけなくては・・・。










