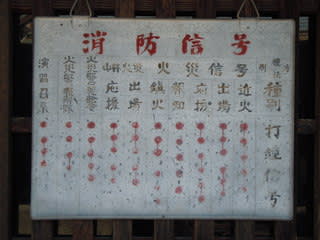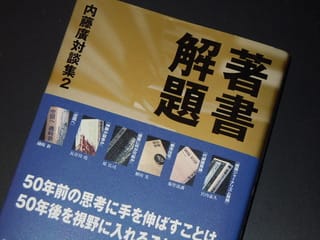**原子力発電所の津波評価においては、「安全設計審査指針」,「原子力発電所の津波評価技術(土木学会)」の考えに基づき、敷地周辺で過去に発生した津波はもとより、過去最大の津波を上回る、地震学的に想定される最大級の津波を数値シミュレーション解析により評価し、重要施設の安全性を確認しています。** 東京電力のHPより
地震学的に想定される最大級の津波を「数値シミュレーション解析により評価し」ということは、想定される最大級の津波の高さをそのまま想定値にはしていないということなのだろうか、この数値シミュレーションが妥当なものであったのか、その検証がいずれ行われることになるかもしれない。いや、そこまでさかのぼることはしないかもしれない・・・。
原発のトラブルをどのように収束させるのか、国際的にも注視されている。 十分な睡眠も、満足な食事もとらずにそれこそ命がけで作業にあったている多くの作業員の方々に心から感謝する。
いままで原子力発電には全く無関心で知識もなかった。これからどんなライフスタイルをとるべきなのか、安心して暮らせる社会システムをどのように構築するのか、国民的な議論が必要になるだろう・・・。
このところ、ブログのトーンがだいぶ変わってしまっている。徐々にもとに戻していこう。
メモ)
原子力発電所の津波評価技術」は土木学会の津波評価部会が平成13年度にとりまとめた(同学会のHPによる)ということだが、その部会の委員構成についてはこんな指摘もある。
→ http://www.isep.or.jp/images/press/report_0322.pdf