
■ 民家 昔の記録 今回は茨城県稲敷郡東村(当時)の農家(撮影7910)。
たおやかな寄棟の屋根が印象的。関東地方にはよく見られるが棟を瓦巻にしている。棟は雨仕舞上弱点となりやすく、また腐朽もしやすい。瓦ならば腐朽の心配もなく、継目を漆喰で処理しているので雨仕舞上も支障ない。棟端(棟の両端部)は漆喰や土で固めてある。
注目は建具。この写真では分かりにくいが、玄関は木製の引き違い戸、部屋の建具は障子戸。当時はまだアルミ製サッシではなく木製建具が一般的だった。
前稿に載せた民家と比べると使用されている材料の違いがよく分かる。民家はこの30年あまりですっかり変わってしまった・・・。



■「通」と「青鬼」は共に北安曇郡白馬村にある集落です。今回は下見。紅葉の頃、再び出かけて、じっくり路上観察したいと思います。上が通、下が青鬼の民家です。

 1
1
■ 先日松本市大手の古いビルの正面の写真を載せました。これはそのビルの側面を撮ったものです。
窓廻りの意匠が見事です。窓台に使われていたのは、やはりスクラッチタイルでした。レンガによる縁取り、窓上の飾り。
こんなすばらしい建築が取り壊されることなく、再生されたのは大変喜ばしいことです。 2
2
歴史の記憶を留める建築、松本にもまだまだ残っています。これからはこのようなレトロな建築も路上観察しようと思います。
1 旧宮坂薬局 松本市大手1丁目
2 旧上原薬局 松本市大手2丁目
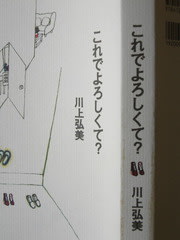
■『これでよろしくて?』読了。川上的ガールズトーク小説と帯にあるが、まあ、要するに女性たちの井戸端会議録。
主人公の主婦、上原菜月が元彼の母親に誘われて入った「これでよろしくて? 同好会」。ときどきレストランに集まって「井戸端会議」。
「婦人公論」に連載された小説ということだから、当然読者は女性。井戸端会議ではその都度テーマが設定される。読者が女性であることを意識したテーマ。 私としては、レストランで交わされているおばさんたちの会話を隣りの席でなんとなく耳にしてしまったような気分。『風花』の方がよかったな。
好み度ということでは★★☆☆☆
さて、次は『名画の言い分 巨匠たちの迷宮』木村泰司/集英社。フェルメールから読み始めよう。

■ 松本市大手(松本駅から北へ徒歩で5分くらい)のところにあるレトロなビル。
さて困った、建築探偵失格な私はこのビルを解説することが出来ない・・・。が、少しだけ試みる。建築年代は、戦前、おそらく昭和初期(昭和8年だと分かった)。3階の縦長の窓の窓台はさて・・・、スクラッチタイルが貼ってあったかな? スクラッチタイルは当時よく使われたが。コーナーを丸く面取りしてあるが、これも当時の建築の特徴。
2階の正面の外壁だけ一部仕上げが違うのは何故? どうも今回の改修工事によるものではないようだ。建設当時1階は道路側に出ていてバルコニーになっていたが、昭和40年代に行われた道路拡幅のために後退させた、ということが分かった。外壁の仕上げの違いはその時の工事によるものであろう。
1階は内部外部とも改修されている。以前は薬局だったが、今は工房になっている。2階は今月4日にオープンしたカフェ+ギャラリー「LABORATORIO(ラボラトリオ)」。
今日の昼過ぎ、ここに初めて入った。内部はすっかり改修されていたが、レトロな雰囲気は保持されていた。
このビルが建て替えられていたら、魅力の乏しい街並みになってしまっただろう。街並みは各時代の建築によって重層的に構成されることで魅力的になる、と繰り返し書いておく。
追記
そうか、「LABORATORIO」という名前はむかし2階が「実験室」だったことに因んでいるんだ! 今度出かけた時オーナーに訊いてみよう。


■ 山形県の旧朝日村(現在は鶴岡市)は山形と鶴岡を結ぶ六十里越街道のほぼ中間地点にあります。私が月山の麓にあるこの村を訪れたのは80年8月のことでした。記録がないので旅程の詳細は分かりませんが、一日に数本しかないバスで山形から鶴岡に向かって移動したことは確かです。バス停の時刻表を撮った写真がありますから。
民家 昔の記録、今回載せた写真は多層(養蚕のために4層くらいの床で構成されています)民家の里として有名な田麦俣から程近い大網という集落で撮ったものです。
寄せ棟の屋根には平側と妻側に「ハッポウ」があります。棟の中央には箱型の煙出しがついています。棟はもともと樹皮(杉皮)で覆っていたようですが、このとき既にトタンに変わってしまっていました。それでも角材をX状に組んだ千木のようなグシが載っています。残念なことに棟の端部にあるはずの棟止板が残っていません。
昔は民家を訪ねて全国各地を巡りましたが、ここは再訪してみたい場所のひとつです。
下は望遠レンズを使って撮った写真です。当時は交換レンズも持って出かけていましたが、今はポケットサイズのデジカメを使って、安易に撮るだけになってしまいました。

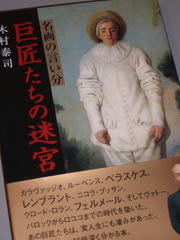
■ 前稿に書いた川上弘美の長編『これでよろしくて?』中央公論新社がなんと書店にあった。で、早速購入。このところ単行本で買い求める小説は川上弘美の作品くらいのもの。帯には**コミカルにして奥深い、川上的ガールズトーク小説**などという意味不明なコピーが。でも気にしない、気にしない。
しばらく前に注文しておいた『名画の言い分 巨匠たちの迷宮』木村泰司/集英社が届いた。
**バロックからロココまでの時代を築いた、あの巨匠たちは、実人生にも凄みがあった。名画の心が、100倍深く分かる本。**と帯にある。
本書で取り上げられているのはベラスケス、レンブラント、フェルメールなど有名な画家、8人。「絵の中に画家の人生を探す」という興味深い試み。これは面白そう。
よかった、2冊とも今週末読書に間に合った。
明日の朝早いので
 なさい、です。
なさい、です。


せいろう倉 木曽郡木曽町(旧開田村)にて 200904撮影
■ 板倉の壁の構法(壁の仕組み、構成システム)としては「落とし板倉」と「せいろう倉」があります。他にも柱・梁の骨組みの両面に板を張る構法もありますが、これは新しい構法でしょう。
前稿で「落とし板倉」を取り上げましたので、本稿では「せいろう倉」を取り上げます。
今年の3月、木曽の旧開田村で路上(ではないです、畑から)観察しました。右の写真を見ればあの正倉院の校倉造りと同じ構法であることが分かります。古くからある構法ですね。
落とし板倉をせいろう倉として紹介している資料もありますが、両者は全く異なる構法です。前稿の全景写真と比べればそのことが分かると思います。
せいろう倉という名称は蒸し器のせいろうに由来しているのでしょう。この倉を偶然見つけたときはうれしかったです。なにしろ初めて見たのですから・・・。
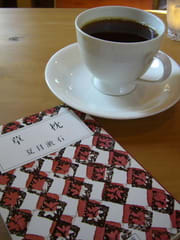
■ 秋の大型連休の中日、午前中書店で本を探すも購入に至らず。で、自室の書棚から『草枕』を取り出してカフェ・シュトラッセへ。
**智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。**
巻末の年譜を見ると漱石が作家活動をしたのはたったの十数年!。そうか・・・、知らなかった。それであれだけの名作を残したのだから驚きだ。いやいや、樋口一葉は一年ちょっとで『たけくらべ』『にごりえ』『大つごもり』『十三夜』などの傑作を書いた。
人生はその長短などにあまり意味がないのかな~。カフェの外の稲穂の波を眺めながらふと思った。
なぜ、漱石を読もうと思ったのだろう・・・。先頃再読した『こころ』はミステリー小説のようで面白かったが、この作品はどうも読みにくい。最後まで読みとおせるかどうか、今回も途中でパスしてしまうかもしれない。
でも・・・、日本を代表する作家をひとりだけ挙げよ、といわれればやはり漱石だろうな。
読書の秋、久しぶりに『我輩は猫である』を読んでみるか・・・。シュトラッセの看板猫(名前は何というんだろう・・・)を見ながら思った。

■ 大町市の郊外にある木崎湖、その湖畔の集落に一軒だけ残っている茅葺屋根の民家。以前からこの屋根が気になっていた。先日国道から脇道に入って、路上観察した。
寄棟の大きな屋根、この写真ではよく分からないが、棟端は2重棟になっている。棟の中央は煙出し棟。棟が鋼板葺きになってしまっているのは残念。だが、もはや絶滅危惧屋根構法となってしまった茅葺、貴重だ。周囲の民家のように鋼板で包んでしまわずにこのままの姿を維持し続けて欲しい。
この写真は30年位前に大町市の隣村、白馬で撮ったもの。この頃はまだ棟も健全、樹皮を押縁で押え、棟木を押え合掌で留めた棟覆いを見ることができた。



■ 「飯田市美術博物館」
原広司さんが「繰り返しの美学」するとこうなる。入道雲、形の違う構成要素の繰り返し。
館内、列柱。珍しく同じ形の柱の繰り返し。色の違う石を角柱の出隅に貼ってもよかったのに。鋼材で構成されたトラス。繰り返しているような、いないような・・・。
複雑な形の屋根は南アルプスをモチーフにしたとか。ちなみに京都駅の大階段は伊那谷、原さんの原風景。
■「いつも文頭につけている■の色に何か意味があるのですか?」と訊かれた。色には意味を持たせてはいない。なんとなく決めている。こう訊かれて、そうか、例えば内容によって色を変えるとか、なにかルールを決めておいてもよかったかな、と思った。
女優・石田ゆり子の『天然日和』幻冬舎文庫。
料理がとても好き、雑貨類が好き、スターバックス大好き。猫4匹、犬1匹と暮らしている・・・。
日々の生活のささやかな出来事を飾らず、気取らず綴っている。彼女の人柄が文章から窺える。
三崎亜記の『廃墟建築士』集英社。
先日 友人から借りた本。この本をリクエストした訳ではない。読書家の友人おすすめの1冊。
**七階を撤去する。廃墟を新築する。図書館に野生がある。蔵に意識がある。**と、帯でこの本に収録されている4編を紹介している。どれもシュール!
「七階闘争」 ビルの七階で事件が連続して起こったことが市議会でも取り上げられて、市長は**(前略)すべての七階を撤去する方向で検討いたしたく、全力を尽くす所存で、あります。**と答弁。それに対して七階護持闘争が起こる。七階に住む主人公はこの闘争に参加するのだが・・・。
ビルの七階を撤去する、六階の上が八階になるってどういうこと? 小説の中では一応説明されてはいるが、どうもその状況をうまくイメージすることができない。でも気にしない、気にしない。なかなか面白い状況設定で、一気に読んだ。
「廃墟建築士」 数年前、蝶のような名前の建築士が構造計算書を偽装した。あの事件からヒントを得たのではと思わせる小説。偽装することなくきちんと廃墟を設計、施工するって、この小説もなかなかシュール。
**今回の検査対象は、築十五年の「廃墟移行物件」だ。今回の移行検査で造反所見が無ければ、正式な廃墟として認定されることになる。**
「図書館」 図書館の本が館内を飛ぶ! 動物園の鳥たちのように。
**閲覧者に見られながら飛ぶことは多大な疲労を伴うため、夜間開館は一日おきに週三日までと制限されていた。**
「本の夜間飛行」を見せるというイベント、好評で期間を延長することになるが・・・。
Mさん、ありがとう。面白かったです。
■ 飯田といえば「リンゴ並木」。1947(昭和22)年の大火の後、当時の飯田市立飯田東中学校の生徒たちの提案によって生まれたそうですが、今では町を特徴付けるシンボルとして、すっかり有名になっています。
このリンゴ並木の両側にレンガ調のブロックが敷き詰められた歩行者優先道路が整備されています。この道路に沿ってオシャレなカフェやレストランが軒を連ねています(写真)。
この道路から路上観察した蔵、案内板によると1840(天保11)年に建設されたそうです。三つの蔵に分棟してあるのは、リスク分散のため。万が一火災に遭っても全焼は免れますから。
総二階建の蔵、なまこ壁が二階にまで及んでいます。扉付きの窓、窓周りの太い縁取りが印象的です。このように古い建築があると街並みに落ち着きが感じられ魅力が増します。「歴史の重層性」ってやはり都市の魅力には欠かせない要素なんですね。
白いのれんのお店「豆吉本舗」で買い求めた甘納豆は上品な甘さ、美味でした。
短編を8編収録している。主人公は30代の女性が多いが、彼女たちの振る舞いや会話がどうも歳相応に思えず、馴染めなかった。ただ、表題作で主人公のジョゼと男友達の恒夫の「コト」に至るまでの会話はアリかもしれない。いちばん面白く読んだのは短編小説のような山田詠美の解説だった。

次は、女優・石田ゆり子のエッセイ集『天然日和』幻冬舎文庫。ストライクゾーンど真ん中な好みの石田ゆり子。「釣りバカ日誌」のOL役、寂しげな表情がなかなかよかった。
いったいどんなエッセイを書くんだろう・・・。今週、隙間時間に読むつもり。









