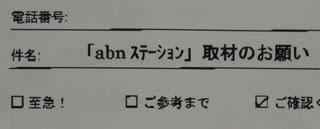火の見櫓は一体どんなところに立っているのだろう・・・。

朝日村にて

東御市にて
■ 火の見櫓の立地条件については、数多くの火の見櫓を観察して帰納的に求めることもできるし、火の見櫓の本義から論理的な考察によって演繹することもできるだろう。
いずれきちんとまとめなくてはならないが、とりあえず試論、いや雑考を・・・。
火の見櫓の本来の役割は火災の発見及び火災の状況把握、それから打鐘によってそれらの情報を伝達することにある。ただし火災の発見という条件は除外したほうが、実情に合っている。
以上から立地条件として
①火の見櫓から集落(地域)内全域を見渡すことができること
②半鐘の音が全域に伝わること
が挙げられる。更に、
③一刻も早く火の見櫓に駈けつけて打鐘することができること
という条件が加わる。
①と②及び③の条件を同時に満たすためには集落(地域)の中心的な位置であり、幹線道路沿いとか主要な生活道路の辻(交差点)に背の高い火の見櫓を建てればよい(*)。

長和町にて
これ(*)には
(a)背の高い火の見櫓は建設費が嵩む
(b)集落(地域)の中心的な場所に土地が確保できないなど、建設上の制約もあり得る。
そこで、例えば③の条件はあきらめて、道路事情のあまり良くない小高い場所に、(a)の解消のために背の低い火の見櫓を建てたり、①や②の条件を火の見櫓1基ではなくて、やはり背の低い火の見櫓を2基、3基と建てて満たすという選択がされたりする。
また(b)の解消のために、集会所や公民館、寺社の境内や参道などに建てたりもする。このような場合、①の条件がクリアできないこともあるだろう。 もっとも集会所は集落のコミュニティの中心地に建てられることが多く、火の見櫓の立地条件と重なる。

辰野町にて
地域によっては河川の増水や氾濫の状況把握という役目が火の見櫓に加わることもあるが、この場合には立地に河川の近くという条件が加わる。
また、隣の集落に火災の発生を知らせて応援を求めるために建てられる火の見櫓もあるが、この場合、立地は集落のはずれということになるのが一般的だろう。
集落の地形的な条件、地理的な条件がそれぞれ異なるから実際の立地状況は様々だ。
だから個々の火の見櫓の立地を観察して制約条件をどのように解決しているか、どう折り合いをつけているかを読み解かなくてはならない・・・。
やはり、多くの事例を観察してどのような所に立っているのか、傾向を分析、把握するのが妥当な方法か・・・。





























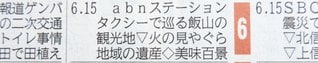


 汗
汗