
■ 「ヤバ! Y字路に沼るかも・・・」という記事を1月20日に書いた(過去ログ)。
Y字路に興味を持ったきっかけは、昨年末だったかと思うが、書店で『Y字路はなぜ生まれるのか?』重永 瞬(晶文社)を目にして、掲載されていたY字路のカラー写真を何枚か見たことだった。それ以来、Y字路が気になるようになって・・・。先日、本書を買い求めて読んだ。
小説を読んでいても、登場人物の名前が覚えられない。それから、例えばブルーバックスのような自然科学系の本を読んでいても専門用語が頭に入らない。このように記憶力が低下して、メモを取りながら読むようにしている。速記に近いような書き方だから、後になると自分でも読めない文字がある(と断っておくことにしよう)。
著者の重永 瞬さんは、まずY字路の定義を示す。それは「Yのかたちをした交差点」というもの。このような純粋なY字路はそう多くはないとのことで、トやXのような鋭角な交差点も広義のY字路として取り上げる、としている。
次に重永さんが示すのはY字路鑑賞の3つの視点。それは路上の目、地図の目、表象の目。次のように視点ごとにそれぞれ章立てして、Y字路を鑑賞している。
一章 Y字路へのいざない
二章 Y字路のすがた ―― 路上の目
三章 Y字路はなぜ生まれるのか ―― 地図の目
四章 Y字路が生むストーリー ―― 表象の目
五章 Y字路から都市を読む ―― 吉田・渋谷・宮崎
六章 Y字路とは何か
実におもしろい内容。たとえば二章は、Y字路のすがたの路上観察について。本書のカバー写真のようなY字路の角地がどのように使われているのか、何か所も(*1)観察・分析している。この章の各節の見出しを挙げればその内容が分かるだろう。
1 Y字路の角には何がある?
2 表層 ―― 角はY字路の顔である
3 角オブジェ ―― 角地の役者たち
4 残余地利用 ―― 「余った」からこその空間利用
5 角地のマトリックス
6 Y字路の角度は何度が理想か?
7 角壁面の長さ
8 Y字路の調査票
三章の「 Y字路はなぜ生まれるのか」はY字路の形成要因に関する論考。重永さんは地理学を研究する京大の大学院生とのこと。本書は平易で柔らかな文章で書かれてはいるが、はじめにきちんとY字路の定義と本書の全体の構成が示されているし、論拠を示しながらなされる分析的な論考は論文のようだ。角地の使われ方は建築学を専攻する学生の研究テーマとしてもおもしろいだろう。
これからは、本書をテキストに、Y字路の角地、Yの上のVの部分がどのように使われているか、観察してみたい。
塩尻市大小屋 2025.02.18
旧中山道(左)と国道153号(右)から成るY字路(五差路)
角はY字路の顔、ということで「角壁面」に看板が設置されている。「残余地」の「角オブジェ」は庚申塔や道祖神、蠶玉大神などの石仏・石神。
松本市城西 2025.02.16
木造の軸組構法(工法とは異なる概念)ではなかなか大変な仕事
**あくまで個人的感想だが、駐輪場や駐車場になっている角地は、あまりおもしろみを感じない。角地に建物がないと、Y字路特有のとんがり感は味わえない。私としては、建物が建て詰まったY字路のほうが嬉しい。**(67頁)と、重永さん。全く同感。このことについて、1月20日に次のような記事を書いた。
**単なる空地とか、花壇のような処理ではなくて、出来るだけ先っちょまで攻めて欲しいなあ。たい焼きだって、シッポの先まであんこが詰まっていたほうがうれしいじゃないか。これは、関係ないか。**
*1 何カ所、何箇所 何ヶ所 どれが一般的なんだろう。カとヶは、3カ所、3ヶ所のように算用数字に付ける時は使うかもしれないが、見た目が好きではないので、これからは「か」と「箇」を意識的に使いたい。












 ①
①
 ②
② ③
③ ③
③ ④
④
 ①
① ②
②


 360
360 280
280


 C形にした左手の人差し指と中指でカメラをがっちりホールド。右手で縦に構えたカメラの右下をホールド。両脇を絞めて手振れを防いで、右手の人差し指でシャターボタンを押す、って横道にそれちゃった。
C形にした左手の人差し指と中指でカメラをがっちりホールド。右手で縦に構えたカメラの右下をホールド。両脇を絞めて手振れを防いで、右手の人差し指でシャターボタンを押す、って横道にそれちゃった。


 ではなく
ではなく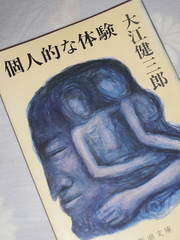





 360
360
