
■ 2021年11月、195稿目のブックレビュー。仮に毎月4冊読んできたとして、4×195=780冊か・・・。11月の読了本は6冊。
『中央本線、全線開通!』中村建治(交通新聞社新書2019年)
中央本線の誕生に多くのドラマがあったことを本書で初めて知った。タイトルに!が付いていることも分かる。このように記録に残すことは意義深いことだと思う。巻末に掲載されている参考文献の数がすごい。本書に調査の成果が十分活かされている。
『知ってるつもり 「問題発見力」を高める「知識システム」の作り方』西林克彦(光文社新書2021年)
『神話でたどる日本の神々』平藤喜久子(ちくまプリマ―新書2021年)
『シルクロード 仏の道をゆく』安部龍太郎(潮出版社2021年)
全く知らなかった中国の仏教的世界。文章を読まず数多くのカラー写真を見るだけでも、誰もが「すごい遺産だな」と思うだろう。掲載されている地図がもう少し詳しかったらよかったけれど。
『青嵐の坂』葉室 麟(角川文庫2021年)
**那美も山並を眺めながら、
「兄上がもっと幸せに生きられる道はなかったのでしょうか」
とつぶやいた。
「さて、どうであろう。わたしは義兄上は会うべきひとに会い、見るべきものは見て逝かれたように思う」**(327、8頁)
なるほど、会うべきひとに会い、見るべきものは見て、か・・・。
『法隆寺の謎を解く』武澤秀一(ちくま新書2006年)
**古来、列島に住む人びとはおだやかで変化にとんだ風土に馴れ親しんできました。(中略)建築と自然景観をトータルに把握する感性がありました。**(212頁)
本書にはこのような風土論的論考も。

(再)塩尻市広丘郷原 善光寺西街道郷原宿近く 3無無無型 脚・屋根・見張り台 無しをこのように表記するのが良いのかどうか。 撮影日2021.11.28


■ 櫓のてっぺん近くに小さい切妻屋根がある。以前はここに半鐘が吊り下げられていたに相違ない。だが、今は櫓の中間に半鐘が吊り下げられている。櫓のてっぺん近くまで登って半鐘を叩くのが大変だからというのが移設の理由、他には考えられない。できることなら小屋根も一緒に移して欲しかった。小屋根は地域の人たちの半鐘を大切に想う心の象徴だと思うから。少し離れたところから全形写真を撮っていて、脚元が気になって近くに行ってみた。
原因は分からないが、元の脚が曲がってしまっている。それで別の部材で補強している。横架材にも斜材(ブレース材)にも孔がある。何か不要な材を間に合わせ的に使ったのかもしれない。
火の見櫓は姿形もいろいろ、保存状態もいろいろだ。
■ 『法隆寺の謎を解く』武澤秀一(ちくま新書2006年)を再読した。
法隆寺には謎がいくつかある。例えば再建されたのか否かという謎。この謎については発掘調査などにより、再建説で決着がついているようだ。本書では法隆寺の謎についてざっと紹介して、なぜ法隆寺の中門には中央に柱があるのかという謎について論考している。この謎について7つの説を紹介しているが、その中では哲学者の梅原 猛氏が『隠された十字架』で論じた聖徳太子の怨霊を封じるためという説がよく知られている。著者の武澤秀一氏は建築家で、この謎について空間論的な視点から論じている。 560
560
法隆寺の中門 中央に柱がある。撮影日2015.01.24(33会の旅行)

金堂と五重塔が横並びに配置されている。
なぜ中門の真ん中に柱が立っているのか、この謎を解くにあたり、著者の武澤氏は創建当時の法隆寺では塔や金堂などが縦一列だった伽藍配置(このことは発掘調査で明らかになっている)が、再建されて金堂と塔が横に並ぶ配置(参拝券参照)に変わったことに注目して、一体なぜ縦から横へ配置を変えたのかについて論じている。このことに関連して、ずいぶん前にぼくは**大陸から伝わった左右対称の伽藍配置は日本人の感性には合わなかったのだろう。日本人の美的感性に合った、周辺の自然環境に同調するような配置を求めた結果だろう**と書いた(過去ログ)。武澤氏も**列島の風土、自然環境の中でつちかわれた空間意識が聖域の空間表現に反映したと思われるのです。**(274頁)と書いている。
中門から金堂と五重塔、正面後方に講堂を見る 撮影日2013.11.16
金堂と五重塔 撮影日2013.11.16
塔や金堂、講堂が縦一列に並ぶシンメトリックな配置にある強い空間秩序について武澤氏は次のように書く。**伽藍が完成しその雄姿を見せた時、その壮麗さに驚嘆し賞賛のかぎりをつくしたにちがいありません。しかし時が経つにつれ、どことなくしっくりこない感覚を覚えるようになったのではないか**(174頁 下線:筆者の私) そう、強い空間秩序はこの国の人の心性に合わず、すんなり受け入れることができなかったのだ。で、再建に際して金堂と五重塔を横に並べた・・・。
武澤氏は金堂、五重塔、中門が並ぶ様を見て**三つの建物がつくる構図のなか、中軸に立つ謎の柱が扇のカナメとなっている。度はずれて大きな中門、その真ん中に立つ重く太い柱。それが視界の全体をグイッと引き締めている。(中略)中軸上にこの柱がなかったならば、構図を支配している凛とした空気は得られなかったにちがいない。そこに残されたのは漠としバランスがもたらす、ただ穏やかというだけの凡庸な、しまりのない印象であったと思われる。**(167頁)と書く。このような印象が、なぜ中門の中央に柱があるのかという謎の答えとなるのかどうか、分からない。
武澤氏は最も早い横並び配置として百済大寺を取り上げ、塔の前にも金堂の前にも中門があったとみる、奈良文化財研究所の復元案を紹介してる。で、法隆寺の中門は二つの門をひとつにまとめたものであり、中央に柱があるのだと。この柱は前述のような効果も得られる一石二鳥の策だったとしている。
武澤氏の論考は横並びと縦並びの違いについて更に空間論的な論考を続け、また豪族に対抗して天皇が強い権威を示す意図を、この配置で示したとして、次のように書いている。**豪族たちによる大陸直輸入、タテ一列の伽藍配置を超えるものとして、ヨコ並び配置の系譜が天皇の血統から生み出された。**(231頁)本書の終盤のこのような論考については、本稿では割愛する。
日本人の心性にシンメトリックな形はしっくりこない、という私の持論(過去ログ)に重なる論考。
『法隆寺の謎を解く』 敬体と常体が混在した文章は読みにくく、残念だ。
 360
360
**「政を行うということは、いつでも腹を切る覚悟ができているということだ。そうでなければ何もできぬ」**(240頁)
『晴嵐(せいらん)の坂』葉室 麟(角川文庫2021年)を読み終えた。作者は読者に伝えたいことを登場人物のせりふに託す。上掲したのは主人公・檜 主馬のせりふ。
財政破綻の危機にある扇野藩(架空の藩)が舞台。新藩主のもと藩政改革を成し遂げようとする主人公の主馬と彼の義兄・慶之助。守旧派の家老や黒幕の大坂の豪商・舛屋との藩札発行をめぐる壮絶な戦い。主馬に敵愾心ともいえる感情を抱いていた慶之助が物語の展開と共に変わっていく。その様に惹かれる。
「青嵐の坂」には二人の女性が登場する。慶之助の妹で主馬の妻・那美と升屋の手代で、藩内の叶屋に目付役として送り込まれた妖艶な女・力。ぼくは生き様の違うこのふたりの女性の活躍の場がもっとあれば良かったな、と思った。力を主人公にした物語も読みたかった。
**「ひとはいま見える姿がすべてであろう。真のおのれなどどこにいるとも思えぬな」**と寂しげに言う慶之助に対して、**「いえ、ひとの真は、たとえいま目の前に見えなくともどこかにあって、そのひとを支えているのだと思います。たとえ、どのように違った道を歩んでもいつの間にか戻ってきてしまうのが、ひとの真ではないでしょうか。いつも自分の心の中のどこかにあるものを信じればよいのだと思います」**(262頁)と言う那美のことばは印象に残る。
物語のスリリングな展開と驚きのラスト・・・。


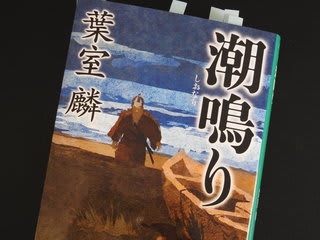




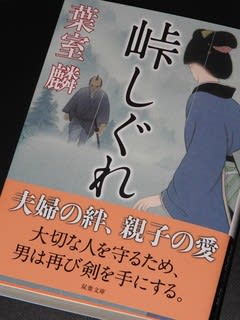
 320
320
■ 葉室 麟の作品では直木賞受賞作の『蜩ノ記』を最初に読んだ。2012年6月のことだった。登場人物の凛とした生き様に惹かれ、それ以降何作か読んできた(上掲写真、過去ログ)。先日書店で『青嵐の坂』(角川文庫2021年)を買い求め、読み始めた。 390
390
今日(24日)は朝カフェで読んだ。**悪に屈せず、信念を貫いた武士を描く、清廉極まる時代小説**とカバー裏面の作品紹介文に書かれている。「清廉」は葉室 麟の作品に共通するキーワードだろう。ストーリーの展開がおもしろいということも共通する。久しぶりに小説を読む楽しさを味わっている。
 ①
①
茨城県常総市水海道宝町 ②
②
長野県上伊那郡箕輪町松島
■ 上掲した2枚は「あ、火の見櫓!」写真展(@朝日美術館 10/16~11/7)で展示した写真。会場でこの2基の写真を漫然と見ていて、小屋付きの見張り台の様子が似ているなぁ、と思っていた。長野県と茨城県、ずいぶん離れた所に立っているのに・・・。
小屋の部分を撮った写真で比べてみた。4角形の櫓に円形の見張り台を設置して8角形の小屋を納めていることは共通している。屋根も8角形。窓の形も半鐘を吊り下げた位置も同じ。
細部を見る。屋根頂部の避雷針に付けた飾りの形が違う。常総市の火の見櫓の屋根③には蕨手が付いていない。箕輪町の火の見櫓の屋根④には付いている。半鐘の小屋根の有無、③には無いが④には有る。で、小屋根にも蕨手が付いている! 見張り台の手すりの形も使用材も違う。手すりの飾り、③には蔓状の飾りがあるが、④には飾りが無い。床の構成が違う。③には床を支える方杖が無いが、④には反った方杖が有る。こうして観察すると、両者細部の様子が色々違う。 ③
③ ④
④
やはり火の見櫓は十基十色だなぁ。

ブログ開設日:2006年4月16日(日)

■ 『シルクロード 仏の道を行く』安部龍太郎(潮出版社2021年)を購入した。安部さんは2013年に『等伯』で直木賞を受賞している作家。
書店でこの本を手にし、**遣唐使・阿倍仲麻呂に想いを馳せた河西回廊、天山南路の旅。西安、蘭州、敦煌、クチャ、カシュガル、パミール高原・・・ 仏教伝来の足跡から日本の源流を探る。**という帯の本書紹介文(写真)を読んで、購入して読もうと思った。**日本を花にたとえるなら、中国は根と幹であり、朝鮮半島は枝である。私のふるさとには「咲いた花を喜ぶならば、咲かせた根本の恩を知れ」という言葉があるが、(後略)**という文章にも納得して、レジへ。
内容の濃い紀行文を早速読み始めたが、掲載されているカラー写真を見るのも楽しい。中国は奥が深い、空間的にも時間的にも。
二部構成 第一部:西安から敦煌までおよそ1700キロの河西回廊をたどり、蘭州の柄霊寺石窟や敦煌莫高窟などを訪れる。(128頁)
**シルクロードの西の端はイタリアのローマ、東の端は日本の奈良だと言われるが、興味深いのはカシュガルが両者の真ん中に位置していることだ。**(271頁)

(再)塩尻市洗馬下花見 3無無無(3柱、脚無し屋根無し見張り台無し)撮影日2021.11.20
■ 2010年5月にこの火の見櫓を見ているが、その時は3基まとめて記事にしていて、それぞれ写真を1枚ずつ載せただけだった(過去ログ)。11年半ぶり再訪。この風景、懐かしい。
火の見櫓を見ている時、近所の方から声をかけられた。
「塗装でも、しなおすんですか?」
「あ、いや写真を撮っているんです」
「趣味で?」
「はい」
3角形の櫓。3つの構面のうち、正面の1面を梯子状に組み、他の2面にはブレースを設置している。構成部材は等辺山形鋼。小さい火の見櫓にあるタイプ。既に洗馬地区でも火の見櫓が何基か撤去されている。この簡易な火の見櫓が消えてなくなる日も近いのかも知れない。
半鐘の小屋根、片側は寄棟。 360
360
柱材と横架材はリベット接合、ブレース(斜材)とは溶接接合。
柱材と梯子桟とはリベット接合。溶接接合とリベット接合をどのように使い分けているんだろう・・・。
■ 『神話でたどる日本の神々』平藤喜久子(ちくまプリマー新書2021年)を読み終えた。プリマ―(primer)が「初歩読本、入門書」を意味する通り、この本は中高生を読者に想定して、日本の神話に登場する代表的な神々を親しみやすく紹介している。
観光などで神社を訪れる機会は誰にもあるだろう。その時、神社に祀られている神様(祀神)について知識があればより有意義な参拝になる。神について関心を持ち、神について知るための入門書。
**七福神やお稲荷さんのように全国的に知られている民俗神もいれば、その地域に固有の神もいます。日本には、たくさんの地域の民俗神がいますが、ここでは東北の「おしらさま」を紹介しましょう。**(189頁)このようにいきなり特定の神様にフォーカスするのではなく、できれば「たくさんの民俗神」の総体がわかるような、総論的な記述があれば有難かった。
日本の神々の名前や親子・兄弟などの関係については、覚えることができない・・・。ぼくの劣化脳では無理かも。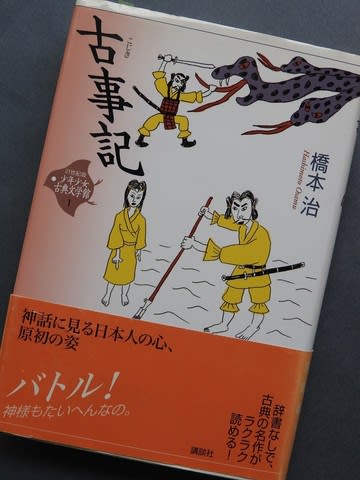
またこの本(*1)を読んで復習しよう。繰り返し学習。
*1 21世紀版 少年少女古典文学館 第一巻『古事記』橋本 治(講談社2009年) この本はおすすめです。

1318 諏訪市豊田上野 4脚444型 撮影日2021.11.14
■ 辰野から県道50号で諏訪市に向かう。諏訪市に入って間もなくこの火の見櫓と出会った。
背景に溶け込んでいて火の見櫓の全形が分かりにくい。加えて電柱に電線、防災行政無線柱。末広がりのフォルムは美しい。バランス的に屋根が少し小さいかな、などと勝手なことを書く。
反対方向からだと逆光で上手く撮れない。防災行政無線柱が邪魔をする。撮る方向が定まらなかった。
屋根面のカーブが実に美しい。

蕨手が目立つ。滑車の取り付け方に注目。
踊り場のつるりんちょ(表面が平滑)な半鐘は後から設置したのだろう。ブレースの間から腕を出して叩くことになる。半鐘に架けた小屋根は雪除けではないか、と写真展の会場で指摘を受けたが、機能はともかく、地域の人たちの優しい心のあらわれと捉えたい。
リングの上下でブレースの長さが極端に違う。
脚元。正面のみ脚、残り3面はブレースを設置してある。このような構成の場合、正面から櫓内に入り、梯子を登るようにしてあるものが多いが、この火の見櫓は左側面の外付け梯子を登るようにしてある。なぜ? 梯子を外付けするなら、4面ともブレースを設置して支障ないが・・・。道路から梯子を登るのかな。登りにくいと思うけど。脚がある櫓正面に梯子を設置すればよかったのに、と思う。櫓のユニットを繋ぐとき、向きを間違えて左向きにしてしまったのかな。そんなことはないだろうな・・・。
14日の火の見櫓と道祖神巡りの成果は以上、本稿で終わり。

1317 上伊那郡辰野町伊那富 4無444型 撮影日2021.11.14
■ 秋季全国火災予防運動の実施期間中(11.09~11.15)ということで放水訓練が行われたものと思われる。火の見櫓に掛けてある黄色い消火ホースが目立っている。他にも消火ホースを掛けた火の見櫓があった。消火ホースが無いときに改めて見たいと思う。
手すりが少し錆びているようだが、健全な状態が保持されていて好ましい。

踊り場に吊り下げた半鐘が一部錆びているのは打鍾の証。消火ホースが風であおられないようにするために細い丸鋼で、このようなものを何ていうのかな、名前が分からない・・・、「結束するもの」を手作りしてある。
消火ホースを束ねて固定してある。手動ウインチのハンドル。
古くなった消火ホースが消防団屯所の屋外に置いてあった。20mは長さ。消火ホースが見張り台に掛けてあると高さがわかる。この火の見櫓の場合、見張り台の高さ約9m。屋根のてっぺんまでは3m足して約12mと推測する。

ガゼットプレートを介して部材を接合しているが、全てボルトによる接合。

同町樋口下田 下田公民館の敷地内に立っている火の見櫓(1104)はリベット接合とボルト接合を併用している。接合方法を比較するつもりで載せたが、発錆状況の違いもよく分かる。
1984年(昭和59年)建設:某タヌキさんの「火の見櫓をさがして」による。

上伊那郡辰野町伊那富 左から二十三夜塔、庚申塔、道祖神 撮影日2021.11.14
■ 道祖神だけ祀られていることも、もちろんあるが、このように二十三夜塔や庚申塔と共に祀られている場合が少なくない。二十三夜塔は月に関係がある。月は太陽と共に信仰の対象で、飲食を共にしながら月の出を待つ行事が「講」を組織した人たちによって各地で行われていた。二十三夜塔は主にこの月待講で祀られた。十三夜塔、十五夜塔、十六夜塔、二十一夜塔など他の月齢の塔も祀られているようだが、二十三夜塔の他に実際に見たことがあるのは二十六夜塔。月見をすることもなくなってきているが、もっと月を愛でたいものだ。
男神と女神が握手している「握手像」 残念ながら顔の表情ははっきり分からないが、おおらかな雰囲気が伝わる。
鞍掛中 帯代七両 という刻字が読み取れる。



■ △形の自然石(このような形の石をよく探したものだ)に円い中区、そこに双体道祖神を彫ってある。男神が盃を、女神が銚子(酒を注ぐ道具)を持つ酒器像。顔の表情がとても和やかで印象的。公家装束。

(再)上伊那郡辰野町樋口 4無444型 撮影日2021.11.14
■ 県道19号沿いに立つ火の見櫓。上の写真の左端に樋口交差点の信号が写っている。既に数回見ているがこの方向から見るのは初めて。
なだらかなカーブを描いて末広がる姿が美しい。
見張り台周り、スッキリ。
ブロック造の消防倉庫の片流れ屋根の軒先近くをブレースが貫いている。道路側から見るだけではこのことには気がつかない。











