

■ 前稿に札幌ドームの構想を設計者の原さんは農具の「箕」から得たと書きました。雑誌で読んだ記憶があるのです。そう書いてからさて、どこに出ていたかな・・・、と気になっていましたが、「GAJAPAN 2001 7-8」に出ていることが、偶然分かりました。書棚から取り出したら表紙が札幌ドームでした。この雑誌は10冊位しか手元にありませんが、たまたまその内の1冊でした。
**もう一つは、構造に関することです。シェルは普通は閉じていますよね。今回はフィールドの出入りのため、一方に対しては開かなくてはいけなかった。さらに普通は閉じて壁で受けるものを、地形と連続した庭をつくりたいということもあって、周りをガラスにして浮かしたいと考えていました。
構造の佐々木さんも、絶対開いたモノをつくろうと固い決意で望んで(原稿のまま 臨んでが正しいと思いますが)いたようです。ところが、構造陣には非常に優秀な人たちが集まっていたにもかかわらず、なかなかイメージがつかめなかったみたいです。そこである時、ぼくが、農家で使う「箕」は閉じていないじゃないかと言ったのです。ざるは全部閉じているけど、箕は切れている。それで箕を買ってきて、みんなで検討して方向性が決まったのです。構造陣が出した解答は、開口のボウブリッジのところで、屋根の荷重とバランスさせるという非常に上手いものでした。**と原さんが語っています。
右側の内観写真の開口部にボウブリッジが写っています。分かりにくいですが(奥のかまぼこ形の開口の空中に浮かんでいます)。このブリッジがドームが両側に開こうとする力に抵抗しているんです。
ドームを野球モードにするとこの部分がちょうどセンター後方、バックスクリーン辺りになります。
野球中継ではボウブリッジを吊っている斜材が写ることがあると思います。が、野球中継ではなくて、外のフィールドも使ったスポーツ大会の中継の時だったかもしれません。
日本シリーズの中継で確認したいと思います。
日本シリーズは第1戦、第2戦が札幌ドーム、その後東京ドーム、そして再び第6戦と第7戦が札幌ドームで行われます。7戦まで戦ってもらえれば、ボウブリッジを確認する機会が増えるでしょう。
で、巨人が日本一!となるといいのですが・・・。
■ プロ野球クライマックスシリーズ、今日の試合で両リーグ共決着しました。セリーグは巨人、パリーグは日本ハム。楽天のピッチャー田中と巨人打線との戦いも見たかったですが仕方がないです。
ところで巨人の原監督と日本ハムの梨田監督の背番号は同じ、88ですね。原監督は選手時代の背番号が8だったから、それを並べたのでしょう。では、梨田監督は? それ程プロ野球に関心があるわけではないので、梨田監督の背番号88の理由を知りません。 調べてみると、前監督ヒルマンから引きついだ背番号とのことです。なぜ継承したのでしょう・・・ まあ、どうでもいいですね。
日本シリーズの試合が行われる球場、東京ドームは日建設計と竹中工務店の設計、オープンは1988年。札幌ドームは原広司、アトリエファイ他の設計、オープンしたのは2001年でした。
何年も前になりますが、東京のGAギャラリーで札幌ドームの模型をみたことがあります。原さんの建築に対する情熱、というか設計に注ぐエネルギーの凄さに圧倒されました。こんなに大きな模型をつくるのか・・・。ひとつひとつ客席までつくってある部分模型でした。
札幌ドーム(←参照)はユニークな形をしていますが、原さんは農具の「箕(み)」から想を得たと雑誌に書いていました。たしかに箕を伏せた形をしています(箕が?の方は画像検索してみて下さい。納得していただけると思いますから)。
注意深く野球中継を見ていると、不整形なドームを構造的に成立させている「しかけ」が写ることがあります。大きな開口部が、なんというか両側に開こうとするのを拘束するための構造です。箕は笊(ざる)とは違って構造的に閉じて(安定して)いないので、上から押されるとつぶれてしまいます。笊はその点かなり丈夫ですが。ですから設計も大変だったと思います。
さらにユニークなのが先の大きな開口部から出し入れする天然芝(サッカー)と人工芝(野球)との交換システム。屋外の天然芝のフィールドを空気圧で浮かせてドーム内へ移動させるのです。
北海道に出かける機会があったら、札幌ドームを見学したいものです。
■ 昨日、23日は二十四節気のひとつ「霜降」でした。が、私はブログへの「送稿」をパスしました。なんちゃって。さて、今回は久しぶりに「繰り返しの美学」です。
上の写真。南木曽町の社会体育館。大断面集成材のアーチでメインフレームを構成しています。そのピン支持の柱脚です。縦に下りているのは雨樋。
柱と基礎とのジョイント部分がこのように見えていると、それだけで大丈夫だなって、直感的に感じますね。
ところで橋は構造体そのもの、余分なものを纏っていないことが多いですね。そこに「すっぴんの美」、「必然性の美」を感じます。
それに対して、建築の場合は隠蔽傾向、構造体を隠してしまうことが多いようです。この柱脚は土木構造物と同様、構造的に必要なパーツだけで構成されています。
下の写真。大町市内のラーメン屋さん。
昔なつかしい街灯のようなデザインの照明器具が柱についています。いくつもつけることで店の賑わいを演出しています。これが侘びしく1灯だけついていたら、お客さんが集まらないでしょう。
今回は写真を撮っただけでしたが、次回はこの店のラーメンを味わってみたいと思います。
■ 血栓は血流を阻害する血液の塊。ダムは川の流れを阻害する土木構造物。このように一見全く関係など無いと思われる血栓とダムを「流れを阻害する」ものとして共通に捉えることができる。
ところで、渋滞と聞いてまず思い浮かぶのは交通渋滞だが、人の流れの渋滞もある。人の渋滞は時として事故に繋がる。東京のビッグサイトのエスカレーターで人の渋滞が起きてエスカレーターが「逆流」、ケガ人が出るという事故が起こった。昨年のことだったかな、記憶が曖昧だ。
2001年7月、花火大会が行われた明石市の大蔵海岸、会場近くの歩道橋で起きた渋滞は死者が出る事故になった。
血栓は血流を渋滞させ、ダムは川の流れを渋滞させるなどとは表現しないが、渋滞という概念をこのような現象にまで広げて捉えると新たに見えてくるものがあるような気がする。
今週の隙間時間で読もうと『渋滞学』西成活裕/新潮選書を購入した。渋滞学という異分野横断的な研究。
血流「渋滞」や川の流れの「渋滞」は、まさかこの本では取り上げていないと思うが、この本を読めば、今、政治的な話題になっている八ツ場ダム、このダムに限らないダムそのものの見方も変わるかも知れない・・・。
■ 歴史を川の流れに喩えるならば、司馬遼太郎は上空から俯瞰的に源流から河口まで、川の全景を捉えようとした作家だった。それに対して藤沢周平は川岸に立って、流れのディテールを捉えようとした。両作家はよくこのように対比的に捉えられる。
司馬遼太郎は歴史の流れをザックリと捉えてみせたし、川岸に立った藤沢周平は人々の日々の暮らしを捉えて作品にした。司馬遼太郎に「武士の一分」は書けなかったし、藤沢周平には「坂の上の雲」は書けなかった。
この週末に読んだ『日本人と日本文化』で司馬遼太郎は対談相手のドナルド・キーンに**やっぱり漢語では表現しにくい思いというものはあるかもしれないですね。ひょっとすると、これは少し大胆すぎる言い方ですけれども、上代日本人は「ますらおぶり」というものを、中国言語を通して学んだのじゃないか。だから原型的には、日本人というのは「たおやめぶり」の民族じゃないか。これはいかがでしょうね。**と発言している。
この発言にもものごとを大胆にザックリと捉えるという司馬遼太郎の特徴が出ていると思う。
この発言から対談は「ますらおぶり」と「たおやめぶり」について進んでいくが、ドナルド・キーンは**『万葉集』を読みますと、「ますらおぶり」というような調子の歌はかなりあります。(中略)一時的に無理して男らしさを発揮しても、ひとつあとの時代になると、男でも女でもまったく同じようなものを書くようになりました。ほとんど作家の男女が区別できない。場合によって、男の人が女性としてものを書きさえした。(後略)**と受ける。
残念ながら日本文学史の知識を全く持たないが、ふたりの対談を興味深く読んだ。
『日本人と日本文化』中公新書
1972年5月 初版
2003年5月 44版

■ 東京は新富町の町屋。3年半前、06年の4月に銀座から徒歩で10分足らずのところで偶然見かけました。どっしりとした店構え、貫禄があります。
今は本当に便利ですね。ネットで検索するといろんな情報を得ることができますから。
まず、地名から。新富町という地名の由来には諸説あるようですが、明治時代にこの辺りに新富座という劇場というか、芝居小屋があったそうで、新富町はそれに由来するという説がありました。説得力があるような気がします、なんとなく。
昔の地名には意味があるんですよね。地名は文化です、安易に変えて欲しくないです。
さて、屋根の上の看板に「大野屋」とありますが、この店が足袋の専門店であることは、路上観察で分かっていました。近くに歌舞伎座や新橋演舞場があって歌舞伎と縁のある土地柄、大野屋は歌舞伎役者御用達の足袋屋さん。
大野屋は創業が安永年間、今から230年くらい前とのことです。この建物は関東大震災のすぐ後に建てられたそうですから、80年くらい経っていることになります。
以下、写真観察。
1階部分の外壁は改修されてきれいになっていますが、2階部分の押し縁下見板張りは当時のままでしょう、きっと。
少し勾配がきつい瓦葺き屋根はどっしりとしています。立派な鬼瓦と棟瓦から受ける印象です。屋根の両端には今では使われなくなった風切り瓦がちゃんと載っています。
軒先は出し桁造り。太い部材が使ってあります。例によって小口を銅板で包んであります。それに銅板を加工した樋。
昔はこのような造りの町屋が軒を連ねていたんでしょうね。繰り返しの美学な街並みが浮かんできます。

■ 司馬遼太郎とドナルド・キーンの対談を収録した『日本人と日本文化』中公新書。今週末はこの本。ザックリと日本の歴史や文化を捉えての発言、面白そう。
NHKのテレビ番組「ブラタモリ」、今回が3回目の放送。タモリがかわいい久保田祐佳アナと街中に残る歴史の痕跡を探して歩く。そこから当時の様子を探っていく、タモリ流路上観察。番組ではCGを上手く使っている。なかなか面白い。次回、観察するのは銀座。どんな発見があるんだろう・・・。
昨晩はウイスキーを飲みながらこの番組を見ていた。
■ 14日付の信濃毎日新聞朝刊に「リニア中央新幹線」の東京―大阪間の輸送需要量や工事費などの新たな試算をJR東海が発表した、という記事が載っていた。そうか、このプロジェクトは東京―名古屋間で終わりではないのか・・・。
記事によると工事費がCルートと呼ばれる南アルプスを貫通するルートで8兆4400億円。維持運営費と設備更新費の合計が年間4240億円だそうだ(諏訪・伊那谷を回るBルートのデータも示されているがCルートより高い)。
記事を読んで「コンコルドの誤謬」を思い出した。
コンコルドは英仏両国で開発した例の超音速旅客機。開発の途中で採算が合わないと分かったが、巨費を投じたので、いまさらやめればすべてが無駄になるということで開発を続行したという「シロモノ」。そしてこのような誤りを「コンコルドの誤謬」と難しくいう。
リニアモーターカーはいまだに山梨リニア実験線で試験走行が繰り返されている。しかし「リニア中央新幹線」は本当に必要なんだろうか・・・。必要だから開発している、というわけではなくて、技術的に可能だからつくるというだけのことではないのか。
東京―大阪間を1時間ちょっとで結んだとしても、その前後の交通事情が改善されない限り、東海道新幹線を利用する場合と目的地までの所用時間はそれほど変わりないだろうに。このようにトータルな交通システムを考えればその一部を構成するだけのリニア中央新幹線の効果はずっと減るような気がする。
そもそもそんなに急いで移動する必要があるんだろうか・・・。現状で充分ではないのかな。そういえば昔「狭い日本 そんなに急いでどこへ行く」というコピーが流行った。
どう考えてもこのプロジェクトは「コンコルドの誤謬」の代表的な事例といずれいわれるようになるような気がする。いや、この手の誤りは「コンコルドの誤謬」に替わって、「リニア新幹線の誤謬」などといわれるようになったりして・・・。
開業時期は東京―名古屋間から20年後の2045年と設定している、と記事にある。まあ、そのころのことは確認できないが・・・。
■ 松本の山屋御飴所の屋外看板
山屋は創業が寛文12(1672)年、340年(!)近く続いてきた老舗の飴屋さんです。松本には昔から飴屋が多かったそうで、江戸時代には数十件もの飴屋さんあったともいわれているそうです。でも現在では数件しか残っていないそうで、山屋はその内の1件です(同店のHPを参照しました)。
今回路上観察したのは店の前の看板。

やはり山屋のHPによるとこの看板は明治時代のものだそうです。「御飴製造所」とあります。「御」という文字は屋根の直下で雨が掛かりにくいために比較的はっきりしていますが、一番下の「所」という文字は読みにくいですね。雨が掛かりやすい分傷みやすいですから。
それにしても丁寧に作られています。反りのついた屋根は銅板葺き。垂木(たるき)も当然すべて反っています。傷みやすい垂木の小口は銅板で包んであります。この写真では分かりませんが、柱から持ち出している梁(屋根を支えている持ち出し梁)には彫刻が施されています。看板の下にある腕木を支えている持送りにも彫刻が施してあります。
善光寺の灯ろうや松本市内の高橋家住宅(市内に現存する最も古いとされる武家住宅)を紹介した時にも触れましたが、柱は「根継ぎ」という技によって傷んだ部分が新しい部材に更新されています。
金輪継ぎという釘や金物を全く使わない継手が使われています。柱の角は古い部材に合わせてちょうなはつり(でいいのかな)の面取りがしてあります。
この飴屋さんの歴史を今に伝える貴重な看板です。
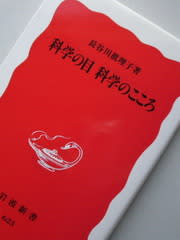
■ ある出版社のアンケートに答えて、図書カードをもらった。で、久しぶりに書店へ。川上弘美の『真鶴』が文庫になって、平積みされていた。手にとってパラパラと頁をめくって元に戻して、新書のコーナーへ。『科学の目 科学のこころ』長谷川眞理子/岩波新書を購入、読了。
岩波の雑誌「科学」に3年間にわたって連載された科学エッセイを収録。
「対称性と美的感覚」 人間の美的感覚と対称性の関係。これは繰り返しの美学に通じる問題、左右対称も繰り返しのパターンのひとつだから。
ヒトの顔を合成してどんどん左右対称に作っていくと、その魅力が増すという研究結果があるとのことだが、**そこで、ほんのちょっと対称をくずした顔が、もっと魅力的だと思われるらしい。**
続けて著者は次のように書く。**では、人間以外のものに対する美的感覚はどうだろう? きっちりと対称になった物体は、確かに美しいと感じられる。しかし、そこで対称性をわざと破ったものは、非常におもしろくて美しい。しかし、それは、そもそも対称性の美というものがあることを前提として、はじめて出てくるヴァラエティなのだろうか?**
私も繰り返しの美学について、同様のことを考え始めている。著者がこの問題についての見解を本書で示していないのは残念。
「建築物の自然観」 **数学的な線や物理法則は、なぜ人間の審美的感覚を刺激するのだろう? 自然界の生物が作り出す形は、なぜ美しくみえるのだろう? その答えは、数学や物理学ではなく、私たちの神経系の構成に関する生物学の中にあるに違いない。**
繰り返しを美しいと感じるのは何故か・・・、やはり答えは出てこないようだ。

■ このところ民家のことばかり書いていました。昔撮った写真などをネタに駄文を重ねてきました。以前、友人から「U1さん、建築の話題は読みませんよ」と言われたことがありました。一度民家モードから離れようと思います。少しは本も取り上げないと、バランスを欠いています。
西洋美術史家・木村泰司さんの『巨匠たちの迷宮 名画の言い分』集英社。
この本に登場する8人は巨匠とのことですが、名前くらいしか知しません。いや、名前すら知らない画家もいます。17世紀のオランダの画家レンブラントは、超が付くくらい有名。でもこの画家の人生については何も知りませんでした。
**富と熱狂の渦巻く市民社会が、画壇のスーパースターとしてもてはやし、そして頂点から引きずり下ろされた男。** この本では彼の人生をこのように括っています。
レンブラントの妻サスキアは優秀なビジネス・パートナーだったそうですが、30歳の若さで結核で亡くなってしまうんですね。そこから始まる人生の凋落・・・。彼は幼い息子の乳母と愛人関係に。それから自分より20歳も若い使用人に気が移り・・・。
こうした私生活の乱れが致命傷となって財政状態は悪化の一途、そして破産。画家はやはり顧客あっての人気商売。当時の厳格な市民社会が彼の不道徳を許さなかったんですね。
彼のドラマチックな人生を知り、この本に載っている「トゥルブ博士の解剖学講義」(この絵は画集かな、で見たことがあります。)や「夜警」、「織物商組合の見本調査官たち」、それから多くの自画像が一層興味深く見えてきました。
やはり「トゥルブ博士の解剖学講義」は傑作です(この画題で検索すれば絵がヒットします)。

小谷村の牛方宿の屋根(0910)
常陸幸田(当時)の民家の屋根(7910)
■ 民家の魅力は素材、技術(技術というか知恵とした方がいいかも知れないが)、労力 すべてその地域のものによって造られたところにある。
まず地域による素材の違い。それは屋根に顕著だ。屋根に使われる材料には板、樹皮、茅、石、竹などがある。
上は長野県小谷村の民家。山間地だから「木」の入手が容易。それで棟納めに木と樹皮(たぶん杉皮)が使われている。下は茨城県内の民家。棟納めに使われているのは平野部で容易に入手できる竹と茅。
このように実証すれば、民家の構法が地域によって異なることが理解できると思う。
屋根棟の部材はそれぞれ雨仕舞や腐朽防止上意味を持っている。上のふたつの屋根の部材には不要なものが無い。嘘が無いと言い換えてもいい。このことにこそ民家の美がある。

■ 改築された全国の駅舎のデザインには全く地域性がない。特に新幹線の駅舎はどこも同じ。金太郎飴駅。長野駅も前の駅舎の方が長野らしかった。松本駅も然り。
でも地域性とは何かと問われると答えに窮する。松本らしさ、松本をデザインするとはどういうことか・・・。蔵をモチーフにすれば、それでOKか?
地域の「材料、技術、労力」で造られた民家の造形には「地域性とは何か?」という問いの答えがある、と思う。が、それは「ユニバーサルな現代建築」で実現可能なのだろうか・・・。それは無理だということは端から明らかではないのか??
このことについてはいずれ書かなくてはならないだろう。今回は課題の備忘にとどめる。
■ 先日「歴史の重層性にある街並みの魅力」などと大層なタイトルを付けてしまった。「歴史の重層性」って何?、一体どういう意味? 当然の疑問だ。
秩序のヨーロッパ、混沌のアジア・日本。
ヨーロッパと日本の都市の構造、街並みの特徴の違いは一般的にはこのように対比的に捉えられる。ヨーロッパの街並みは限定されたデザインコードに拠ってのみデザインされた建築のファサードの連なりによって成り立っている。そこにはゆるやかに秩序づけられた美しさが在る。繰り返しの美学の街並み。
一方、この国の街並みは実に混沌としている。隣りあう建築の間にデザインの関連性など全くない場合が多い。この国の街並みで「秩序づけられた美しさ・繰り返しの美学」は歴史的街並み保存地区、そう昔の宿場のような街並みにのみ例外的に存在する。
東京の表参道は有名建築家によってデザインされた建築が街並みを形成しているが、そこには街並みとしての秩序は存在していない。いかに独自性を出すかにデザインの主眼が置かれ、統一感が全くないバラバラな街並みが形成されている。唯一の救いは大きなケヤキの並木だ。
この国の街並みの魅力を考える時はこの混沌とした状態を前提とせざるを得ない。ならば、せめて大正から昭和初期、戦前、そして戦後まもなく建てられた古い建築も共存する、つまり何層かの歴史の重なりが見られるような街並みに、魅力を見出そうという考え方があるのではないか。
このことを「歴史の重層性にある街並みの魅力」と表現した、という次第。
以上、先日のブログのタイトルの説明。

■ 夕佳亭(せっかてい)。このところ何枚か茅葺の写真を載せています。で、ふとこの茶室を思い出しました。そういえば金閣寺の境内にも茅葺があったな、と。
今年の2月、中年オジサン仲間で京都旅行をしたときにこの茶室もチラっと見学したのです。
夕暮れ時、ここから眺める金閣が夕日に映えて美しいことから、夕日に佳い茶室という意味の夕佳亭と名付けられたそうです。確かに茶室にしては随分開放的です。
寄棟屋根の棟は雪割と呼ばれる竹とからすと呼ばれる藁束、からす押えと呼ばれる竹によって構成されています。京都方面に見られる棟納めです。残念ながら、このときは建築観察など二の次でしたから、棟の詳細が分かる写真は撮っていません。
まあ、この1枚を撮っていただけで可としておきます。









