

■「繰り返しの美学」で最初に取り上げたのがこの建物でした(昨年の6月)。上の写真はまだ何を撮りたいのかはっきりしません。
今日、下の写真を撮りました。何を撮りたいのかはっきりしてきています。「建築の構成要素の繰り返し」にきちんと迫っていて余分なものは写していません。
これは堆肥舎です。別に美しさなど必要ないかもしれませんが、いえ建築は用途が何であれ美しくなくてはいけません。コンクリートの腰壁とその上の鉄骨の柱、そして小屋組みの繰り返しが美しいです。よく見ると腰壁の型枠の痕が分かりますが、それも揃っています。
黄色い重機はこの写真のアクセント。繰り返し感を強調するために後方を端まで写していません。まだずっと続くような印象を与えます。
今年最後の繰り返しの美学は原点回帰。来年はどんな繰り返しの美学と出合うことができるでしょう・・・。


















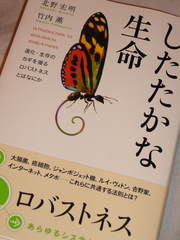







 「バイオミミクリー 生物模倣」。生物の形や生態系そのものにヒントを得て様々なものやシステムのデザインに採り入れること、とでも理解すればいいでしょうか。
「バイオミミクリー 生物模倣」。生物の形や生態系そのものにヒントを得て様々なものやシステムのデザインに採り入れること、とでも理解すればいいでしょうか。



