11月に読んだ本6冊のレビュー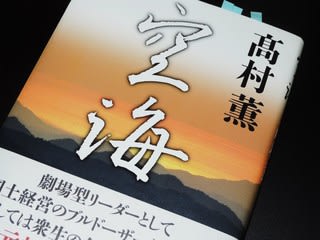
『空海』 高村薫/新潮社
■ 昨年(2014年)の4月から月2回のペースで新聞に1年間連載された「21世紀の空海」をまとめたもの。毎回熟読していたが、本書で再読することができた。
**日本古来の自然やアニミズムを滲みこませた身体の直接体験と、中国語の論理や修辞が合体したとき、まさに空海独自の比類ない密教世界が開かれた。** 「終わりに」 183頁
804年空海を乗せた遣唐使船は約1ヶ月漂流した後、福州に漂着した。このとき肥前国田浦を出航した遣唐使船は4隻、内2隻は行方不明になっている。
このとき空海が無事長安に入ることが出来なかったら・・・、恵果が生きていなかったら・・・、空海が後継者に指名されなかったら・・・。
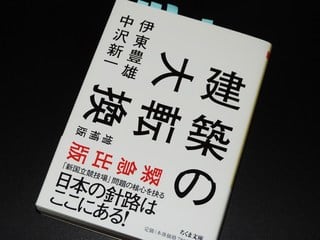
『建築の大転換』 伊東豊雄・中沢新一/ちくま文庫
**人間と自然環境を切り分けるのではなく、人間と自然との密接な関係を前提として緻密な配慮に基づいた計画が必要なはずです。**(72頁)
伊東さんのこの言葉が本書のポイントと解した。このような理念に基づいて計画された伊東さんの最新作「ぎふメディアコスモス」を見学しなくては・・・。

『銀の匙』 中 勘助/岩波文庫 1935年11月30日 第1刷発行
名作は読み継がれる。少年時代の思い出、心情をこれほど詳細に瑞々しく綴れるとは・・・。
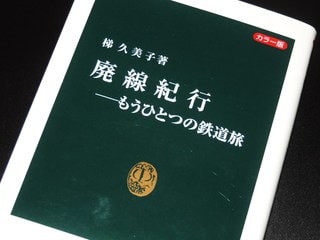
『廃線紀行』 梯久美子/中公新書
**廃線とは地理と歴史が交わる場所(後略)**204頁
**昔の路盤を歩いていると、今自分が踏んでいる土の上を、かつて多くの人々の人生を乗せて列車が走っていたことを実感するのである。**204頁
土地は歴史を記憶するという梯さんのことばは、火の見櫓は歴史を記憶すると言い換えてもよいだろう・・・。
マニアな世界は他人の理解の及ばないところにあるものだが、本書を読んで共感することが少なくなかった。

『事故のてんまつ』 臼井吉見/筑摩書房
川端康成自死の真相、深層。

『伊豆の踊子』 川端康成/新潮文庫
出会いと別れ、人生は寂しい・・・。
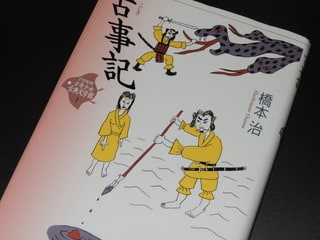
『古事記』 太安万侶・撰録 橋本治/講談社
上、中、下巻の三巻から成る古事記の上巻、神話の世界をわかりやすい現代文にしている。神様たちのはらはらどきどきわくわく大冒険、小学校高学年生なら楽しく読むことができるだろう。注釈はきっちり大人向け。



































